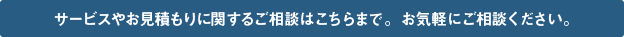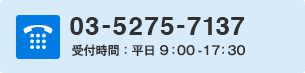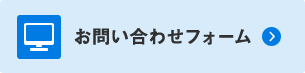社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会様
84箇所のグループホームの家賃・光熱水費の請求業務を効率化。支払い代行から利用者402名の金額算定まで一気通貫で対応!
提供サービス:決済サービス
インタビュー

事務局次長(地域生活支援統括センター長) 牧野隆行様
地域生活支援統括センター 主任 土田栄様
障がいのある方への支援をおこなう東京都手をつなぐ育成会。誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のため、特に大切にしているグループホーム運営を中心に、幅広いサポート事業を展開しています。
同会では、グループホーム運営現場の業務負担を軽減し、スタッフが利用者様に向き合える環境を整えるべく、請求業務のアウトソースを決断。熟考の末、FOCの集金代行・収納代行サービスを導入されました。
今回は導入の経緯や効果について、事務局次長(地域生活支援統括センター長)の牧野隆行様、主任の土田栄様に話を伺いました。
もくじ
1. グループホーム利用者の家賃や光熱水費を個別に現金徴収。請求書の発行や精査に追われていた
2. 現場の負担軽減のためクラウド型の請求代行サービスを検討。FOCのサービスを選んだ決め手は
カスタマイズ性の高さ
3. 導入後は2名で84箇所のグループホームの請求業務を完結。家賃・光熱水費の現金管理は一切不要
に!
4. 請求業務効率化の効果を実感。今後はさらに複雑な食費請求もアウトソーシングを検討中
グループホーム利用者の家賃や光熱水費を個別に現金徴収。請求書の発行や精査に追われていた

― 東京都手をつなぐ育成会様の概要を教えてください。
牧野事務局次長(地域生活支援統括センター長):
当会は昭和36年に東京都で障がいのある子どもを持つ親の会として発足しました。現在は居住支援や就労支援、相談業務などさまざまな事業を運営しています。グループホーム事業は設立当時から力を入れており、現在は都内に84箇所のグループホームを運営し、402名の利用者様が共同生活を送っています。
私はグループホーム事業を統括する地域生活支援統括センターの責任者、主任の土田は経理業務を担当しています。
― グループホーム部門はどのような体制で利用者様への支援をおこなっているのですか?
各グループホームには世話人や生活支援員がおり、利用者様の生活をサポートしています。エリアごとにホームを統括するセンターが5箇所あり、サービス管理責任者が担当エリア内のホームを巡回して世話人や生活支援員、利用者様のフォローをしています。
― サービス導入前に抱えていた課題を教えてください。
課題は、家賃と光熱水費の請求フローが煩雑だったことです。各ホームの家賃は利用者数で案分しますが、施設によって4〜7名の幅で人数が異なるうえ、家賃も地域ごとに違います。そこに毎月変動する光熱水費が加わるので一律の金額を請求することができません。世話人は家賃をその都度で合算・等分し、利用者様から集めていました。また、光熱水費は毎月定額で利用者から徴収して支払い、6ヶ月ごとに精算をしていました。結果として、ホームに毎月届く請求書は全体でおよそ500枚程度になり、現場はいつも請求業務に追われていました。
― 当時の請求フローと問題点を詳しく教えてください。
まず世話人がホームに届く家賃の請求金額を確認し、利用者数で案分します。世話人は請求書や領収書を手書きで発行し、その金額を利用者様から現金で徴収したものを取りまとめ、銀行やコンビニで支払いをおこなっていました。
この請求フローの場合、金庫で現金を管理するリスク、帳簿をつける労力も生じます。預かりの事実を残すために業務日誌をつけるなどの記録業務も負担でした。毎月の締め作業も大変で、月末〜月初の1週間ほどは世話人向けの研修を入れないよう本部も配慮していました。
苦労していたのはセンターのサービス管理責任者も同様です。サービス管理責任者は担当ホームを巡回し、帳簿のチェックや現金精査など、世話人の請求業務を日常的にフォローします。さらに、ミスや現金のズレが生じるたび訪問して訂正しなくてはいけないため、約15名いたサービス管理責任者は世話人の請求業務のフォローが主な業務になっていました。
こうした頻繁な巡回による交通費・時間コストの高さは長年の課題でした。現金管理のための専用端末を導入することも考えましたが、多くて7名ほどのホームすべてに端末を導入するのは不経済という判断でした。
現場の負担軽減のためクラウド型の請求代行サービスを検討。FOCのサービスを選んだ決め手はカスタマイズ性の高さ

― 集金代行・収納代行サービス/スマートインボイスを導入された経緯をお聞かせください。
現金での管理リスクや業務負荷を懸念する声が高まったことで、2019年から請求業務を効率化できるサービスの導入を意識しはじめました。
まずは、最も簡単に思われた家賃の口座振替をおこなおうと考えました。以前より付き合いのあった三菱UFJファクター(株)様に相談したところ、FOC(当時はNOC)を紹介していただき、集金・収納代行サービスというものを知ったのです。
並行してほかのサービスも検討し、最終的には2・3社のサービスが候補となりました。それぞれ慎重に比較し、導入した場合の請求フローを策定しながら一年かけて検討し、最終的にFOCのサービスを選びました。
― サービス導入の決め手は何でしたか?
決め手となったのは、FOCの担当者からいただいた提案です。当会の課題を解決するには、スマートインボイスのシステム機能を使った請求書発行や収納代行にプラスして、FOCのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を組み合わせたサービスが最適だとご提案いただきました。特に驚いたのは、家賃・光熱水費をまとめて、案分して利用者様ごとの金額を算出してくれるというBPOサービスの活用アイデアです。最低限のコストではじめながら、必要に応じてサービスを追加できるカスタマイズ性は大きな魅力だと感じました。
請求書のフォーマットや項目についても多くの要望を出しましたが、根気強く対応いただき、FOCならば当会の悩みに特化したオーダーメイドのサービスを作り上げてくれると確信しました。
これらに加えて、当会に類似した事例を紹介いただいたことで、導入後をイメージしやすかったことも決め手の一つです。これなら本部と現場の行き来の少ないシンプルな請求フローが実現しそうだと期待が高まりました。
最終的には、信頼していた三菱UFJファクター(株)様からの紹介という安心感が後押しとなり、2020年にサービス導入に至りました。
― 導入を決めてからの、関係者の反応はいかがでしたか?
おおむね好意的でした。とくに上層部は前向きでしたね。現場の苦労を感じていたので、新しいシステムを入れる不安よりも、一刻も早く現場の現金管理をなくしたいという思いが強かったのだと思います。
土田主任:
新たに請求業務を担当することとなった私たちも、自らマニュアルを作り、実地で試行錯誤することで操作に慣れていきました。不明点があるときはFOCの営業担当者が訪問した際や、メールで教えてもらうことで解消することができ、サポートにも満足しています。
現在は家賃と光熱水費に加え、日用品費の請求もスマートインボイスを活用しています。
導入後は2名で84箇所のグループホームの請求業務を完結。家賃・光熱水費の現金管理は一切不要に!

― 導入後はどのような変化がありましたか?
牧野事務局次長(地域生活支援統括センター長):
最大の課題であった現場での現金預かりや帳簿付けは、家賃と光熱水費については一切廃止になりました。代わりに本部に土田を含む2名の担当者を置くことで、現在まで業務が問題なく回せています。402名の利用者様への請求業務を一手に担う部門としては少ないのではないでしょうか。84箇所のグループホームの世話人と、精査に追われていたサービス管理責任者の課題の一部を解消できました。
― 導入後の請求フローを教えてください。
土田主任:
現在は光熱水費の請求書は直接FOCに届くように変更しました。FOCで支払いを実行したのち、各ホームの利用状況に合わせ、利用者様ひとりあたりの請求金額を算出します。利用者様の人数はもちろん、月内に入居や退去される方がいる際は日割り計算をするなど、複雑な条件にも対応していただいています。
金額が確定した後、利用者様の請求データを当会に送ってもらい、私たちは目視でチェックします。計算精度は高く、利用者様のイレギュラーな事情がない限りは手直しすることはほとんどありません。請求データをスマートインボイス上にアップロードし、自動で請求書を作成します。
完成した請求書はFOCから各ホームに向けて送付されます。そして、利用者様の指定口座より振替をして完了です。当会でおこなうのは請求データのチェックとシステムへのアップロードのみと、請求フローの大半をアウトソーシングしています。
― 導入前の課題であった、現場の負担軽減はどの程度実現されましたか?
牧野事務局次長(地域生活支援統括センター長):
世話人やサービス管理責任者は、請求にまつわる業務の一部がなくなり、負担が軽減されました。苦労していた締め作業から解放されゆとりが生まれたことで、これまでよりも利用者様のサポートに集中できるようになったという声も耳にします。
現金保管のリスクにともなう世話人の精神的負担が一部解消されたことも有意義でした。
また、サービス管理責任者にも変化がありました。請求業務のフォローが軽減され、空いたリソースで障がいを持った方たちの支援や、現場のマネジメントといった本来の業務に専念できるようになったのは喜ばしいことです。
さらに、現場と本部の両方で効率化が図れたと感じているのが請求書・領収書の発行業務です。
少し複雑な話になりますが、グループホームを利用される方は、自治体より自立支援給付費を受けています。自立支援給付とは障害福祉サービスを利用される方を対象とした制度で、利用者の状況に応じて自己負担金額が定められ、超過分に対し支給されるものです。事業者は自立支援給付費の自己負担部分、さらに当会の場合はグループホームでの家賃や光熱水費、日用品費などの実費分も含めた請求書と領収書の発行が求められています。
以前は自立支援給付費に関しては本部で請求書・領収書を発行して手作業で発送、家賃や光熱水費などは世話人とサービス管理責任者が手書きで発行するという、負荷の高い方法を取っていました。
しかし、FOCのサービスを活用してからは、請求書・領収書に自立支援給付費だけでなく家賃、光熱水費、日用品費の項目を加え、合算金額がわかるようになっています。現場で対応するのは食費のみとなり、業務のスリム化に貢献しています。なおかつ発送まで代行していただき、本部の労力も節約できました。
現状、自立支援給付費の請求書・領収書については紙で発行するよう行政より要請を受けています。また、当会にはデジタル対応が難しい利用者様も少なくありません。紙での発行もできるスマートインボイスは当会にフィットしたシステムだと感じています。
請求業務効率化の効果を実感。今後はさらに複雑な食費請求もアウトソーシングを検討中

― 今後はFOCのBPOサービスをどのように活用されていこうと考えていますか?
グループホーム事業の本来の目的は、障がいのある方が安心して地域で暮らせるようにサポートすることです。現場スタッフは利用者様の支援に専念するべきであり、管理部門は彼らが業務に集中できる環境を整えることがミッションだと強く感じています。今後もFOCのサービスを活用し、現場のバックオフィス業務の負担を減らせる仕組みづくりに積極的に取り組む所存です。
例えば、食費の請求業務もアウトソーシングしたいと考えています。実は導入後、効果を実感した現場から「食費の請求もやってほしい」との声が多く上がっていたのです。現在、試験的に4つのホームでの食費の請求業務代行がスタートしました。将来的にはすべてのホームで展開できればと考えています。
― FOCのBPOサービスの導入を検討する企業に、メッセージをお願いします。
請求業務や収納業務は大変ですが、自社で「やれなくはない」業務だと思います。しかし、労務リスクや現金管理リスクを加味すれば、信頼のおけるアウトソーシング業者に任せるのが最もコストが低いと言えるのではないでしょうか。
アウトソーシングによって現場スタッフが本来の業務に専念できる環境を作り、従業員全員が同じ方角を向いて生み出す社会的価値の大きさをぜひ実感してほしいと思います。
― 取材にご協力いただき、ありがとうございました。
社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会:Webサイト
■企業情報
| 従業員数 | 2,030人(常勤1,140名/非常勤890名) |
|---|---|
| 事業内容 | 障がいのある人が主体性を持ちながら暮らせる共生社会を目指し、生活支援・就労支援・相談業務など幅広いサポートを提供。すべての人が安心して暮らせるよう地域社会の福祉課題の解決にも積極的に取り組んでいる。 |
背景
・運営するグループホームは、利用者ごとに請求金額が異なる設計。そのため、現場担当者は利用者ごとに請求金額を算出する必要があった。
課題
・現場担当者はグループホームの運営費用を案分し、手書きで請求書を発行。現金で料金を徴収して帳簿を作成するなど、一連の請求業務の負荷が高い状態だった。
・エリア担当者は請求業務をフォローするための巡回業務が頻発しており、人的コストの高さも課題となっていた。
改善ポイント
・FOCのBPOサービスを導入し、グループホームごとの家賃・光熱水費および一部の日用品費を合算、利用者ひとりあたりの請求額算出をアウトソーシング。
・スマートインボイスを活用し、請求書発行を自動化。
・請求額に基づき利用者の口座振替を行い、一部の現金徴収が不要になった。
導入の成果
・現場担当者による現金の管理、それにともなう帳簿作成が一部不要になり、コア業務である利用者の生活支援に集中できる環境が実現した。
・巡回業務が減少したエリア担当者は、現場のマネジメントに専念できるようになった。利用者と現場担当者の満足度向上に力を発揮している。
この業務の関連サービス
他の事例を見る
-
(公財)世界自然保護基金ジャパン(WWF)様
給与計算をアウトソーシングすることで、
社内の意思決定や制度化の速度が増した -
独立行政法人 P法人様
「調達」での膨大な書類手続きを一元管理し業務工数を大幅に削減