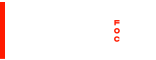業務内容をヒヤリングし、マニュアルを作成した。そして、保険会社のフロアの一角を与えられ、業務はスタートした。当初はリーダーとオペレーターの2人体制でのはじまりだった。スーパーバイザーとして、この案件を担当した加賀は、スタート後の1ヶ月間、現場にはりついた。毎日、顧客の担当者とその日の業務内容について確認した。
業務内容をヒヤリングし、マニュアルを作成した。そして、保険会社のフロアの一角を与えられ、業務はスタートした。当初はリーダーとオペレーターの2人体制でのはじまりだった。スーパーバイザーとして、この案件を担当した加賀は、スタート後の1ヶ月間、現場にはりついた。毎日、顧客の担当者とその日の業務内容について確認した。
「私をはじめ、FOCスタッフが社内にいることで、イレギュラーの事態にも迅速に対応することができます。さまざまな方とコミュニケーションをとることができます。営業的な話になりますが、顧客の懐に入るという状況は、仮に競合他社が入ってこようとしても、大きなアドバンテージになります」
名刺のデータ入力など、スポット的な業務だが、ほかのセクションからも声がかかるようになっていった。加賀は、改めて、オンサイトで業務が行なえることの意味と価値を実感した。
本来の業務を受託している部署から別部署へ異動した社員からも新たな業務の依頼を受けた。紹介されて、広がっていった社内の人脈もある。アウトソーシングの会社としての立場からメリットがあることはもちろんだが、視点を変えて、顧客企業の立場からも、価値ある存在になっていたのだ。
「外部からではわからないことも、中に入ることで見えてくるものがある。企業の仕組みや組織まで理解できる。だから、改善への新たな提案につなげることができるのです」。もちろん、失敗もある。しかし、現場にいることで日々ブラッシュアップし、修正していくことができる。B社のケースでは、加賀は時にはイニシアチブをとって、社内の課題解決にあたることもあるという。加賀の思い描くアウトソーシングと顧客企業との理想的な関係が、構築されているようだ。
加賀には、忘れられないプロジェクトがある。
3年ほど前に前任者から引き継いだ別の保険会社C社の案件だ。
代理店からFAXで送られてくる手書きの書類をデータ化するというプロジェクトだった。
手書きとデータを照合し、校正する。細部にまで目を行き渡らせる必要がある業務だ。だが、そのプロジェクトを引き継ぐ前には、一時、運用管理体制の混乱から現場が困惑し、業務遂行力が明らかに落ちた。顧客は不満を募らせ、まさに悪循環に陥っていた時期があることを、加賀は事前に知らされていた。
プロジェクトの担当となった時には、前任の努力があり、一定の落ち着きを取り戻した時期ではあったが、取り組まなければならない課題は多く残されていた。
加賀は、まず運用体制を再構築した。スキルの足りない人材を一部交代し、残ったメンバーには運用上の些細な情報もできるだけ共有するように伝えた。現場のリーダーたちとは、毎週、定例のミーティングを実施するようにし、今までリーダー間で発生していた「運用に関わる情報を聞いていない」、あるいは「あの人はこう言っているようだが、その考えはおかしい」など、コミュニケーション不足から生じる不満を解消することに取り組んだ。顔をつき合わせ、意見をぶつけ合い、お互いが納得したうえで結論を出すことによって、少しずつ関係性を改善していった。
「約70人体制だったのですが、新規採用時には、このプロジェクト独自のスキルチェックを行ない、なるべく運用スキルに問題がない人を採用することで、人間関係を再構築しました。人間関係の不満が少なくなってくると、定着率も良くなり、スキルもあがっていく。スタッフたちの参加意欲も高まって、業務の品質も安定するようになっていきました。」
目に見えて、成果はあがっていった。それは、数字上からも一目瞭然の成果だった。
「“FOCの強みは何か”ということを理解して、その強みを活かし、いかにサービスとしてカタチに結びつけるかが私の使命です。アウトソーシングは、課題に対して、いかに最適な業務フローを構築し、その実行段階において品質の管理を行ない、運用する人材が最大限のパフォーマンスを発揮できるようにマネジメントすることが重要です。つまり常に現場に寄り添って、業務の品質を安定化することが重要なのです」
一般的にコンサルタントは、課題を抽出し、改善プランを提案することにとどまる。アウトソーシング、FOCは現場において改善を行い、その実行をもって効果につなげる。そこが大きな違いだと加賀は言う。いかに付加価値をつけて、業務を遂行していくか。言われたことを100%やるだけではいけないのだと、最後に付け加えた。