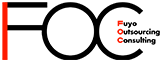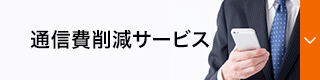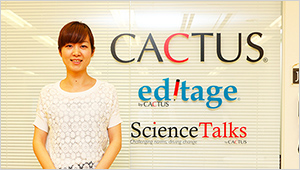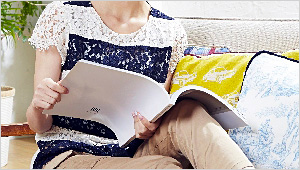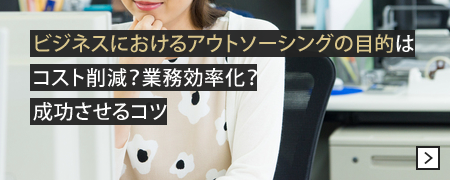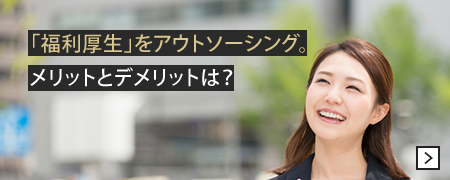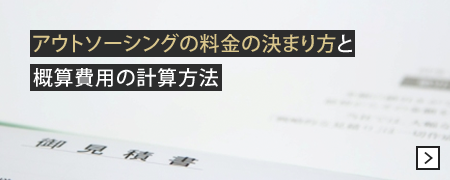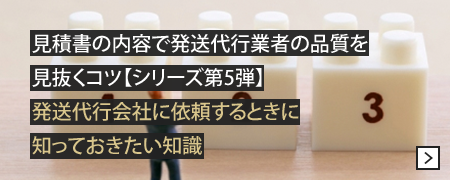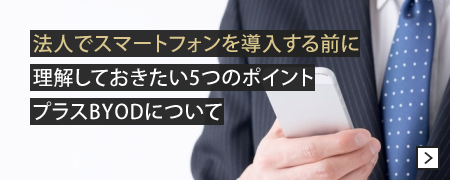コスト削減の7つの方法


共有可能な業務プロセスの洗い出しとダブリの解消
コスト削減を図るにあたり、まず、ビジネスをコアかノンコアに分類し、業務プロセスの可視化が必要です。 次に、業務プロセスごとに、その必要性や共有可能性について検討します。共有可能な業務プロセスについては、極力標準化を図り、業務プロセスのダブリの解消やシステムの有効活用を検討します。このとき、不要なプロセスを担当している社員の配置換えを検討するケースも出てきます。社員の配置換えについては、素養の有りなしはともかくモチベーションにも考慮する必要があります。 なぜ配置換えになるのか、上長はしっかりと説明する必要があります。終身雇用を前提にした事前説明なき人事権の発動は、一歩間違えると個人の問題ではなくその周辺の社員にも影響がでるためです。
FOCのサービス
複数回にわたるヒアリングやアンケートを実施し、業務項目の洗い出し、稼働工数、人員数、業務フローなど多岐にわたる調査を行い、業務のボトルネックや不必要な部分を見つけていきます。


申請承認手続きのシステム化(ワークフローの導入)
日本では、未だに紙ベースで申請承認手続きを行うほか、重要な稟議書の場合には、社員が関連部署を持ち回り、決済印を依願している会社が多いようです。 一方、欧米ではワークフローと呼ばれるイントラネットを利用した申請承認手続きを導入し、効率化とペーパーレス化を図る会社が多くなっています。また、ワークフローの導入を通じ、申請者と異なる承認者が承認しているか、承認が効率的に行われているか、検証や監査の精度の向上と効率化が図られています。 直接的なコスト削減というよりは、従業員の手続きに関わる時間コストを削減する観点が必要です。
FOCのサービス
お客様の業務がどういう流れなのかを把握して、最適なワークフローを作成します。紙とシステムに分けて管理されたい会社様にもご要望に合わせたサービスをご提案します。


サービスレベルの見直し
社外だけでなく社内の顧客(従業員)に対するサービスが過剰か否か検討します。あると便利で、かつ業務効率が向上するものなのかどうか、という観点で検討しましょう。 また、残業や業務負担の多い業務については、その原因がマネージャーの資質によるものか(終了時間間際にしか指示を出さないマネージャーもいるようです)、個々の業務の仕方なのかもしっかりと検証します。 ただ、社外に対してのサービスレベルが過剰であるという事実があっても、顧客のイメージが著しく落ちる可能性もありますし、社内に対してでは、退職リスクや昨今の採用難を考慮しないといけません。どちらにしても緊急事態でない限り、コスト削減という大名目で断行するのではなく、相手のことを考え、落としどころを探ることも重要です。
FOCのサービス
これまでの経験値から、無駄な承認プロセスや必要なプロセスをリスト化・整理し、よりお客様のニーズに合ったサービスレベルに整えます。


人件費の見直し
本当に正社員がやるべきものなのか否か、見直しをします。比較的新しい考えとして、標準化された業務や簡易な業務は、余った時間を活用したいという主婦やシニアを活用する、ということもあります。 助成金や補助金の制度もあるため、積極的な雇用を検討してみましょう。
FOCのサービス
標準化された業務や簡易な業務(ノンコア業務)を見える化し、アウトソーシングや派遣など、どのような方法が適当かをご提案します。


不動産費の見直し
一部の企業では採用され始めています。業務プロセスを行うべき場所について、自宅からの勤務(work from home)が可能か、その導入についても検討してみます。個人用のデスクなどのファシリティやPCなどIT機器を含めたオフィス関連費だけでなく、通勤手当といった福利厚生費の見直しも視野に入れることができます。
FOCのサービス
ファシリティ関連業務において、これまでかかった経費が妥当かどうか、仕様書等で判断させていただき、適正価格でのご提案をいたします。


一般事務用品の見直し
ワークフローは、決済手続きでのペーパーレス化だけでなく、経費や出張精算にも利用できます。紙ベースの事務作業を減らすことにより、 カラーコピーの利用を減らすことが可能です。 ちなみにコピーの際、会議資料の再利用や、裏面を使うという考え方もありますが、個人的にはお勧めしません。機密情報が万が一裏面に書かれているなどのセキュリティの問題や、再コピーをしてしまうなどの二重コストの発生が主な理由です。
FOCのサービス
支店間・部門間での事務用品の在庫数を洗い出し、購買を含めて一元管理するための体制を整えます。


定期的な見直し
コスト削減は、一回行えばいいというものではありません。業務フローを含め、定期的な見直しが必要です。 また、コスト削減を図るうえで、システム化は重要ですが、あれもこれもという形で、システムが増殖するケースがあります。その結果、システム間をつなぐデータ加工が新たに増えるなど、逆に非効率になる場合があります。 さらにクラウド環境の発達により、高性能で低料金のシステムも出てくるため、定期的なシステム関連費用の見直しが必要です。
FOCのサービス
アウトソースされた業務だけでなく、業務全体を見直し、業務フローを再構築、不必要なシステム・業務を洗い出すとともに、新たに必要となったシステムを追加し、無駄のないサービスを提供いたします。
どこからコスト削減に取り組むのが良いのか?
コスト削減の7つの方法を解説しましたが、いざ行おうと思うと、どこからコスト削減として手をつければ良いのか悩まれると思います。まずはコア業務に近いところから着手し、“大きな業務”から“小さな業務”とレイヤーを下に移動させるようにしてコストがかかっている点を洗い出していけばよいでしょう。
ただ、人間、ものごとに集中してしまうと本筋からそれてしまうこともあります。その結果、自社のバリューチェーンを崩すようなコスト削減を推進してしまい、売上を下げてしまっては逆効果です。
また、現場目線でいえば、マネージャー自身のコストに対する意識改革も必要で、さらにその下の社員の活動に落とし込むためにも評価基準の再設定も必要になるでしょう。その際、コスト削減の結果、経営責任のない社員のみが犠牲を強いるようなものとならないよう配慮をしましょう。
こんなお悩みありませんか?
- 部門ごとの発注コストが多く、管理本部がコントロールできない
- 会社の売上規模に対し、経費がかかりすぎる
- 物流コストを担当部門に任せきりで、把握できていない
- 電話料金や印刷費を見直したい
- 事務所の賃料をもっと安く抑えたい
- 既存取引先の変更ができず、相見積りも取れない
コスト削減サービスの一例
間接費削減
賃料
倉庫利用料
エレベーター
ESC保守
ビル管理
電気設備保守
消防設備保守
レンタルマット
衛生清掃
害虫駆除
廃棄物処理
機械警備
人的警備/駐車場管理
貸鉢/植栽
グリストラップ
定期修繕、内装工事
浄化槽/受水槽
引越し
事務用品、消耗品
機密文書処理
各種リース
システム保守費用
ソフトウェアライセンス
業務委託/人材派遣
配送、物流
クレジットカード手数料
オンライン決済
損害保険(火災保険、賠償保険、等)
銀行振込手数料
現金輸送
店舗消耗品(レジ袋等)
制服、リネン
包装資材(ダンボール等)
国内航空券費用
採用(媒体、紹介会社)
健康診断
検便
POS保守
ETC
自動販売機(手数料UP)
上記のほか、こんなサービスもございます


通信費削減サービス
料金プランの見直し等、通信費削減だけでなく、通信に関わる業務につきましても、見直し・削減のご提案をいたします。
主な対象業務
- ・利用状況管理 ・料金プラン見直し ・IP電話導入推進 ・解約もれ確認
- ・請求書一本化 ・社用携帯導入推進 ・モバイルナンバーポータビリティ対応
- ・インターネット回線見直し


光熱費削減サービス
電気・ガス・水道等の原価系費目に関して、それぞれ専門家(スペシャリスト)を配置し、幅広く対応します。
主な対象業務
- ・電気、ガス、水道料金見直し ・ガソリン、軽油料金見直し ・採光計画提案


印刷費削減サービス
印刷関連費用に対し、単なる相見積りではなく、原価推計で最適価格を算出し、価格交渉します、またコスト削減実現後もサプライヤーのマネジメントなど、付加サービスを実施しています。
主な対象業務
- ・コピー料金削減 ・チラシ、パンフ印刷費見直し ・その他印刷関連費削減
FOCのコスト削減サービスの特長
これ以上の節電対策は無理だと思っていましたが、ボリュームディスカウントという方法を提案いただき、電力単価を下げることでコスト削減が実現できました。(大手SIer)
固定電話・社用携帯の業者選定からプランの見直し、併せてインターネット回線のコストダウンまで実施していただきました。請求書が一本化されたことで、事務処理も格段に楽になりました。(商社)
長年つきあっている取引先があり、相見積りも取れない状況でしたが、FOCさんから原価に見合った最適価格を算出していただき、取引先に提示することで、適正価格へコストダウンすることができました。(流通関連)
この企業におすすめ
会社全体の
間接費を見直したい
企業
これ以上光熱費を
抑えられないと
思っている企業
既存取引先が
適正価格か
知りたい企業
FOCのコスト削減サービスを導入されたお客様の事例
コスト削減の意識を社内で浸透させるために
コスト削減は、純利益の拡大につながるという点で、売上の増加と同様の効果があり、とても重要な活動の一つです。
経営者だけが考えることではなく、例えばマネージャー自らが、人材を含む経営資源が無意味な形で浪費されていないことを社員に対し示す必要があります。 そのためにはコスト削減の成果に関する評価基準や人事査定の基準を新たに作ることも良いでしょう。また、より社内に浸透させる目的で、社外への積極的な発信を行い間接的な意識づけも必要です。
残業や時間外の労働には正当な対価が払われるべきですが、現状はどうでしょうか? 現在、インターネットショッピングの拡大により、物流業界で再配達に伴う過剰労働と賃金の不払いという問題が発生しています。 従業員や派遣社員に対し、対価を伴わない労働を強いているとすれば、ビジネスモデルに問題があると言えます。 こういったケースは、社員の理解を得る形で、ビジネスモデルの再構築が必要と考えられます。
やってはいけないこと、注意点
コスト削減の結果、経営責任のない社員のみが犠牲を強いるようなものとならないよう配慮が必要です。例えば、コスト削減を行う目標として「無駄を省く」ことは重要ですが、会社の経費としてこれまで認められていたものが、突然「無駄」と認定されることに違和感を抱く社員は多いはずです。