坂田 良平
Pavism代表。 一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト理事、JAPIC国土・未来プロジェクト幹事。 「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。 筋トレ、自転車、オリンピックから、人材活用、物流、ITまで、幅広いテーマで執筆活動を行っている。
MENU

経済産業省が、2018年9月7日に発表したDXレポートは、大きなインパクトを国内の経済界に与えた。
DXというキーワードがバズり、話題になる一方で、単なるデジタル化とDXを勘違いする企業や人も増えている。
帝国データバンクが2021年12月に行ったアンケートでは、8割強の企業が「DXおよびデジタル化などDX推進に向けた取り組みを実施している」と答えている。しかしその具体的な内容は「オンライン会議設備の導入」(61.9%)、「ペーパーレス化」(60.6%)などが中心だという。
これはデジタル化ではあるが、DXではない。
同レポートでは、「既存製品・サービスの高付加価値化」(11.7%)および「新規製品・サービスの創出」(10.8%)といった、DXへの本格的な取り組みを進めている企業は1割に留まると、警鐘を鳴らしている。
DX推進のため、経済産業省はDXセレクション2022を2022年3月24日に発表した。
「DXセレクションとは、DXに取り組む中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例を選定して紹介するものです。優良事例の選定・公表を通じて、地域内や業種内での横展開を図り、中堅・中小企業等におけるDXの推進並びに各地域での取組の活性化につなげていくことを目的とする」と、経済産業省は説明している。
率直に申し上げれば、目的意識の高さに対し、DXセレクションは内容が伴っていない。
DXセレクションを反面教師として、DXを事例から学ぶことの難しさを考えよう。
DXセレクションに選定された16企業の事例は、「DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)」(経済産業省)から確認可能である。
上記ウェブサイトからは、グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞を受賞した4企業のプレゼンテーション(Youtube)の他、取り組みをまとめたレポートを確認できる。
申し訳ないが、このレポート・Youtubeを見て、DXを学ぶことができるかと言えば…、難しいだろう。
(1) 選定企業のアウトプットをそのまま掲載しており、皆が読んで分かりやすい形に翻訳されていない。
(2) DXに対し、正しい理解をしており、広範な知識を持つ人でないと、レポート、プレゼンテーションから、学びを得ることができない。
(3) 単なるデジタル化の事例であって、DXではないと思しき事例も掲載されている。
(3)は論外である。
だが、もしかしたらちゃんとしたDX事例なのに、筆者が読み解けていないだけという可能性もある。それは(1)で指摘した、選定企業の取り組みを読者に分かりやすく伝える翻訳作業ができていないからだ。
筆者はFOCに限らず、さまざまな企業の事例を取材し、執筆してきた。
事例というのは自社の取り組みである。自社のことだから、その内容に一番詳しいのは、自社の、しかも担当した社員であるはずだ。
筆者のような外部ライターは、1~3時間程度のインタビューを行った程度で、担当社員の知識量を超えることなどできるはずもない。
にもかかわらず、事例記事作成を、筆者のような外部人材にアウトソーシングする理由とはなにか?
(1)自社社員では、取り組み内容について第三者に伝わるように言語化できないから。
(2)自社社員では、伝えるべきポイントを取捨選択して、適切に情報を整理整頓できないから。
(3)対象となる事例について、第三者(=ライター)の目から客観的に評価して欲しいから。
DXセレクションのレポートやYoutubeに登場するのは、社長や担当者など、取り組み推進の主人公となった方々である。
残念ながら、事例の登場人物たちの言葉にはバイアスがかかるし、ご自身が伝えたいポイントと、我々読み手が知りたいポイントは必ずしも一致しない。
だから世の多くの企業は、事例記事を作成するときに、プロのライターを招き、翻訳作業を依頼するのだ。
ここで言う翻訳作業とは、事例当事者たちの想いはそのままに、その内容を第三者に分かりやすく取捨選択、適切な言葉を再配置して伝わる文章にすることである。
DXセレクションにおけるレポートのように、当事者の言葉をそのまま掲載する行為は、読み手に翻訳作業を丸投げする行為である。
DXの旗振り役である経済産業省がやるべきではなかった。
あくまで筆者の肌感覚なのだが、以前の事例取材というのは、上記(1)および(2)の技術が高いライターが重宝されていたように思う。
逆に言えば、(3)、すなわちライターの私見・考察などは不要だと考えられていたし、実際私も考察を書いて、顧客や編集部から原稿を突き返された経験がある。
だが、5~6年位前から、(3)が求められるようになってきたと感じている。
「良い点だけでなく悪い点も含めて考察して欲しい」
──ここ数年の依頼を振り返ると、100%このように依頼される。
この理由を考察し始めると長くなってしまうが、ざっくりと申し上げれば、ライターの考察は、記事のテイストに雑味を付与するスパイスとして、読者に対し、記事内容の消化を促す効果をもたらす。
それでなくともDXは難しい。
だからこそ、DXセレクションの場合は、選定に関わった方々の声の所感(このケースだとライターの考察に相当する)を掲載すべきだった。
「なるほど、こういうことなのか!」といった肯定的な反応、もしくは「我々は真似できないよ…?」といった否定的な反応など、「あなた(選定者)は○○と言っているけど、私は△△だと思う」という、読者自身に我が身我が事として考察を促す効果により、読者のDXに対する理解が進んだことだろう。
間違いなく、このDXセレクション2022の選定には、多くの人たちの手間と努力が投じられているはずである。
今からでも遅くない。ぜひ学びを得ることができる内容へと、DXセレクションを昇華させて欲しい。
先日、小野塚征志氏(ローランド・ベルガー)が、「DXビジネスモデル 80事例に学ぶ利益を生み出す攻めの戦略 (できるビジネス) 」(インプレス)を上梓された。
小野塚氏は、国内を代表するDXの論客の一人であり、私も取材させてもらったことがある。
同書では、DXを「デジタル化技術を活用したビジネスモデルの革新」と定義した上で、戦略的方向性として以下の4つを挙げている。
(1) 場を創造するビジネス
(2) 非効率を解消するビジネス
(3) 需給を拡大するビジネス
(4) 収益機会を拡張するビジネス
その上で、この4つに分類した80のDX事例を挙げている。
「本書は、DXの理論や方法だけでなく、80の先進事例を解説することで、ビジネスモデルの進化のあり方を具体的に学べる」
──これは同書の「はじめに」に記された言葉であるが、この言葉に違わぬ良書である。
環境意識の高まりによって、「グリーンウォッシュ」もしくは「SDGsウォッシュ」なる言葉も話題に挙がるようになってきた。
「ウォッシュ」とは、「whitewash:ごまかす、うわべを取り繕う」を意味する。グリーンウォッシュ、SDGsウォッシュと言えば、「環境貢献活動(ないしSDGs)に取り組んでいるふりをする」行為や企業を蔑むスラングである。
現在、DXが話題になっていることもあり、単なるデジタル化をDXと称し喧伝したり、もしくは「うちのソリューションを導入すれば、DX対策はバッチリです!」などというシステムベンダーなども散見される。
こういった不埒な輩は、「DXウォッシュだ!」と糾弾されてしまえばいいのに…
──心根の卑しい筆者は、このように感じてしまうのだが、残念ながらDXウォッシュなる言葉を使う人は、まだまだいないようだ。
DXに関する論客のひとりである、マイケル・ウェイドは、著書『DX実行戦略 デジタルで稼ぐ組織を作る』において、DXを「デジタル・ビジネストランスフォーメーション」の略語であるとしている。
そして、より大切なのは、「デジタル」ではなく、「ビジネストランスフォーメーション」であると訴えている。
DXではなく、DBX=「デジタル・ビジネストランスフォーメーション」としていれば、単なるデジタル化をDXと勘違いするようなアピールは減ったのではないかと思う。
FOCブログ「Knock」において、筆者はDXに取り組む必要性をこれまでも述べてきた。
とは言え、DXに取り組むには大きな努力と困難が伴う。だからこそ、イノベーターらの先進的な取り組み事例が、DXに悩む多くの企業の道標となるはずなのだ。
良質なDX事例レポートが一つでも多く、世に出回ることを期待したい。
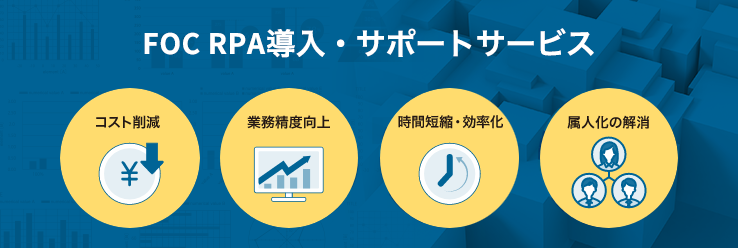
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
坂田 良平
Pavism代表。 一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト理事、JAPIC国土・未来プロジェクト幹事。 「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。 筋トレ、自転車、オリンピックから、人材活用、物流、ITまで、幅広いテーマで執筆活動を行っている。

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE