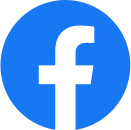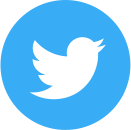~これまでのあらすじ~
TOARU株式会社で働く、人事部主任の館林、財務部課長の内藤、経理部部長の関口といった三人らが主人公。彼ら・彼女は、テレワーク期間中、社内のチャットシステム上での交流がきっかけとなり、意気投合し合う仲になった。三人が集う場所は、遊休資産が眠る、“視聴覚室”。そこで繰り広げられる
トークには、本音も入り混じり、それぞれの使命への落とし込みに繋がることもあるようだ。
財務部 内藤アヤカが抱えている、高齢の男性部下、ミズノ氏についての悩みは、いわゆるステレオタイプのものではなかった。それを踏まえ、人事部 館林ハルヒコは、“定年70歳制度”導入を機に全社の人事制度改革にまで、発展させようとしているのか・・・?部内会議の場で、企画のプレゼンの真っ最中だ。
人事部係長 館林ハルヒコのプレゼン進行模様。
「”定年70歳制度”が導入されたら、若手社員のモチベーションにも更に気を配る必要があります。
勿論、国の制度を受け入れることは義務ですが、これを機に人事体制を見直してはどうかと思うのですよ。まずは、機能性強化。上司と部下との関係性を“良くする”よりも、機能的にしていくのです」。
“定年70歳制度”導入を機会に、上司と部下との関係性について、機能性強化を図ろうとする館林は、人事部内のミーティングにて、自身が企画したラフ案をプレゼンしていた。
最初に上司と部下が質問シート(Aパターン:以下を参照)を使って面談し、次の段階で、人事部がその上司と別の質問シート(Bパターン:以下を参照)を用いて面談するといった、フローだ。
人事部 館林係長が試作した二種類の質問シート
Aパターン ~上司から部下へ・・・質問シート~
- Q1,あなたの貢献度について、どのように考えていますか?
- Q2,自社で今後、どのような職務・活動をしたいですか?
- Q3,上記“2”を実践することで、どのような効果が表れるでしょう?自由に余白を 使って描いてみてください。
- Q4,まずは、明日、何から始めますか?
Bパターン ~人事部から質問者へ・・・質問シート~
- ◆あなたの部下〇〇さんが描いた“質問シート”から、感じたことを記入してみてください。
- Q1,あなたは現在の部署で、部下に対し、今後どのような機会を提供しますか?
- Q2,“Q1”の実践後、部下はどのように貢献すると思いますか?
- Q3,あなたの部下〇〇さんの潜在能力や今後の期待など、自由に余白を使って描いてみてください。
人事部スタッフは、二パターンの質問シートを凝視している。シートに盛り込まれている質問事項を読みながら頷く者や頭を傾げる者。無言の笑顔で、館林に向かって賛同している姿勢を示す者。
人事部十人十色の感想なのか?その内の一人の部員が手を挙げて、館林に質問する。
「何となく、理解はできましたが、“定年70歳制度”を機会になぜ、こうした質問をしてもらって、部上司と部下の機能性を高める必要性があるのか?もう少し、教えて頂けますか?」
他数名の人事部員が“うんうん”と同じ二拍のリズムで首部を縦に振った。おそらく、質問者である部員に賛同しているのだろう。こうした反応に対し、プレゼン者の館林も、明快な回答する。
「同じ部署内で、互いが同じ仕事を続けていると、やがて慣れてしまって、『あの部下は、こうだから・・・』『この部下は、〇が不得手で、□が得意・・・』といった評価が定着してしまうこともあるでしょう。それが、本当に正当なのか?正しく疑う必要があると思ったのですよ。ひょっとしたら、バイアスによって、部下の潜在能力を潰してしまっているのではないかと。そこで“定年70歳制度”の導入を機会に、ニュートラルに戻して、改めて部下と上司が向き合うことが大事かと思いましてね・・・」
館林の説明が終わるか終わらない頃、人事部員の携帯電話が音を立てた。慌てる部員。すかさず、立ち上がって頭を下げる。
「すみません、係長が大事な話をしているのに、雑音が混じってしまいました」。
部員が詫びる姿に館林がフォローする。
「携帯の音色、私も同じ着信音ですよ。雑音ではないでしょう。折り返し、相手の方に連絡しなくて良いのですか?」
館林の気遣いに対して、笑顔を向ける部員。携帯電話の音色は何となく、心地よいメロディーラインが奏でられたような気がした。
次に別の人事部員が立ち上がった。時間が気になるのか、スマートフォン上の時計を見ているようだが、表情はどことなく清々しい。何か伝えたいことがあるようだ。
「係長、単に国の制度だから、といった理由で、定年70歳制度を導入したところで、軌道修正する箇所を野放しにしていれば、“年齢の高い人=〇〇である。”といったバイアスに気づかずに進めるでしょうからね。偏見を持たないAIを完全導入して、人事考課することも良いでしょうが、まずは、係長の案を、この人事部案で導入しませんか?ここでの上司・部下の機能性が効いていなければ、他部署でも、面目が立たないでしょう」。
ようやく、座は終盤を迎えた。館林のラフ案は、人事部内で試験的に実施される運びとなるようだ。
財務課長内藤アヤカとミズノ氏が向かった場所は、Z地方にある備品倉庫。
内藤は、男性部下にあたる、60歳越えのミズノ氏と共に、朝一番の新幹線に乗って、Z地方に到着していた。そこには、あの“視聴覚室”と同様に10年程前に閉鎖された機械部品工場の存在がある。
何となく古びた鉄材や油の残り臭が感じられる空間。現在は、デリケートな保管が不要の備品倉庫としての、役目を担っている場所だ。
「内藤課長、今日は貴重な時間を頂き、ありがとうございます。資産計上されている、モノの実態調査に私が御伴できるとは、光栄です。わくわくしますね。あ、すみません。財務部の大事な仕事ですよね、年甲斐もなく・・・」。
ミズノは、恐縮そうな笑みを内藤に向ける。内藤は、iPadを左腕で抱えながら、備品の実態を調べ始めていたところだった。背中をすっと伸ばして、ミズノ氏の方に目をむけた。
「ミズノさん、自然体でいきましょうよ。そんな、畏まらなくても、いいですよ。そうですね~わくわくしますね・・・」
と言いながらも、自身もミズノ氏に対しての気構えを感じていた。再び、努めたセリフなのか、『わくわくしますね~』と、ミズノ氏に繰り返し伝え、協調を図ろうとした。
そんな内藤の思案に気づいたのか、ミズノ氏は、別の方向にある備品のところに移動する。足取りは、軽やかだ。器用な手つきで、備品と手元の資料との突合を進めようとした。そこには、古びた段ボールで包まり、品名とナンバリングが確認できるも、中身をきちんと見なければ、怪しいような感覚が漂っていた。段ボールのひもを解こうとするミズノ氏。そこへ、内藤が声を掛ける。
「ミズノさん、どう思いますか?財務のデータとの突合をするのに、支障はなさそうですが、“実態調査”で終わって良いのですかね~?」
中途入社で、課長職にまで昇りつめた内藤のことだ。おそらく、単なる年上部下に対する、謙虚な相談ではないだろう。つまり、言わずと知れた、“テスト”の位置だ。ミズノから、どんな回答が返ってくるか、試しているのだろう。
すると、ミズノは一旦、作業の手を止めて、出口に向かった。内藤もミズノの後に続いた。なんとなく、そんな行動が相応しいと、内藤なりに感じたようだ。
遠い距離から、カモメの鳴き声が聞こえる。どこからか、潮の薫りもする。海の方向が解かるような気がした。こうした、リアルな意味での“自然体”と、いつ出番がやってくるか分からない、備品たちが眠る倉庫は、対称的であると感じる内藤だった。
ミズノは、空を見上げる。そして、内藤に対し、質問の答えを返すのだった。
「内藤課長、我われの背後にある倉庫には、使い物にならなそうな、解体された機器の一部もありましたが。遠い昔は輝いていたこともあったのでしょう。息を吹き返すためには、進化が必要です。
そこで、ここの土地との融合性が生まれれば、どことなく粋な気がしませんか?ここ周辺に住む人や生活面、価値観に触れないと、何が得策なのか、解らないですが、実態調査は倉庫の内外にも、目を向けないと・・・なのでしょうね」。
内藤も空を見上げながら、ミズノに言葉を返すのだった。
「ミズノさん、なるほど。実態調査の真意は、そこなのですね。私も勉強になりました。ただ、“ここ周辺に住む人”と言っても、一括りにすることなく、丁寧な取材が必要ですね」。
倉庫と周辺の自然について、対称的だと感じる内藤と、融合を視野に入れるミズノ氏。それぞれの考え方は異なるも、真の意味での“実態調査”を続けて、TOARU株式会社内に潜む、資産・資源の有効活用策を検討するのだろうか?
カモメの鳴き声が再び聞こえてきた。先程より、ボリュームが大きい。どうやら、二人がいる周辺に近づいてきたようだ。
人的資源の活性化がカギ!・・・いつもの“秘密基地”視聴覚室で繰り広げられる三人の雑談。
「生え抜きの経理部員から聞きましたが、Z地方にあった機械部品工場は、リーマンショックも影響して閉鎖に追い込まれたのですよ。工場だけではなく、関係する地方支社・支店も閉鎖されて、リストラの嵐も吹いて・・・」
経理部長の関口ミツルは、財務課長の内藤と年配社員ミズノ氏が訪れた、Z地方にある倉庫についての解説をしていた。
ここは、例の秘密基地にあたる“視聴覚室”。昼休みの残り時間に三名らの雑談を重ねる場である。次は、Z地方の現場の倉庫に出向いて“実態調査”に当たった内藤が口を開く番だった。
「ミズノさんのような、独特な魅力のある人的資源をもっと表出させて、ここTOARUの企業価値を高めることを、主流にしていかないと・・・あのZ地方と昔、成長を続けていた工場だった倉庫との融合性。一口に地方貢献とは、言い表せないほどの、スケールの内容が出来上がるのかしら?」
人事係長の館林は、何かを思案しているのか?先程から、ずっと黙っているが、そろそろ昼休みも終盤。清々しい表情で言葉を発する。
「上司と部下の機能性アップって、つまり、そういうことだよね。上司が部下の能力を引き出す機会提供をして、上司側も部下から学ぶ機会を得る。それがTOARUの業績アップや社会貢献に繋がっていけるようにしないとだね」。
三人は、視聴覚室の出口に向かう。午後からの就業に向かう時刻となった。『では・・・!』とそれぞれの部署へと退散するも、視聴覚室内の遊休資産たちは、同じ場所で今後の事態をじっくりとみつめているようだった。
次回へ続く
“定年70度導入”をきっかけにして、人事部館林が企画した上司と部下の機能性アップの試みと、財務部内藤の、年上部下ミズノ氏との向き合い方がリンクした様子です。
Z地方と倉庫の融合性は、新企画としてどの方向性に進むのか?期待してみていきましょう。
次回は、経理部関口を主人公に、職務の本質を描いていきます。どうぞ、お楽しみに!
田村夕美子