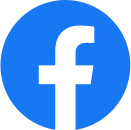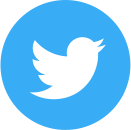給与計算実務能力検定とは、内閣府認可一般財団法人職業技能振興会が認定する民間資格で、給与計算業務に関する知識と実務能力を測るための検定試験です。
2014年から実施されている検定で、毎月の給与計算だけではなく、社会保険の手続きや年末調整などといった幅広い業務を理解・遂行できるようになります。
給与計算実務能力検定とは?受験資格、試験内容、学習ポイント、類似資格を紹介


給与計算実務能力検定は、給与計算業務に関する知識と実務能力を測るための検定試験です。概要、試験内容と学習ポイント、類似資格について解説します。検定を受験して給与計算業務に活かしたい方におすすめです。
給与計算とは、社員の給料を計算する業務のことをいいます。どんな企業でも毎月の給与計算は行われており、社員の生活にも直結する、重要な仕事のひとつです。
給与計算業務を正しく行うには、社会保険の仕組みや労働法令などの幅広い知識が必要不可欠とされているため、資格取得を通して必要な知識が身につく「給与計算実務能力検定」を受験する人もいます。
本記事では、給与計算業務を行う方にとって役立つ資格、給与計算実務能力検定について解説します。また、サンプル問題を参考に、学んでおくべきポイントもご紹介します。
この記事の目次
給与計算実務能力検定とは

なお、給与計算に関する資格は給与計算実務能力検定のみです。
給与計算はどの企業や団体においても欠かせないため、給与計算業務に携わりたい方などは資格を取得しておくと就職・転職にも役立ちます。
◆給与計算実務能力検定の級の区分
給与計算実務能力検定では、難易度別に試験区分が2級と1級に分かれています。
【給与計算実務能力検定2級】
2級は、実務上の基礎となる労務コンプライアンス(労働関係法令を遵守したうえで労務管理を行うこと)について正しく理解し、基本的な給与計算を行い、給与明細を作成できるレベルです。
2級をクリアしている給与計算担当者は、一般職員として、通常の給与計算業務をこなせる者とされています。
【給与計算実務能力検定1級】
1級は、労働法令や税務についても正しく理解し、複雑な制度やイレギュラーな給与体系にも対応でき、年末調整を含めた年間を通じて給与計算に関するすべての業務に精通しているレベルです。
社会保険や税務などに付随する手続きを行うことができ、給与計算業務のリーダーとして管理できる者とされています。
つまり、2級は「基本的な給与計算を行い明細が作成できるレベル」であり、1級は「年末調整や社会保険など複雑な計算が必要なことまで理解し、給与計算に関する全般の業務ができるレベル」となります。
◆受験資格、受験料、平均合格率は?
給与計算実務能力検定における受験資格、受験料、平均合格率などの詳細をまとめました。
▼受験資格
特にありません。どなたでも受験可能です。
▼試験日
【2級】年2回(3月、11月)
【1級】年1回(11月)
▼受験料
【2級】8,000円
【1級】10,000円
※資格取得後は2年ごとに更新料5,000円が必要
▼平均合格率
【2級】75%
【1級】47%
※2017年3月〜2019年11月までに実施された検定の合格率から算出
このように、学歴や実務経験による受験制限がなく、合格率も比較的高いため、取得しやすい資格であると言えます。
給与計算実務能力検定の試験内容

給与計算実務能力検定の試験内容・出題科目は以下のとおりです。それぞれの試験概要や出題科目を把握し、勉強に役立ててください。
【2級】試験概要・出題科目
2級は記述式の計算問題はありません。必要な知識について、マークシート方式で適切な選択肢を選んで回答していきます。
・試験時間:120分
・出題形式:知識問題35問、計算問題5問(それぞれ四肢択一、マークシート方式)
・点数配分:知識問題1問2点(計70点)、計算問題1問6点(計30点)
・合格基準:全体で7割以上の得点
計算問題に必要な情報は、試験時に「資料集」として配布されます。資料集には、健康保険・厚生年金保険の保険料額表、雇用保険料率表、給与所得の源泉徴収税額表などが記載されています。
2級出題科目
① 給与計算の基本的な仕組みの理解
② 給与計算に関連する、労働基準法や労働契約法などの労務コンプライアンスに関する知識
③ 給与計算に付随する各種手続きの基本
④ 社会保険関係の基本的な給付
⑤ 給与計算に最低限必要な割増賃金などの計算方法
⑥ 実例に基づく基本的な給与計算の計算問題 など
【1級】試験概要・出題科目
1級は記述式の計算問題があります。知識問題は選択肢から選びマークシートで回答していきます。
・試験時間:120分
・出題形式:知識問題30問(四肢択一、マークシート方式)、計算問題10問(記述式)
・点数配分:知識問題1問2点(計60点)、計算問題1問4点(計40点)
・合格基準:全体で7割以上の得点、かつ計算問題が6割以上の正解
2級と同様、計算問題に必要な情報は、試験時に「資料集」として配布されます。2級とは違い出題範囲が広がるため、資料集には年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表、生命保険料・地震保険料の控除額の計算式なども記載されています。
1級出題科目
① 給与計算に関連する、労働基準法や労働契約法などの労務コンプライアンスに関する知識
② 賃金、労働時間帯に関する法令の基本と応用
③ 給与計算に付随する各種手続きの基本と応用
④ 社会保険関係の重要な手続き
⑤ 実例に基づく応用的な給与計算の計算問題
⑥ 年末調整についての知識
⑦ 実例に基づく年末調整の計算問題 など
出題範囲が2級よりも広範囲にわたりますが、どれも実務において重要なポイントです。給与計算実務能力検定を受ける受けないに関わらず、勉強しておくことが求められます。
給与計算実務能力検定のサンプル問題から見る学習ポイント

給与計算実務能力検定の出題サンプルから、給与計算担当者が理解しておきたいポイントを簡単に解説します。
▼給与計算実務能力検定 サンプル問題
https://edu.jusnet.co.jp/test_sample/
詳しくは、試験を実施している一般財団法人職業技能振興会が監修する認定テキスト「給与計算実務能力検定公式テキスト」を参考にして勉強することをおすすめします。
◆賃金支払いの5原則
給与計算の大前提である、労働基準法第24条に定められた「賃金支払いの5原則」について触れていきます。
労働基準法第24条において「①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。
これらの5つの原則をまとめて「賃金支払いの5原則」と呼ばれています。
【通貨払いの原則】
給与は小切手や現物ではなく、通貨(現金)で支払わなければなりません。ただし、労働協約に定めがある場合は、通貨以外のもので給与を支給することが可能です。
【直接払いの原則】
給与は本人に直接支払うのが原則です。たとえ労働者が未成年であっても、労働者の代理人に支払うことは原則として許されません。
【全額払いの原則】
賃金は、所定支払日に支払いが確定している全額を支払わなければなりません。ただし、書面による協定があれば、社宅賃料や社内預金などの天引きが認められています。
【毎月払いの原則】
給与は、少なくとも毎月1回以上支払わなければなりません。支給日を同月中2回に分けることも可能です。なお、結婚手当などの臨時的な支払いや賞与は毎月払いの対象外となります。
【一定期日払いの原則】
賃金は「毎月25日」といったように、期日を特定して支払う必要があります。「毎月第3土曜日」など、変動する期日を支払日とすることは認められません。給与支払日が休日にあたる場合、支払日を前後にずらして行うことは可能です。
◆労働時間と割増賃金・割増率
労働基準法第32条では、1日8時間、週40時間以内を「法定労働時間」として定めています。法定労働時間を超えて働く「時間外労働」を行った場合、または「深夜労働」や「休日労働」を行った場合、使用者は労働者に対して「割増賃金」を支払う義務が発生します。
割増賃金が発生する条件と割増率は以下の通りです。
【時間外手当】
・1日8時間、週40時間を超えた場合(25%割増)
・時間外労働が月45時間、年360時間を超えた場合(25%割増)
・時間外労働が月60時間を超えた場合(50%割増)(※1)
(※1)中小企業は2023年4月1日より適用されます
【休日手当】
・法定休日に出勤した場合(35%割増)
【深夜手当】
・22時から5時までの時間帯に働いた場合(25%割増)
◆労働時間に対する休憩時間数
休憩時間は労働基準法第34条において、「労働時間が6時間を超える場合にはその途中に45分以上、労働時間が8時間を超える場合にはその途中に60分以上の休憩を与えなければならない」と定められています。
・6時間を超える労働、最低休憩時間45分
・8時間を超える労働、最低休憩時間60分
上記のように、休憩時間が付与される条件として、労働時間が6時間と8時間を「超えているか」がポイントとなります。
例えば、6時間ちょうどの労働時間であれば休憩の義務は発生しませんが、6時間を1分でも超える場合は最低でも45分の休憩を挟む必要があります。
◆年次有給休暇など休暇や休業
正社員やパート・アルバイトにかかわらず、勤続6ヶ月以上かつ出勤率が8割以上である場合、年次有給休暇が付与されます。
年次有給休暇を取得した際の支給額は平均賃金で計算されることもありますが、多くの企業では通常の勤務時と同額とするケースが多いです。
また、慶弔による休暇や、出産・育児、介護などの理由によって休業せざるを得ない場合、期間中の賃金を無給、有給のいずれにするかをあらかじめ就業規則に記載しておく必要があります。
◆労働協約と就業規則と労働契約
労働協約、就業規則、労働契約といった似たような言葉について理解する必要があります。それぞれの優位性も異なります。
労働協約とは、使用者と労働組合が協議し、労働条件等に関する事項について合意した結果について書面にまとめたものです。
就業規則は、労働者が遵守すべき規律や労働時間、賃金等の労働条件について使用者が定めたものです。
労働契約は、使用者と労働者個人が結んだ労働条件を約したもののことをいいます。
守るべき優位性は、「労働協約→就業規則→労働契約」の順です。
就業規則および労働契約よりも労働協約が優先され、労働契約よりも就業規則が優先されることになります。
具体的には、労働協約で「時間外労働の割増賃金率は2割5分以上」と取り決めた場合、就業規則において「時間外労働の割増賃金率は2割」とすることはできません。
そして就業規則において「時間外労働の割増賃金率は2割7分」と定めた場合は、労働契約で「時間外労働の割増賃金率は2割5分」とすると就業規則に反しているので、2割7分以上にしなければなりません。
◆社会保険の給付
社会保険とは、具体的に「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5つの保険の総称です。
社会保険の対象は正社員だけではなく、パートやアルバイトも、それぞれ要件を満たしていれば含まれます。社員がいない一人経営だとしても、社長自身が社会保険に加入しなければなりません。
社会保険の加入対象は、以下の要件を満たしている社員です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月給8万8,000円以上
・1年以上働く見込み
・学生ではない
・被保険者となる人が501人以上の事業所に勤務
条件に該当する社員がいる場合、雇用形態に関わらず社会保険に加入させなくてはなりません。
健康保険、厚生年金保険、介護保険の計算方法は、それぞれの保険料率に標準報酬月額を掛けて算出します。
その他、細かなルールが定められているので、社会保険についての勉強は欠かせません。
関連資格「社会保険労務士」「日商簿記検定」とは

給与計算業務に携わるのであれば知っておきたい関連資格、「社会保険労務士」「日商簿記検定」を解説します。保持しておけば、給与計算の実務においても十分に役立ちます。
◆社会保険労務士とは
社会保険労務士は、1968年より実施されている厚生労働省所轄の国家資格です。
労働者の入退社におけるさまざまな手続きや、労務管理のコンサルタントなど、人事や労務に関する全ての業務を引き受け、総括的に企業づくりの支援を行う専門家として活躍します。
社会保険労務士になるためには、毎年8月下旬に実施される社会保険労務士試験に合格しなければなりません。毎年約5万人が受験を申し込む人気の資格ですが、試験範囲の科目数が多く、合格率は平均6%程度であることから難易度の高い試験であるといえます。
社会保険労務士試験には、労働基準法および労働安全衛生法、雇用保険法、社会保険に関する一般常識などの出題が含まれます。そのため給与計算業務と密接な関係にあり、受験者は社会保険労務士試験の知識を、給与計算実務能力検定へ繋げるなど、有効活用することができます。
◆日商簿記検定とは
簿記とは、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と財務状態を明らかにする技能で、この習得度を測るのが日商簿記検定です。
日商簿記検定はレベルごとに初級、3級、2級、1級とあり、実務で通用するレベルは3級以上であるといわれています。
簿記を理解することで、経理事務に必須の会計知識が得られるだけではなく、基礎的な経営管理や分析力が身につき、コストを意識した仕事ができるようになります。
また、多くの企業では、スキルアップや自己啓発のために日商簿記の取得を奨励しているほか、大学や短大によっては簿記検定が単位として認められる場合もあり、年間で50万人以上の方々が受験する検定として社会的に高い信頼と評価を得ています。
給与計算実務能力検定などの資格とあわせて、業務のステップアップに繋げると良いでしょう。
まとめ|資格取得を通して必要な知識を身に着けよう
今回は給与計算実務能力検定の概要や試験内容についてご紹介しながら、給与計算業務に関わる担当者であれば知っておきたい知識についてもご紹介しました。
給与計算業務は、資格がなくても行うことができます。しかし、給与計算実務能力検定には「労働基準法の知識」や「労務」に関する問題も含まれているため、取得しておくと経理や総務全般の業務に役立てることができます。
給与計算業務はミスが許されない、重要な業務内容です。必要な知識を日々習得していくことは重要です。
給与計算担当者であれば、給与計算実務能力検定を取得しておいて損はないので、未来の自分への投資として受検を検討してみてください。
給与計算に関わる様々な業務をカスタマイズしご提供

年末調整や住民税の計算など給与計算業務には年に数回繁忙期がありますが、繁忙期だけアウトソーシングしても給与計算業務は効率化できません。FOCはアウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性で、総合的に給与計算業務の効率化を支援します。
サービスの特徴
- サービス範囲の広さ
- システムと業務の一括提供
- 現状を踏まえた設計と運用
- 運用環境のセキュリティ性
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

関連記事を見る
-
【事例】経理アウトソーシングの失敗例と回避策5選!後悔しないサービス選びを解説経理アウトソーシングを検討しているが、失敗したらどうしようと不安を感じていませんか?本記事では、実際に起こりがちな5つの失敗事例とその具体的な回避策...経理アウトソーシング失敗経理2025.12.03
-
営業事務アウトソーシングする4つのメリットと料金相場・導入するポイントを解説営業事務アウトソーシングは、導入することでコア業務への集中や業務効率の向上、コスト削減などのメリットが得られる一方で、情報漏洩のリスクや業務状況の...営業事務・事務代行アウトソーシング営業事務2025.01.20
-
【事例】BPaaSとは?BPOとの違いや市場規模3つの導入メリットを解説本記事では、BPaaS(ビーパース・Business Process as a Service)について詳しく解説します。BPaaSと近しい言葉にBPO(ビーピーオー)やSaaS(サース)があ...アウトソーシングBPaaSBPOアウトソーシング2024.12.05