Knock編集部
FOC当コンテンツ編集者。 FOCのwebマーケティングを担当兼当コンテンツ編集を担当。 「knock」を読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。
MENU
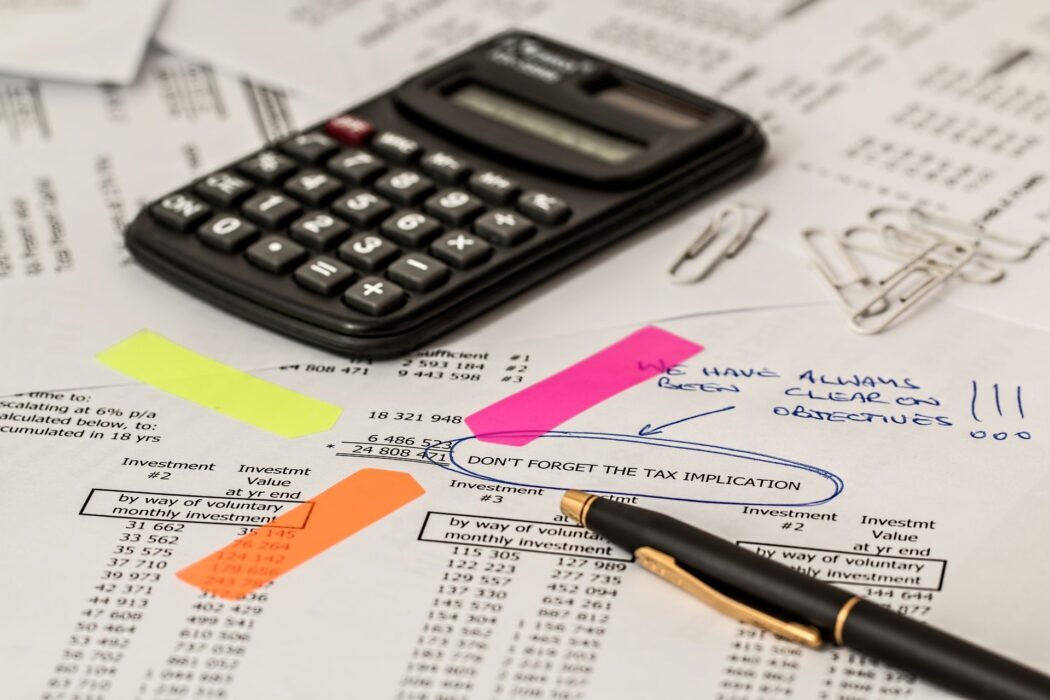
企業の中で給与計算は、従業員に支払う賃金を決定する欠かせない業務です。一見当たり前に行われていますが、担当者からすると複雑で難しい点が多くあり、ミスが発生してしまうことも少なくありません。
本記事では事前準備や計算手順、注意点など給与計算の基本的な内容について、初心者にもわかりやすく解説していきます。
この記事の目次
まずは給与計算について、その概要と基本的な仕組みを説明します。
給与計算とは、従業員に支払う毎月の給与を決定する業務です。
法律でも定められているとおり、会社は従業員に対して定められた期日までに給与を支払う義務があるため、給与計算はミス無く正確に行う必要のある重要な業務となります。
給与計算は基本的に以下の構造となっています。
給与額(手取り) = 総支給額 − 控除額
それぞれの金額の内容は以下のとおりです。
総支給額(額面):基本給に各種手当や月の残業代などを全て足した、従業員に支給するお金の総額。
控除額:社会保険料や税金など、従業員が支払う義務のある金額
給与額(手取り):総支給額から控除額を差し引いた、実際に従業員の手元に支給される金額。
例として、ある従業員の月の総支給額が50万円、控除額が10万円だった場合、その従業員が手取りとして実際に受け取る給与額は40万円となります。
では給与計算を行うにあたって、一体何が必要となるのでしょうか。ここでは業務を行うための事前準備について解説していきます。
給与計算を行うためには、そもそも各支給金額を決定する必要があり、その決定のもととなるのが就業規則や給与規程となります。就業規則は一般的に従業員の労働条件や働く上でのルール全般が記載されており、その中で賃金の決定についても給与規程として作成しておく必要があります。
この書類に基づき、基本給や各種手当、時間外労働の際の割増賃金などが決定されます。
なお、従業員が10人以上いる会社の場合は就業規則の作成および届け出が必須となっています。ここでいう従業員には、パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用労働者も含まれますので、注意しておきましょう。
給与計算での各種支給額を決定するにあたり、従業員情報も最新のものを準備するようにしましょう。
一般的に基本給や各種手当などは、従業員の勤続年数、職種・役職、勤務地、扶養状況などによって変動するためです。
各従業員がその月、どの日程でどれだけの時間働いたかという情報も支給額の決定に必要です。
特に時間外労働や休日・深夜労働については法律で割増賃金での給与計算が定められており、重要な項目となります。
正確に各従業員への支給額を決定するために、上述の就業規則・給与規程や従業員情報とあわせて、勤怠情報も準備しておきましょう。
一定の条件に当てはまる従業員は社会保険への加入が義務付けられており、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つが該当します。
給与計算においても後で触れる社会保険料の算出のために必要ですので、これらへの加入がしっかりと行われているか確認しましょう。
ここからは給与計算を行う流れについて、計算手順もあわせて説明していきます。
給与計算を行ってまだ経験が少ない、もしくはこれから行う予定の場合は、内容をしっかりと確認しつつ進めていきましょう。
まずは支給する給与の総額である、総支給額(額面)についてです。
総支給額の計算方法は以下のとおりで
総支給額(額面)=基本給+各種手当+割増賃金
各金額の内容は以下のとおりです。
基本給:一定期間の労働に対して支給される、ベースとなる給与金額
各種手当:役職手当、住宅手当、勤務地手当など、従業員毎に支給される手当の金額
割増賃金:残業代や休日・深夜手当など、月の勤務状況によって変動する金額
基本給や各種手当については、基本的に就業規則に基づいて固定で算出されるため、計算する必要はありません。従業員の役職や勤続年数などの情報をもとに、確認していきましょう。
一方で割増賃金については、従業員の月の勤務状況によって変動する金額のため、計算を行う必要があります。
割増賃金の計算式は以下のとおりです。
割増賃金=該当の労働時間数✕1時間あたりの賃金✕割増率
割増率の最低基準は、現状以下のとおりに定められています。
時間外労働:25%以上、月60時間を超えるものは50%以上(中小企業は2023年3月末まで猶予あり)
休日労働:35%以上
深夜労働:25%以上
会社によっては上記の最低基準を上回る設定がされていることもあるため、就業規則などで事前に確認しておくことをおすすめします。
続いて、従業員が支払うべき控除額の計算を行います。まず基本となる控除額として法定控除があり、こちらは社会保険料と税金の2つに分けられます。それぞれについて解説していきます。
【社会保険料の計算】
社会保険料として控除の対象となるのは、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料の3つが基本で、満40歳以上の従業員については介護保険料も対象となります。
各保険料の計算は、以下のとおりです。
・雇用保険料=総支給額×雇用保険料率
雇用保険料率は、厚生労働省より公表されている雇用保険率表を参考にしましょう。
なおこちらは年度によって変更されている可能性があるので、常に最新のものを使用するよう注意が必要です。
参考:雇用保険料率
他3つの社会保険料の計算式は以下のとおりです。
・健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率÷2
・介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率÷2
・厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2
標準報酬月額とは、社会保険料の算出の基準となる金額です。その年の4〜6月の3ヵ月間の給料の月平均である報酬月額をもとに算出します。
参考:標準報酬月額について
健康保険料率については、都道府県毎に異なります。以下の保険料額表を参照し、保険料率を確認しましょう。
参考:健康保険料額表(令和4年版)
介護保険料率は令和4年9月現在、1.64%と定められています。
参考:介護保険料率について
なお介護保険料は健康保険と一体的に徴収される決まりとなっており、該当する場合(満40才以上)は、健康保険料率に介護保険料率(1.64%)が上乗せされます。したがって、個別に介護保険料の計算を行う必要はありません。
厚生年金保険については平成29年9月を最後に引上げが終了し、令和4年9月現在18.3%で固定されています。こちらの料率を使用しましょう。
参考:厚生年金保険料率
【税金の計算】
次に税金についてですが、こちらも所得税と住民税の2つに分かれており、それぞれ以下のように計算を行います。
所得税の計算は、以下の流れで行います。
1.総支給額から社会保険料を控除した金額を算出
2.従業員の扶養親族の人数を確認
3.国税庁より公表されている「源泉徴収税額表」に、1と2を当てはめ、該当する金額を確認
3で使用する「源泉徴収税額表」は国税庁のHPより確認できます。
この表も毎年更新されるもののため、最新版かどうかを確認するようにしましょう。
参考:源泉徴収税額表(※令和4年時点)
続いて住民税についてです。
住民税は計算によって求めることもできますが、毎年5〜6月に各従業員が居住する地区の自治体が会社に通知書を送付してくれます。これを「特別徴収税額通知書」といい、ここに記載されている毎月の住民税額を控除する形で問題ありません。
法定控除に加え、会社によっては独自で定められている控除も存在します。これを法定外控除といい、代表的なものとして社内預金、財形貯蓄、社宅・寮費、親睦会費などが挙げられます。就業規則や従業員情報などをもとに、これらも計算していきましょう。
最後に、実際に従業員の手元に支給する給与額(手取り)を計算します。
冒頭で説明した通り、総支給額から、控除額(法定・法定外)を差し引きすることで算出できます。
支給額(手取り)が算出できたら、各従業員の銀行口座へ振り込み、給与明細を渡します。
給与明細は、従業員はもちろん、会社側にとっても支払い状況を確認するうえでの重要な書類です。従業員への支払い履歴は、賃金台帳に記録しておくとよいでしょう。
具体的な流れや計算方法について解説しましたが、実際に給与計算業務を行ううえでの注意点もあわせてご説明いたします
注意点の1つに、賃金支払いの5原則というものがあります。これは労働基準法第24条に定められており、給与を支払う側が守るべき重要な原則です。各項目の内容は以下のとおりです。
通貨払いの原則:
賃金は通貨での支払いを原則とし、小切手や現物給与などでの支払いを禁じるものです。
直接払いの原則:
労働者本人以外に賃金を支払うことを禁止するものです。労働者から委任を受けた委任代理人や、労働者の親権者などの法定代理人に支払うことは、原則できません。
全額払いの原則:
社会保険料や税金などの控除を除き、給与を全額支払いすることを定めたものです。
毎月1回以上払いの原則:
賃金は毎月1回以上支払うことを義務付けたものです。なお、勤続手当や精勤手当など臨時に支払われる賃金や賞与については、対象外となります。
一定期日払いの原則:
賃金は毎月25日などの、一定の期日で支払うことを義務付けたものです。特定の期日を設けないこと(15日から月末までの間など)や、変動する期日(毎月第3月曜日など)を設けることは禁止となります。なお、支払日が休日にあたる場合に日程を繰り上げもしくは繰り下げして支払うことは認められています。
上記5つの原則に違反した場合、会社に対して30万円以下の罰金が科せられますので、注意しておきましょう。
注意点としてもう1つ挙げられるのが、残業代の支払いです。
単純に支払いを行うということだけでなく、法で定められた割増賃金で正確に計算を行うことにも注意しましょう。
残業代が正しく支払われず、従業員が労基署へと相談に行くケースも少なくありません。その場合は会社に対して6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
先述の業務上の注意点とあわせて、どのようなリスクが存在するかについても説明します。給与計算を行う場合、これらも踏まえながら業務を行うようにしましょう。
給与計算業務では各種金額の計算上、従業員の個人情報を多く扱うため、ミスによる情報漏えいのリスクが伴います。
個人情報の漏えいが発覚した場合、従業員やその家族から訴訟を受けることや、場合によっては個人情報保護法によって罰則を受けることもあります。
従業員の納めるべき税金が計算上の不備によって正しく納められていなかった場合、後で本来よりも高額な納税が必要となる可能性があります。
場合によっては追徴課税を科せられることもあり、その際は税務署による税務調査や労働基準監督署の立ち入り調査などの対応を迫られることとなります。
金銭面だけでなく、対応にかかる工数の面でもリスクとなり得ることを念頭に置きましょう。
ここまで説明してきた内容から分かるとおり、給与計算は内容が複雑かつ、ミス無く正確に行う必要のある業務です。では給与計算をスムーズに行うには、どのような方法があるのでしょうか。
大きく2つに分けて説明していきます。
1つ目の方法として、給与計算システムの導入があります。
給与計算システムを導入するメリットとしては、大きく以下の2つが挙げられます。
導入メリットの1つは担当部署の負荷軽減です。担当者による手作業に代わってシステムが自動計算を行うため、単純に担当者の業務負荷が軽減されます。また機械による計算のため、手作業の際に発生していたヒューマンエラーも低減され、結果として確認作業などの負荷も少なくなるでしょう。
もう1つの導入メリットは法改正への対応がスムーズに可能な点です。給与計算は多くの法律に触れる業務であり、各法律の改正が行われるたびに業務上の対応が必要となります。給与計算システムではこの点を機能更新によって対応できるため、工数およびミスの削減につながるというメリットがあります。
給与計算システムは多くの種類のものが存在しており、それぞれ機能や料金などが異なります。導入を検討する際は自社に合ったものを選定するようにしましょう。
2つ目の方法として、アウトソーシング(代行)サービスの利用が挙げられます。
アウトソーシング(代行)サービスを利用しプロに業務をお任せすることで、正確かつスピーディーな遂行が可能です。
これにより給与計算システムと同様、担当者の負荷軽減、法改正へのスムーズな対応につながるでしょう。
また、特定の人員への業務集中が避けられるという利点もあります。
給与計算は属人的な業務になりがちで、特定の人員のみが行っているという場合も少なく有りません。自社のみでの対応では担当者がいなくなった際に業務が滞るリスクがありますが、アウトソーシング(代行)を依頼することで、このような問題も解消できます。
委託する業務範囲を柔軟に選択できる点もメリットとして挙げられます。アウトソーシング(代行)サービスでは、一部業務のみを委託、その他の業務とあわせて委託するなど、柔軟な業務範囲の選択が可能です。
必要な業務を適切に選定し委託することで、社内の業務効率化につながり、また自社対応に比べ人件費などのコスト削減が見込める場合もあります。
アウトソーシング(代行)サービスも、サービス内容や料金など会社ごとに特長が異なりますので、自社に合ったサービスを検討してみましょう。
本記事では、給与計算の概要や具体的な手順、注意点などについて説明してきました。
内容が複雑なだけではなく、リスク回避のためにも正確に行う必要がある業務ですので、よく理解したうえで進めていくことが重要です。
自社での対応が難しいと感じた場合は、最後にご紹介したような業務の委託も有効となりますので、必要に応じて検討してみることをおすすめします。

年末調整や住民税の計算など給与計算業務には年に数回繁忙期がありますが、繁忙期だけアウトソーシングしても給与計算業務は効率化できません。FOCはアウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性で、総合的に給与計算業務の効率化を支援します。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
Knock編集部
FOC当コンテンツ編集者。 FOCのwebマーケティングを担当兼当コンテンツ編集を担当。 「knock」を読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE