くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」
MENU
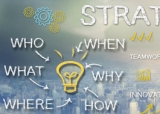

事業戦略の構想が明確で、かつアウトソーシング領域が明確であれば、問題がありませんが、通常はどの業務をアウトソーシングすべきか曖昧な場合があります。アウトソーシングの目的のひとつは、より作業的な部分を選んで外部リソースを活用し、自社リソースを重要な領域にあてることです。
したがって、自社にとって重要な業務=コア業務と言えるような領域をアウトソースすることは目的から外れます。目的を外さないようにするためには、自社のコア業務を見極める必要が出てきます。
しかし、企業の中には、コスト削減という言葉ばかりに注目してしまい、一体何が自分たちのコア業務なのか、判断できず、誤った業務をアウトソーシングしていることがあります。一例を話しましょう。
この記事の目次

ある企業X社は、消費者向け商品の副資材を扱っている企業です。食品の包装材や容器のようなものをイメージして下さい。こうした商品は差別化が難しく、顧客企業から見ると、価格や品質で大きな差がない限り、業者選定の理由になりません。顧客企業が最も重視するのは、かさばる在庫を替わりに保管してくれ、生産計画の変更に合わせてすぐ届けてくれる業者です。つまり、高いレベルの物流サービスが重要な選定なのです。
ところが、X社は物流を外注企業にアウトソースしました。日々トラック業者を雇い、送るだけです。何時に顧客につくのかわかりません。一日一回だけの大量輸送で、顧客に在庫を持たせます。緊急輸送はできません。顧客の評判は芳しくありませんでした。
そこで競合Y社が輸送を自社物流化し、高いサービスレベルで市場を席巻していきました。こうなると、X社は太刀打ちできません。品質も価格も同等なら、サービスが重要なのですから。
X社は、自社のコア業務を包装材・容器の製造と考えていました。そこで、コアではないと考えた物流を“ただのもの運び”としてアウトソースしたのです。一方、Y社は物流もコア業務をとらえ、物流を自社で行い、きめ細かいサービスを提供しました。Y社は今、市場の半分を握るガリバー企業へと成長しました。一方、X社はじり貧でY社の後塵を拝しています。

X社はアウトソーシングすべき領域を誤りました。何が自社のコア業務かきちんと見極めるべきだったのです。コア業務はアウトソースしてはいけません。一方、ノンコア業務はその業務を担う人員、体制、組織をアウトソースできます。
コア業務を見極める判断基準は以下のものがあります。この方法は、組織や体制全体をアウトソーシングするような場合ではなく、業務機能単位のアウトソーシング判断に使う方法です。
自社にとって、その業務領域が競争力に直結するものか、そうではないか、考察します。他社との差別化の要因になっているものは何か、顧客が最も重視していることは何か、顧客から最も支持されていることはなにかを見極めます。これらの条件に該当するのがコア業務です。
先のX社やY社が属する業界では、物流もコア業務です。品質・コストは当たり前であって、より顧客の求めるものが物流サービスになっていたのです。ここを読み誤ったために、X社はY社に敗れ続けているのです。
また、顧客を軸に判断するだけでなく、自社の判断軸もあります。スキルやノウハウが蓄積できる業務はコア業務ということができます。手放してはいけない領域です。企業の存続を左右するような業務です。たとえば、カメラメーカーにおけるレンズ製造、洗剤メーカーにおける界面活性剤製造、飲料メーカーの原液製造などです。シンプルにいえば、コア業務以外はノンコア業務で、アウトソーシングの対象です。
別な視点では、戦略的業務と定型的業務の区別があります。ある業務が戦略的な業務、分析と判断や意思決定を伴う業務か、あるいは定型的で作業的な業務、誰が行っても同じ結果となる事務処理業務かを識別します。定型的業務はアウトソーシングの対象です。
たとえば、予算策定は戦略的業務ですが、経理事務は定型業務です。前者はアウトソーシングできませんが、後者はアウトソーシングできます。
経営を支援するような業務は、企業秘密を扱ったり、経営者と直結して活動する必要があったりするため企業内で行うべき業務です。一方、業務遂行を支援する業務は、各社似たような業務のため、アウトソーシングの対象といえます。たとえば、人材管理は経営支援業務でアウトソーシングできませんが、給与計算はアウトソーシングできます。
上記をまとめると、自社でリソースを集中すべき機能とアウトソーシング対象としてもよい機能が見えてきます。
自社リソースで行うべきは、コア業務、戦略的業務、経営支援業務と判断される業務です。それ以外は、アウトソーシング可能な業務と考えられます。
一方、自社リソースで行うべき業務であっても、仕事を作業レベルに分解して、作業指示できるレベルにすれば、アウトソーシングできます。たとえば、経営支援業務であっても、調査業務などの作業であれば自社で行わず、アウトソーシングすることができます。
ただし、アウトソーシングするのは作業です。間違えても、意思決定や判断までアウトソーサーに委ねてはいけません。最近、「どうすればいいのか教えてくれ」という企業も増えています。仮にそうした問いかけをしたとしても、あくまでアウトソーサーが行えるのは「提案」までであって、その提案が果たして正しいのかどうか、見極める責任は委託元企業にあります。判断こそ、コア業務であり、戦略的な仕事なのです。判断業務までアウトソーシングしてはいけません。

アウトソーシングすべき領域の検討を終えたら、最後に懸念されるリスクを検討します。アウトソーシングの結果、権利関係で問題が出ることもあります。また、業務プロセスで見た場合に漏えい等のセキュリティ問題が出ることがあります。
権利関係で言えば、業務をアウトソースした場合、“かたち”として残るような成果物の権利がどちらに所属するかの問題です。たとえば、設計をアウトソーシングした場合の設計図面の権利です。設計の権利を自社に保持したい場合、リスクはないか検討し、設計をアウトソーシングすべきか、あるいはCADオペレーションなどの作業レベルに限定すべきか、また契約書で権利を取得できるようにしておけるか検討します。
また、アウトソーサー側の社員による情報漏えいなどの問題が起きないか、きちんとセキュリティの仕組みを考えることも必要です。近年、顧客情報の流出などで大打撃を受ける例が多くあります。アウトソーサー側の社員の情報持ち出しが原因になるケースもあります。情報漏えいリスクをきちんと検討し、果たしてアウトソーシングしても良いかどうか、情報漏洩を避ける仕組みは十分か検討が必要です。
このように、リスクの検討を経て、最終的にアウトソーシングすべき業務、作業領域を決めていきます。

FOCでは、30年・1,000社にご提供し続けている経理・人事・総務をはじめとした間接・事務業務に対してアウトソーシングのほか、RPA、AI、クラウドシステムを組合わせてサービス提供いたします。
こんな課題を解決します
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE