くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」
MENU

近年、RPAの導入で多くの企業が労働生産性の向上を実現しています。RPAの採用を検討しているものの、費用が気になる企業も多いのではないでしょうか?本記事では、RPAの導入コストと、費用負担を抑えるための補助金制度について詳しく解説します。

RPA(Robotics Process Automation)とは、主に企業の総務や経理、人事などのバックオフィスに多い定型業務をオートメーション化するための施策、あるいはそれに伴う技術のことを言います。
一連の作業をソフトウェアロボットに記憶させ、正確に再現させることで業務の自動化を図る取り組みであり、それを実現するシステムをRPAツールと言います。ただし、最近ではRPAツールのことも単にRPAと呼ぶことが多くなっています。
RPAで自動化できる定型業務とは、一般的に作業内容が一定のパターンに決まっている業務を言います。例えば、帳票の作成や顧客データの転記作業、請求書の発行といった仕事は、同じパターンの作業を繰り返すため定型業務に含まれます。
こういった仕事は単調ながらも、人間の手で行うとどうしても時間が掛かってしまう作業のため、RPAの導入によって自動化することにより、企業の労働生産性を上げることができます。
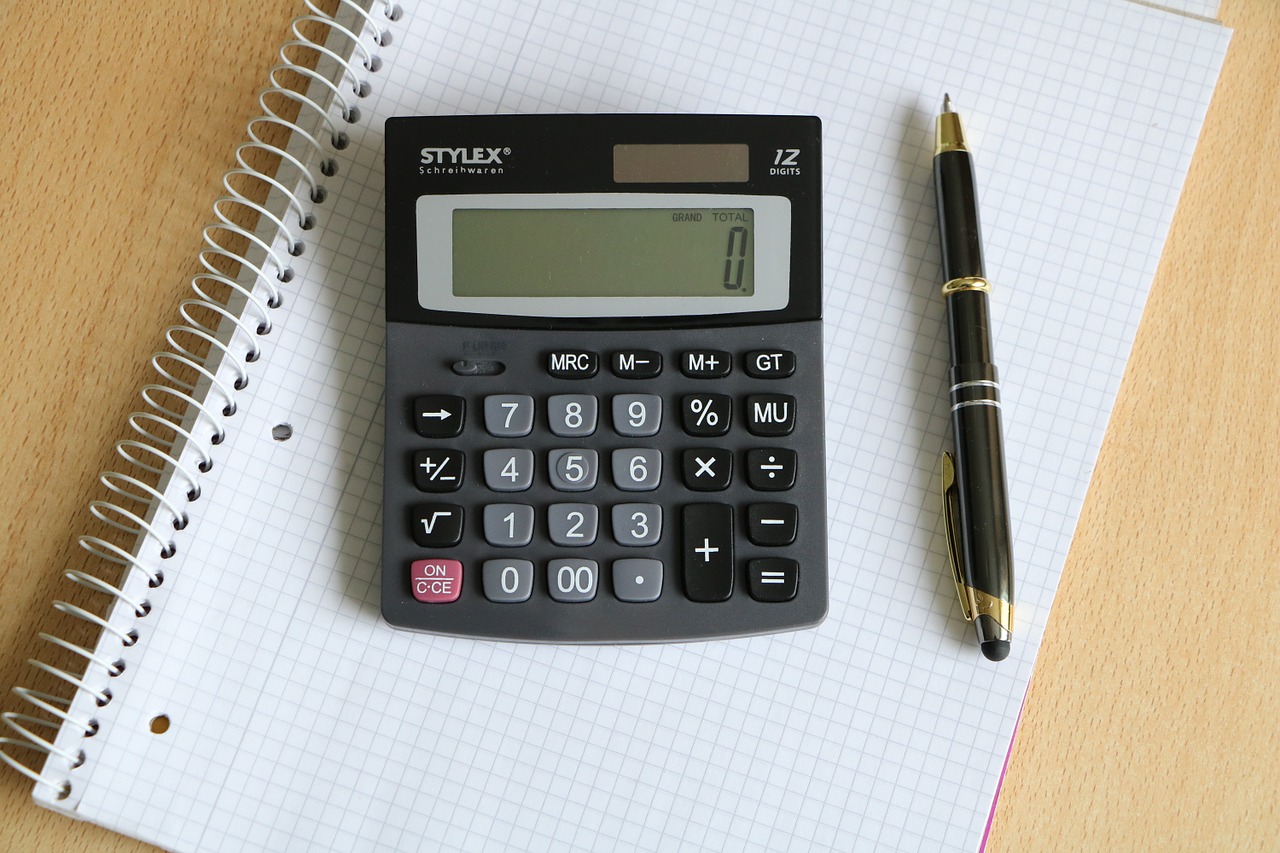
RPAの利用コストは導入時に掛かる費用(イニシャルコスト)と、月々の運用に掛かる費用(ランニングコスト)に大別されるほか、各ベンダー(サービス提供者)からサポートを受ける費用なども必要になってきます。それぞれみていきましょう。
RPAは「デスクトップ型」「サーバー型」「クラウド型」の3タイプに大きく分けられ、それぞれのタイプと導入する規模によって導入コストに大きな差が出るのが特徴です。当然、選択するサービスによっても費用は違いますが、大体の相場をまとめると次のようになります。
・デスクトップ型:0~20万円程度
・サーバー型:100万円~(※数千万円掛かる場合もある)
・クラウド型:30万~50万円程度
このように、初心者向けで初期費用が掛からないサービスもあれば、数千万円掛かるタイプもあります。特にサーバー型は大規模事業者向けのものが多く、費用についてはベンダーに問い合わせが必要なサービスが大半です。
また、トライアル版など無料で利用できるものもありますが、その場合、機能が制限されてしまっている可能性があります。
導入の検討材料として使ってみたいという場合にはおすすめですが、長期的な利用には向いていないでしょう。
RPAのサービスを利用するにはベンダーにライセンス料や使用料を支払う必要があり、それがランニングコストとなります。相場は次の通りですが、サービスによっては年間契約が必要です。
・デスクトップ型:月額5万円~(※フル機能版:月額10万円程度~)
・サーバー型:月額50万~120万円程度
・クラウド型:月額10万円~
なお、デスクトップ型RPAは、ロボットの開発と実行ができるフル機能版と、作業の自動化処理のみ行える実行版で費用が違います。
実行版は月額数万円で利用できるものもありますが、フル機能版になると月額10万円以上掛かるものが多いです。サーバー型とクラウド型の多くは、ロボットの開発と実行がともに行えるサービスになっています。
(ライセンス料は月額のものもあれば年間一括支払いのものもあります)
RPAの導入に当たっては、サービスベンダーのサポート費用も考慮すべきです。サポートなしでの利用も可能ですが、自社にIT技術者がいない場合はできるだけ依頼した方が良いでしょう。サポートの例として、次のようなサービスがあります。
・RPAによる自動化支援
・RPAツールのトレーニング
・運用ガイドラインの作成支援
・ロボットのメンテナンス
・ロボット作成に関する質問に回答
例えば、WinActor(NTTデータ)の場合、年間ライセンス契約をすれば、オプションで導入前に操作レクチャーやロボット作成支援サービスを受けられるだけでなく、年間50時間に限りRPAのシナリオ作成に関する支援などが受けられます。
RPAの導入コストを把握した上で、さらにRPAによる人件費の削減をはじめとした諸々の経済効果を試算できれば、費用対効果の算出が可能になります。
例えば、次のような計算式で費用対効果の金額が算出できます。
(削減できる人件費+生産性の向上によって発生する収益など)‐(1年間のライセンスコスト+1年間の保守コスト+1年間の教育コスト)
費用対効果が算出できたら1年間のランニングコストに対してどのくらい収益が上がるか、初期費用の回収までにどのくらい時間が掛かるかなどを考えてRPAの導入を検討することが重要です。

RPAの導入を検討しているものの、費用の問題で導入に踏み切れない企業も少なくありません。予算の面で不安がある企業は、費用負担を軽減できる補助金制度の利用がおすすめです。RPAの導入に関しては、以下の制度が使える可能性があります。
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者が自社の経営課題の解決に見合ったITツールを導入するための費用の一部を補助する制度です。ツールの導入対象となる業務プロセスの数によって補助金の申請額が変わり、上限30万~450万円の範囲で補助金が受け取れます。
補助率が1/2なので、RPAをはじめとしたITツールの導入に掛かる費用負担が半分になる可能性があります。詳しい補助金の上限額や申請条件については、公式ホームページを確認してください。
ものづくり補助金も中小企業や小規模事業者が対象の補助金制度です。企業が試作品の開発や生産プロセスの改善をするための設備投資をする際に利用でき、上限1000万~3000万円の範囲で補助金が交付されます。
補助率は原則として1/2なので、800万円の設備投資に関して申請が通った場合、400万円の補助金を受けられるということです。申請には細かい条件が定められているので、詳しくはものづくり補助金の総合サイトをチェックしましょう。
商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者(個人事業主)が申請できる補助金で、次のように業種と常時雇用の従業員数によって、申請資格の有無が決まります。
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業以外)の場合:常時雇用の従業員が5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時雇用の従業員が20人以下
・製造業その他:常時雇用の従業員が20人以下
補助対象事業者は各地の商工会連合会や、日本商工会議所からの支援を受けた上で事業計画書を作成し、担当事務局に申し込むことで補助金(50万円)を受け取れます。詳しくは公式ホームページを確認してください。

次に、現在注目されている人気のRPAツールをいくつか紹介します。気になるものがあったら、積極的に問い合わせをしてみましょう。
「Uipath StudioX」はRPA業界のリーディングカンパニーであるUipath社が2020年4月にリリースしたばかりのRPA開発ツールです。コードの入力なしでRPA開発ができるのが特徴で、ドラッグ&ドロップでスムーズにロボットの制御ができます。
Excelを中心に、あらゆるデスクトップアプリやウェブアプリに対応しており、企業が日常業務で利用している複数のシステムに跨る操作を簡単に自動化でき、作成した自動化フローは他のユーザーとシェア可能です。
とにかく使いやすさにこだわっており、無料ライアルもできるので、初めてRPAを導入する企業にもおすすめです。ライセンスごとの料金は次のようになっています。
・RPA Developer (RPA開発者向け)の場合:50万円〜80万円程度(年間)
・Citizen Developer (現場の方向け)の場合:30万円〜50万円程度(年間)
サービスサイト:Uipath StudioX
「WinActor」はNTTデータが提供しているRPAツールです。Windows上で操作可能なあらゆるアプリや業務システムに対応しており、一連の作業をワークフロー(シナリオ)としてロボットに学習させることで、業務の自動化ができます。
シナリオの作成支援などサポート体制が充実しているのも魅力です。フル機能版と実行版の2種類が提供されており、ライセンスによって料金が違います。
・ノードロックライセンス(1台だけライセンス導入)の場合:フル機能版90万8000円(年間)/ 実行版24万8000円(年間)
・フローティングライセンス(複数の部署など大規模に導入)の場合:フル機能版・実行版ともにオープン価格
サービスサイト:WinActor
「Axelute」は富士通が開発している自治体向けのRPAソリューションです。Windows上の操作だけでロボットによる自動化シナリオを作成でき、さらにシナリオの操作内容をもとにExcel形式で手順書を自動生成できます。
もともとデスクトップ型RPAでしたが、現在は自治体の全部署での利用を見越してサーバー型RPAの提供もされているようです。1台当たりの費用については、リリース時点で次のようになっています。
・デスクトップ型:スタンダード(シナリオ実行)版:2万円(月額) / エンタープライズ(シナリオ編集)版:6万円(月額)
・サーバー型:個別に見積もり
サービスサイト:Axelute
「NEC Software Robot Solution」はNECの開発した業務自動化ソフトウェアロボットです。定型業務を自動化し、人とロボットの協働を可能にすることで、企業の人手不足の解消と働き方改革の実現を後押します。買取ライセンスと期間ライセンス、フローティングライセンスの3つから選択でき、1年間のサポートパックも利用可能です。
・買取ライセンス:288万円~(1年間の保守込み)
・期間ライセンス:36万円~(3カ月ライセンス)
・フローティングライセンス:要問い合わせ
各ライセンスにはロボットの構築・実行ができる通常版と、ロボットの実行のみの実行専用版の2種類があります。詳しい内容と価格は公式ページで確認してください。
サービスサイト:NEC Software Robot Solution
「BizRobo!」はRPAテクノロジーズが提供しているRPAツールで、日本では特に知名度が高く、すでに1,500社以上の企業が導入済みです。現在、次の3つのバージョンが利用できます。
・BizRobo!mini(デスクトップ型):年額90万円(1アカウント)
・BizRobo!Basic(サーバー型):年額720万円
・BizRobo!Lite(サーバー型):年額180万円(同時稼働ロボット2台の場合)
実行ロボット数無制限の 「BizRobo!Basic」に対し、 「BizRobo!Lite」は同時実行ロボット数を制限することで、より安価に利用できます。詳しくは公式ホームページをチェックしてください。
サービスサイト:BizRobo!
「Automation Anywhere」はアメリカで市場シェアNo.1のサーバー管理型RPAソリューションです。全世界で1,000社以上に導入されているハイエンド製品で、AI(人工知能)による機械学習と自然言語処理機能を活用することで、非定型業務の自動化を実現します。
RPAと業務プロセス管理(BPM)を組み合わせたツールになっているため、業務全体の効率化を図りたい大企業におすすめです。利用料金は最低100万円(年額)となっています。
サービスサイト:Automation Anywhere
RPAの導入には導入コストとランニングコストに加えて、ベンダーからサポートを受けるための費用が掛かります。
RPAのタイプや導入規模によってコストが大きく変わってくるので、事前に費用対効果を試算して、自社のビジネス規模に合ったRPAを選択するようにしましょう。補助金の申請資格がある場合は、高額な導入費用を抑えられる可能性もありますので、積極的に利用しましょう。
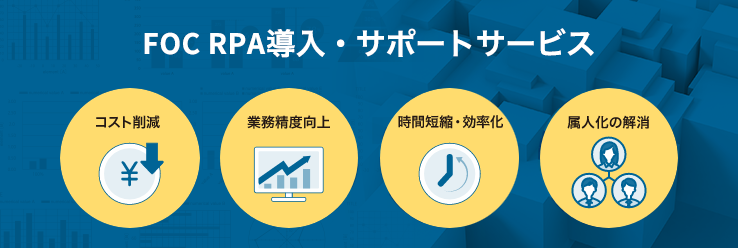
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE