パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。
MENU

RPAは多くの企業で導入されています。RPAによって通常業務を自動化することで、作業をより効率的に行うことが可能になるでしょう。どのような業務が自動化できるのかを、仕組みや導入事例を踏まえた上で紹介します。

RPAによって業務を自動化する試みは大企業のみならず中堅企業にも進んでおり、MM総研のデータでも導入状況は右肩上がりです。自社の業務が自動化できるかどうかを検証する前に、そもそもRPAとはどんなものなのか、具体的な定義について知っておきましょう。
引用元:https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=391
RPAは、正式名称を「ロボティック・プロセス・オートメーション」といいます。この場合のロボットとは人型のものではなく、パソコンやサーバーにインストールして使うソフトウェアのこと表します。
発注データの入力やアンケートの集計など、定型的なオフィス業務をロボットに代行させる仕組みそのものを指します。ロボットが人の業務を代行することにより、労働力不足の解消や人件費の削減などが可能になります。
RPAは、主に次の二つの業務を得意としています。
1.ルールが定型化されている業務
データの入力業務やパソコン内での手順が明確に決まっている業務を手順に沿って実行する業務を得意とします。電子化されているパソコン内のデータであれば、決められた処理方針の通りにツールを横断して対応することも可能です。紙のデータが存在する場合は、電子化するところから考えましょう。
2.大量の反復作業
人がやれば飽きてしまうような大量の繰り返し作業も得意です。さらにRPAは人よりもスピーディに24時間稼働できるだけでなく、大量の作業もミスなく完了することができるのです。
同様に、パソコン内にある大量のデータ収集・分析も得意としています。
同じようなケースで取り上げられることが多いため、混同されがちなRPAとAIですが全く異なるものです。AIとは「Artificial Intelligence」の略で人工知能のことを表します。AIについて深堀りをすると、実はさまざまな定義があり専門家の中でも意見は分かれています。ここでいうAIとは機械やシステムに組み込むことが可能で、データに基づいて判断ができる機能のことを指しています。
RPAは人が定めたルールに従い確実の作業を行う仕組みに対して、AIはゴールに対して大量のデータや情報から分析して自ら判断することができるのです。
RPA単体ではできなかったことが、AIと組み合うことによって可能性が広がります。7月には代表的なRPAベンダーのUiPathがAIモデルを活用できる新製品群をリリースしていましたが、今後このような取り組みはもっと加速していくことでしょう。

RPAの需要は大企業のみならず中堅企業にも増加傾向にあります。なぜ近年、RPAが注目されているのか、その背景を見ていきましょう。
一つ目の要因は、少子高齢化による日本全体の労働力の減少です。みずほ総研の調査では、2016年〜2065年にかけて労働力人口は4割減少すると言われています。
引用元:https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/pl170531.pdf
政府も女性が社会進出しやすい環境や制度構築や、高齢者の再雇用促進、多様な働き方を受け入れる制度の推奨、外国人労働者の受け入れなどさまざまな施策を試みていますが、すぐに解消できる問題ではなく浸透までに時間がかかります。
労働人口が減少していく中で、人の手のみを使った生産力の維持が難しいことから、効率化に向けた施策の一つとしてRPAに注目が集まっています。
二つ目は、企業の管理する資料や契約書などの重要な情報が、紙からデジタルへ切り替わっていることです。
クラウドサービスの登場などを筆頭に、日本では業務のデジタル化が進んでいます。このデジタル化と、パソコン業務を自動化するRPAは非常に相性が良いのです。また2020年10月、電子帳票保存法の改正もペーパーレスを促進の狙いがあります。テレワークが普及し始め、紙文化からの早急な脱却が進んでいるのです。
このような状況もRPAが導入が促進される理由のひとつとなっています。

RPAにも自動化できる業務とできない業務があります。RPAを導入することでどのような業務を効率化できるのかを紹介します。
RPAは、バックオフィス業務のような定形作業や単純作業、大量の反復作業が得意です。
単純作業がどれほど細かく膨大な量であっても、RPAなら人が行うより迅速に且つ正確に実行可能です。ロボットなのでストレスを感じることもなく、24時間休みなく稼働することができるため、業務のスピードも精度もあがります。
RPAはデータの監視やチェックなどのシステム監視やメンテナンスも可能です。社内のITシステムやサーバーへのアクセス、ログの消去などは決められたルールに則り作業を行えるためです。。
システムに異常があると即座にアラートが出るため、すぐに異常を察知できることから企業の信頼性向上にも役立ちます。
膨大なデータの収集、スコアリングも、RPAであれば迅速に行うことが可能です。
もしデータが紙の場合は、AI-OCR(紙から情報を読み取りデータ化するOCR機能に、学習するAI機能を活用し、読み取り精度を向上させていく)も活用すると良いでしょう。
PRAツールを導入することで、人の手からこうした業務を手放すことができ、本来集中すべき業務に、社員が集中して取り組めるようになります。
顧客や担当者からの問い合わせ、さらに社内からの問い合わせ業務などについても対応ができます。。24時間365日対応できるのは顧客満足度の観点からも大きなメリットになります。
チャットボットと組み合わせてよくある対応を定型化したり、有人対応が必要な問い合わせはオペレーターにつなぐといった業務を担当することで、カスタマーサポートの業務負荷を減らすことができます。
チャットボット、AI-OCRなど、他の技術との組み合わせでRPAの活用は広がります。

RPAを社内に導入し、業務を自動化するためにどのようなプロセスをたどれば良いのでしょうか。導入手順について詳しく見ていきましょう。
はじめに現状プロセスの洗い出しです。ここで、RPA導入できるかどうかの見極めを行います。導入対象と考えている業務だけではなく前後を含めた全体フローの項目を洗い出しましょう。項目が洗い出せたら、
・作業手順は定型化できているか、またはすぐできるものか
・要してる作業時間&対応している人数
この2つを中心にRPA導入導入範囲を定めていきましょう。量が多くても、フローやマニュアルが存在しない業務については手順を書き出してみて社内で協議してみるのも良いでしょう。合わせて、本当に必要な作業なのかの振り返りは必要です。担当者も「入ったときからやると決まっていたから」と無意味に続けている業務も見つかる可能性があります。日々行っている疑問に思わないことも、この機会に洗い出してみると良いですね。
自動化できそうな業務の候補が挙がったら、次はその業務のどこからどこまでを自動化するのか検討します。
例えば、RPAにメールマガジンの配信作業を任せたとします。リード(見込み客)を獲得を目的としている配信メールに対して、返信などのリアクションが合った場合、確実に分岐できる条件分けができるか、またでき場合はRPAに任せるのが良いのか人が対応するのかを具体的に議論していきます。
作業量が多い、単純な反復作業である、ミスが起きやすく確認のための人手が取られる…など人が苦手でRPAが得意なことから始めていきましょう。
RPAのツールには、設計に時間はかかるものの必要な機能を網羅している汎用型とそれぞれの業務に合わせてパッケージになっている特化型の2種類があります。特また、全社的な導入を考えているならサーバー型、一部の部署の特定業務に限定している場合はパソコンに直接インストールするデスクトップ型がおすすめです。
まずは自社に合ったツールを選定しましょう。自動化する業務や導入目的がツールと合っていないと、RPAツールを導入しても効果が発揮できず、導入に使ったコストが無駄になってしまう可能性があります。
社内環境も大切です。RPAを受け入れる環境が整っていないと、実際にツールを運用する社員間にツールが浸透せず効果が得られない可能性があります。
ツールの選定と、ツールを受け入れるための準備を整えましょう。
本格的な導入に至る前に、一部の部署や業務単位で導入するといった試験運用を行ってみましょう。全社導入を行った後に致命的な問題点や、ツールがうまく運用できないといった課題が浮き彫りになった場合に、修正が難しいからです。
最初は、無料のトライアル期間を設けているものや、完全無料のツールを活用してみましょう。そして、事前に想定していたことが合っていたか、運用に際しての課題を発見し、ひとつひとつなくしていくことが重要です。
試験導入の結果、浮かび上がったシナリオの問題点を修正していきます。通常処理の問題点の修正と、イレギュラーな処理に関する修正を施します。
特に、あらかじめ入力していないイレギュラーな処理が発生してしまうと、RPAはエラーを出し、処理が停止してしまいます。試験的な運用を行った結果、シナリオを組み込んでいない処理があった場合は修正が必須です。
RPAを運用する上でのルールやマニュアルなど、扱う側の環境も整えていきます。マニュアルのわかりにくい点を修正し、誰でもわかるマニュアルにすることがポイントです。
試験運用が終わったら、本格的な導入に移行していきます。各部署・チームの業務フローに合わせてRPAツールの細かい設定を行っていきます。
導入後は、定着化に向けて進めていきましょう。慣れるまでの間、使いにくさを感じたり、ストレスを感じたりする社員がいるかもしれません。そうした社員へのサポートも大切です。
そしてどのような効果が得られているのか、当初の目標や目的を達成できたか、といった効果検証を行いつつ、修正しながら運用を進めていきます。新規の部署ができた際も導入がしやすいよう、マニュアルの整備もあわせて進めていきましょう。

会社の部署や業務によって、RPAの使い方も異なってきます。ここでは、どの会社にもある代表的な部門ごとに、RPAの導入事例を紹介します。自社で導入する際の項目の参考にしてください。
経理部門では伝票入力、出入金の消込、社員経費の金額チェック等、入力業務や金額の称号にRPAツールが活用されます。。数字や入力項目を一つ間違えると膨大な確認作業が発生してしまいますが、ロボットによる正確な記入であれば誤表記のリスクが減らせるためです。
また、伝票データを取り込んでExcelやデータベースへ自動出力を行い、その後のデータの保存や仕訳といったフローまでを自動化することもできます。
申告書や決算報告書を自動で作成するといったこともできます。報告書や資料を作成するために、データベースから特定の項目を抽出するといったことが、RPAを用いて可能になります。
人事部門では、採用業務及び入退社手続きで活用されることがあります。採用活動の履歴管理、社員の情報の更新、福利厚生などの各種手続きの申請を行わなければなりません。また、労務管理も同様です。勤怠管理や残業、休日管理、通勤手当の申請等も定型的なチェックと確認が必要になります。ミスが許さず、煩雑でボリュームも大きい割に難易度は高くないことからRPAに最適とも言えます。
その他には、交通費の精算や労働時間を超過している部署や従業員へのアラート連絡など、人が行わなければならない連絡作業についても代用できるのです。
営業部門では主に、マーケティング稼働や顧客データの管理などに活用が可能です。顧客の個々の情報管理を基本に、伝票を取り込んで受注・販売のデータを更新する、提示資料を自動で作成するといったことが可能です。
また、顧客情報を元にした営業メールの送信は、営業担当者が行おうとすると膨大な作業になってしまいます。顧客のステータスやスコアに応じたメールの使い分けや、送信にベストなタイミングも見極めなければなりません。
RPAとCRM(Customer Relationship Management)、MA(Marketing Automation)などのツールと組み合わせて、顧客に最適な内容のメールを自動で送ることで、営業担当者の負担を軽減することができます。
マーケティング部門では、情報収集の作業が定型業務となります。顧客からの自社商品やサービスの評価、競合他社の発売している商品の価格などの情報収集などです。
こうした業務を、RPAを使って自動化します。Web上で他社の商品や評価を自動で収集し、データベースに落とし込んだり、または自社のチェーン店や別店舗から送信されてきた情報をExcelにまとめるといったことが可能です。
そうして情報処理が終わった際に、担当者に自動で連絡します。

社内のオフィス業務を自動化するためにRPAを導入するにあたって、いくつかの注意点があります。導入する際には以下のポイントに対し、解決策を持って臨みましょう。
RPAで業務を自動化できるといっても、ツール自体を管理、統括する担当者の存在は必要です。業務内容に変更があった場合にシナリオを修正したり、エラーが起こった際に即座に対応できなければ、RPAの運用管理は難しいでしょう。
また、作業を自動化することにより従来その業務を行っていた社員は他の業務に充たることができます。時が経てば退職等の都合により、RPAに任せている業務を知ってる社員がいなくなることもありえます。万が一システムのトラブルで停止した際に、業務を把握している人がいないと代わりに遂行することもできなくなります。また、RPA自体がブラックボックスになることを避けるため、しっかりと適宜監視、管理していくことが必要になります。
システムスキル面で不安がある場合は、RPAツールの選定段階で、事業者からどの程度サポートを受けられるのかを確認する必要があります。導入後の運用までフォローしてくれる事業者もいますので選定時に検討できると良いでしょう。
RPAはITツールのため、サーバーダウンやエラーなどで停止してしまうこともあります。そすぐさま復帰できる体制がなければ、その間の業務が停止してしまいます。特に重要な業務について、どこまでRPAツールに頼るかは考えなければなりません。
またRPAツールは、担当者がいなくても作業が自動で行われるため、担当者以外の人間にはどのように動いているのかがわからない、という状況にしばしば陥ります。
こうしたケースでは、担当者の異動や急な退職などがあると、誰もツールを修正することができないという問題が発生する可能性があるので、引き継ぎやマニュアルの作成はしっかりと行う必要があります。
RPA導入時にはコスト投資の目的を社内に事前に共有しておきましょう。
RPAに期待することは経営者と現場の社員に温度差があることが多いです。AI同様に自分たちの仕事を奪っていきかねない存在と言われがちのRPAです。導入する目的を明確にされないと「自分のしごとを奪われる」リスクと不安になる社員や、「残業が減る!」と仕事量の減少を目的と捉え、他の仕事を当てられたときに不満に思う社員が発生する可能性も生じます。システム導入は目に見えて「コストが掛かる」わかりやすい投資になるため、明確に使用目的を伝えておくことで余計な摩擦を生じさせないリスクヘッジになるでしょう。
また、RPAを管理する部門と、実際にRPAを操作する部門の方向性の違いからも摩擦が起こる可能性があります。管理部門では安定した稼働を求め、実際に動かす部門では常に最新の状態で使用したい、といった違いです。
こうした問題を解消するために、何のためにRPAを導入するのかは、社内で事前にすり合わせて、会社全体で共有しておくことが求められます。
RPAは定型業務を自動化することができます。業務効率化や人件費削減などさまざまなメリットがあり、導入する企業は増加傾向にあります。
自動化する際には、導入による摩擦を防ぎ、スムーズに浸透させるために、目的や効果をある程度想定し、社内で情報を共有することが肝要です。自動化できる業務を部署ごとに選別して適切なツールを選択することで、より大きな恩恵を受けることができるでしょう 。
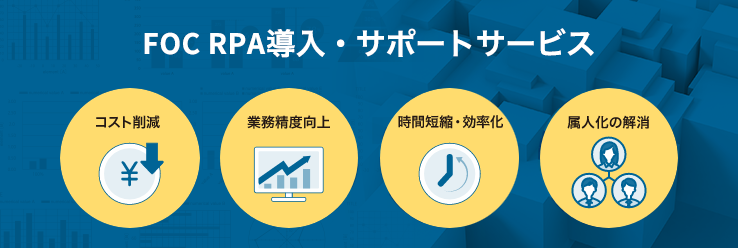
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE