パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。
MENU

RPAのツールには機能や価格が異なるさまざまな種類があります。企業からのシェア率が特に高いツールを紹介しますので、自社導入の際に参考にしてください。RPAが注目される背景や市場動向から、的確なツールの選定について考えてみましょう。

RPA(Robotic Process Automation)とは、定型業務をロボットを使って自動化する技術のことです。海外では一般的に普及していますが、近年は日本でも導入が進んでいます。
どの程度日本で導入が進んでいるのかを、リサーチ・コンサルティング会社のMM総研がリリースしたデータを基に見ていきましょう。
大手企業の50%が導入
上記の「RPA国内利用動向調査2020」のデータによれば、2019年11月時点でのRPA導入率は、全体で38%、中小企業で25%、大企業で51%となっています。RPAの導入率は、大企業が高い傾向にあります。
さらに、大企業では導入率は年々増加傾向にあります。中小企業でもRPAの導入を検討している企業は増え続けており、RPAに対する注目度の高さがうかがえます。
AIとの併用化が進んでいる
同資料によれば、AI(人工知能)との併用が進んでいることも明らかになっています。
特に製造業の品質管理などに多く活用されていて、2018年時点ではAIの導入率は26%であったものの、翌年は36%に拡大しており、10ポイントの伸びが見られます。
AI導入率をRPA導入の段階別(導入済・準備検討中・未導入)で見ると、導入済みの企業でのAI導入率は77%に足していて、RPA導入企業のAI導入率が高いことがわかります。
このことより、RPAを活用する企業とそうでない企業で、デジタル活用に差が現れていることが明らかとなりました。

RPAの導入率は大企業を中心に、年々増加傾向にあることがわかっています。なぜRPAが注目されているのかを、労働人口と働き方改革の二つの要因から見ていきましょう。
労働人口の不足
少子高齢化が進む日本では、労働人口の不足が問題になっています。2060年には人口のおよそ40%が65歳以上となり、労働力人口は2010年代と比較して、およそ6割ほどにまで減少すると言われています。
現時点においても、慢性的な労働人口の不足はどこの業界でも問題視されている状況です。この状況を打開するために、IT技術による効率化・自動化によって人間の代わりとなる労働力を確保しようという試みがなされてきました。
RPAの導入はその一環です。オフィス業務を自動化することにより、労働力を確保することを目的とした導入が進んでいます。
働き方改革の実現に向けて
2019年から施行された働き方改革関連法では、大企業・中小企業ともに長時間労働の制限や有給休暇の消化などを企業に求めています。
そのため、従業員の全体的な労働時間を削減し、より効率的な働き方の仕組みを作る必要があるのです。
RPAの導入は、労働の効率化や自動化により、従業員の労働時間を削減するという課題の達成に貢献します。
加えて、ロボットに簡単な業務を任せることで、人間の労働者に、よりコアな業務を担当させることができるというメリットもあります。こうした背景によってRPAの導入が進んでいるのです。
ITの浸透
RPAに注目が集まる前から、紙の書類からデジタルへの切り替え、クラウドツールの導入など、ITの浸透が大企業・中小企業ともに進んでいます。
ITの浸透とともにRPAの導入が進んでいるという側面もあります。
例えば発注書の作成が手書きではなく、パソコンで行えるようになれば、RPAを使って自動で作成することも可能になります。データの入出力やデジタル資料作成など、パソコン業務を自動化する技術は、RPAととても相性が良いのです。

RPAを導入することにより、企業にとってどのようなメリットが発生するのでしょうか。具体的に解説していきます。
人件費の削減
RPAツールは、オフィス業務を人が行うよりはるかに速く正確に処理することができます。これによる大きなメリットは人件費の削減です。
例えば、それまで10人で行っていたデータの打ち込み業務を、RPAによって自動化することで担当者が1人でもこなせるようになったとします。すると9人分の人件費が削減できるということになります。
RPAツールの導入・運用にもコストはかかるものの、人件費と比べればはるかに安上りです。
生産性の向上
RPAツールはルールに従って正確に作業を進めていくため、人間の作業にありがちなミスを防止することができます。加えて、人間とは違って24時間働かせることも可能です。
勤務時間外でもデータの処理や登録を自動で行うことができ、業務負荷を抑えることができるため、生産性の向上につながります。
必要なリソースを集中できる
業務の中には、人間にしか対応できない業務も多くあります。単純作業を機械に任せ、人的リソースを人間にしか行えない業務に集中させることが可能です。
新規事業戦略の企画や提案など、会社の利益や経営方針に関わるコアな業務に、投入すべき人材を投入することができます。
業務に携わる作業者も、単純作業に囚われることなく、本来すべき仕事に全力でパフォーマンスを発揮できるのが、大きなメリットと言えるでしょう。

RPAツールは海外の大手企業から国内のベンチャーまで、さまざまな事業者が開発しており、多くの種類があります。
その中から、自社にとってもっともパフォーマンスを発揮できるRPAツールを選ぶためには、どのようなポイントを注視すべきでしょうか。
サーバー型・クラウド型・デスクトップ型の3つに分類される
サーバー型はサーバーの内部で稼働するRPAで、複数のシステムやデータベースを横断的に処理するのに利用されます。
クラウド型はいわゆるSaaS(Software as a Service)形態でインターネットを経由してRPAの機能を利用することができます。
サーバー型は価格的にはデスクトップ型やクラウド型と比較すると高くなりがちですが、「システムやアカウントの管理が一括して楽に行える」「複数のロボットをサーバー内で稼働させられる」と言ったメリットがあります。
一方、デスクトップ型はパソコンにインストールして稼働するタイプのもので、特定のPCで行っている作業を自動化することが可能です。
パソコン1台からも導入することができるため、その分利用価格もサーバー型と比べて安くなっています。
適正な規模と価格
基本的には規模と価格は比例します。全社で導入するような大規模なRPAの場合、月額で数十万円かかるものも珍しくありません。パソコン1台から導入するような小規模のものであれば、無料で利用できるツールもあります。
機能の種類やできること、導入規模などを検討した上で価格として適正なものを選びましょう。価格にこだわるあまり、必要なパフォーマンスが発揮できないとなれば、導入する意味がなくなってしまいます。
特化型と汎用型のどちらか
RPAには、特定の業種のみに対応した特化型と、さまざまな業務に対応した凡用型のツールがあります。
特化型のツールには、特定の業務に関する機能が充実しています。例えばマーケティング業務であれば、顧客データの管理を行うだけでなく、メールソフトと連携させて顧客ごとにメールを送信したり、メールの解析を行うといったことが可能です。
一方汎用型はプログラミングや画面設定によりRPAをカスタマイズすることにより、幅広い業務に対応できます。自動化する業務を選定した上で、どちらのタイプが良いのかを見極めましょう。
セキュリティの要求レベル
RPAツールに、どの程度のセキュリティを要求するかによってもツールの選び方は変わってきます。
高いセキュリティを求めるのであれば、複数のアプリやパソコンを一律で管理できるサーバー型のRPAツールが適しています。管理権限を操作できるか、ログイン認証機能はあるかなど、求めるセキュリティの要求レベルも、自社のセキリティポリシーに照らして明らかにした上でツールを選定しましょう。

RPAツールの中でも、国内企業からのシェア率が高いツールを紹介します。ツールの特徴や機能についても、それぞれ見ていきましょう。
国内開発で扱いやすい「WinActor」
「WinActor」は、NTTグループの企業であり、光デバイス・電子デバイスの設計・開発・販売を行っている「NTTアドバンステクノロジ」が開発したツールです。完全日本語である点やシンプルな操作性によって、日本人に使いやすく設計されています。
WindowsPCで動作するソフトの操作手順を学習し、パソコンで自動操作できる機能を持っているのが最大の特徴です。マイクロソフト製品やブラウザ、その他の業務用システムの動作を自動化することができます。
基本はデスクトップ型のソフトですが、管理ソフトを導入することでサーバー型RPAとして活用することも可能です。
大企業での浸透率1位「UiPath」
先述したMM総研の「RPA国内利用動向調査2020」内でも、「UiPath」は大企業での浸透率1位に選ばれているRPAツールです。ドラッグ・アンド・ドロップで行える開発のしやすさや、拡張性、管理のしやすさでシェアを伸ばしています。プログラミング機能を使うことで、より高度なシナリオを作成することも可能です。
サーバーでの中央管理から、パソコンにインストールして使うこともできるので利用幅が広く、開発環境を提供するStudioやアプリケーションの動作をテストするTest Suite、ロボットを管理するOrchestratorなどさまざまなツールを提供しているのが特徴です。
国内実績トップクラス「BizRobo!」
国内1500社以上での業務代行実績があり、10業界20業種40社とパートナー連携をしている豊富な実績を持つツールです。
ユーザーが業務の特性や事業戦略に合わせて使えるように、スモールスタート向けのminiやオーソドックスなBasic、紙処理事務のDocumentなどのいくつものラインナップがあります。
ドラッグ・アンド・ドロップで設計できる使いやすさや、開発用ツール「Design Studio」を使うことで、手順に沿って操作するだけで自動化が行えるフローの組みやすさで、ノンプログラマーの企業でも導入しやすいのも特徴です。
製造・流通で多数実績を持つ「Axelute」
「Axelute(アクセリュート)」は、富士通が自社のテストツールを一般向けに改修して販売されました。記録した内容からエクセルのマニュアルを自動生成することができるので、属人化するリスクを薄めることができます。
直感的な操作でシナリオの生成・共有も行えるので管理がしやすく、シナリオの再生結果をサーバー上で確認し、どのように使われたのかを確認することもできます。
製造業・流通業などで豊富な導入実績を持っており、信頼のできるツールです。

RPAツールは、日本だけでなく海外の企業でもすでに一般的に利用されており、豊富な種類のツールが揃っています。ここでは、海外のシェア率が高く、日本でも使いやすいRPAツールを紹介しましょう。
グローバル実績の豊富な「Blue Prism」
「Blue Prism」は、英国に本社を置く企業が提供しているRPAツールで、日本では2017年に法人が設立されました。
世界で1,800社を超える企業が導入していて、日本でも導入数を増やしています。RPAの導入に際して、特定のPCを切り離して管理する、ログイン履歴を含む監査ログの暗号化など、セキュリティに強いのもセールスポイントです。
操作性にも優れていて、フローの部品をドラッグ・アンド・ドロップで移行する、順番ではなくどこからでもフローを設計できるレイアウトの自由度が魅力です。デバッグ機能にも優れ、自由度の高さと相乗して開発しやすい環境を作り上げています。
アメリカのRPAトップシェア「Automation Anywhere Enterprise」
「Automation Anywhere Enterprise」は世界で3,000社以上の導入実績があり、アメリカでトップシェアを誇るRPAツールです。大規模導入や、複雑な業務を自動化する点において優れています。
WindowsアプリからWebアプリ、データベースやOCRなどさまざまなシステムとの連携が可能な点もポイントです。できることが多く、部門やユーザーごとの細かな管理が可能で、どこからでもロボットへの実行指示を行えます。
Automation Anywhere Enterprise
2万5000件以上の顧客を抱える「NICE」
意思決定の必要・不必要どちらのケースでも対応ができる柔軟なシステムが特徴なのが「NICE」です。アナリティクスによる分析により、日常の作業を分析してRPAで実行可能なプロセスを提示してくれるので、自動化する業務の分別が楽に行えます。
OCRやチャットボット、機械学習技術との連携も可能で、さまざまなフロントオフィス業務を中心に効率化が行えます。実際に、導入している企業の種類もIT・通信・金融・保険などと他業種に渡り、幅広い業務に対応できるのが特徴と言えるでしょう。
200以上のグローバルパートナーを持つ「Pega Robotics Automation」
「Pega Robotics Automation」はマーケティングや営業支援、顧客管理などの機能を総合的に備えた「Pega Infinity」の一部として統合されており、そのためPegaのユーザー企業が他者のツールと連携することも想定されています。
他のアプリやシステムとの連携がとりやすく、特にBPMS(ビジネス・プロセス・マネージメント・システム)との連携を円滑に行うことができます。
米国退役軍人省、三菱UFJ銀行など、大手の企業や省庁にも導入されているグローバルなツールです。

上記に紹介したツール以外にも注目すべきRPAツールは数多くあります。その中で代表的なツールについて、理由と共に紹介しましょう。
提案機能のある「NaU DSP」
「NaU DSP」は「前進判断」「後進判断」「提案型判断」という3つの推論機能を持っています。これにより、利用ユーザーに対し多角的な提案をすることが可能です。
例えば年齢・性別・地域などの個人情報からおすすめの商品を自動で導き出すだけでなく、複数の商品を導いたり、商品から個人情報の一部を推測するといったことが可能です。
そのため、複雑なルートのシナリオでも組みやすくなっており、高度な意思決定にも活用できます。データチェックや手続きの自動化など、フローの異なるさまざまな業務を自動化できるツールです。
ソフトバンクが提携する「SynchRoid」
ソフトバンクが提供しているツールで「SynchRoid」は、リリース前に実際に同社内で導入し、効果が実証されたことでも知られています。そのためソフトバンク社のサービスとの提携がしやすく、すでにソフトバンクのサービスを利用している企業には特におすすめです。
「SynchRoid」の公式サイトでは、自動化する業務の選定サービスや、開発スキルや業務フローの書き方のトレーニング講習を提供していて、スキルアップにも有効です。
完全無料でRPAツールを提供する「WorkFusion」
「WorkFusion」(ワークフュージョン)の中でも「RPA Express Starter」は完全無料で提供されていて、世界150ヵ国で2万5,000以上のダウンロード実績を持っています。
「RPA Express Starter」はデスクトップ型のRPAツールですが、複数ロボットの集中管理を行いたい場合は有料版の「RPA Express Pro」への移行、さらにAIと併用したい場合は「Smart Process Automation」に移行するといった具合に、用途に合わせてプランを選ぶことが可能です。
特に「Smart Process Automation」は複数のテクノロジーと組み合わせ、事務作業全体の8割ほどを自動化できると言われています。
クラウドRPAとしてグッドデザイン賞を受賞した「BizteX cobit」
「BizteX cobit」はクラウド型のRPAツールであり、インストールなどの準備は不用です。そのため専門知識も必要なく、最短で即日から利用できるようになります。
直感的なUIで操作がしやすく、2018年にはクラウドRPAとしてグッドデザイン賞を受賞した実績もあります。クラウド型なのでPCがなくても実行が可能で、管理ツールがなくても実行結果を確認することもできます。
トライアル期間も設けられており、とにかくスピーディーに導入したい企業におすすめです。
RPAツールを導入することで定型業務を自動化し、その分浮いた人材をコアな業務に振り分けることができる、などのメリットがあります。労働人口の減少やデジタル化を背景に、日本でも着実に導入企業数を伸ばしています。
RPAツールには、サーバー型やデスクトップ型、特化型や汎用型などさまざまなタイプがあり、自社の目的や利用環境に合わせてツールを選ぶことが重要になります。
シェア率の高いツールはそれだけ導入実績もあるので信頼性も高く、導入を検討するにあたっては一つの指標となるのではないでしょうか。
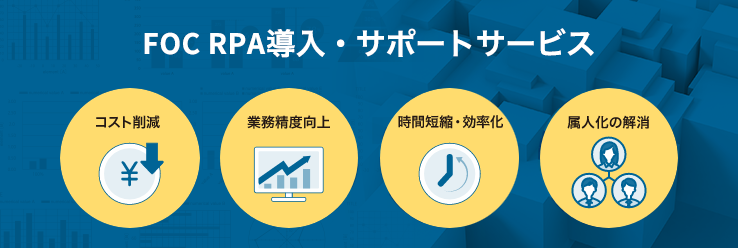
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE