くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」
MENU

労働を取り巻く環境の変化によって、日本企業では業務効率化が求められています。業務効率化を実現する手段の一つとしてRPAの活用が注目されています。それではRPAを活用することによってどのようなメリットがあるのでしょうか。自社に合うかのイメージがつけられるように事例と共に見ていきましょう。

「働き方改革」や「DX」などと共に近年注目を集めているのが、「RPA」です。言葉としては聞いたことはあるものの、実際にどのようなものか知らないという方もいるでしょう。
RPAの概要から、混同されがちなAI、OCRとの違い、そして具体的な活用シーンについてご紹介します。
RPAは「Robotic Process Automation」の略語
RPAとは「Robotic Process Automation」の頭文字を取った言葉で、人間に代わってロボットが業務を行い、自動化する仕組みのことを指します。
自動化できる主な業務内容は、データベースへの入力や電子書類の作成など、作業工程が決まっている定型業務で、AIを用いてより高度な業務を自動化することもあります。
大手企業を中心に、導入する企業が近年増加の傾向にある技術です。
近年、RPAが注目されてきている理由
RPAが近年注目されているのには、大きく2つの理由があります。
1点目は、労働人口の減少です。少子高齢化の社会を迎えている日本では20~65歳の働ける年齢の人口不足が大きな問題となっています。厚生労働省の試算では、2040年頃には就業者数は現在の20%ほども減少するとの見込みもあると言われています。
人手不足については、外国人労働者の活用や産休育休を機に退職をしてしまう女性の活用、定年後のシニア活用などの施策が政府により後押しされていますが現場に落とし込むまでには時間がかかります。
2点目は働き方改革の推進です企業はここ数年の働き方改革に関連する法案の改正に伴い、現状の働き方について見直しが急務となっています。長時間労働の抑制をはじめとした労働環境の改善を行いつつも、企業としての成長も考えなければならないところです。そのため、非生産的な業務をシステムやロボットへの代替を検討し、優秀な社員を本質的な活動に集中させるための施策の一つとしてRPAが注目されているのです。

RPAを活用することにどのようなメリットがあるのでしょうか。RPAを導入した企業の報告などから見られる顕著なメリットを紹介します。
社員のリソースをコア業務に集中できる
RPAはパソコン上で行うデータの収集や分析、手順が決まっている単純作業などを自動化することができます。人が行うと時間がかかったり、ミスが発生したり、と生産性をあげるたうえで弊害は大きいものですがシステムであるからこその強みが発揮できます。
そして、従来これらの業務を担当していた社員のリソースは頭を使う、本質的な業務に充てることが可能になります。人とシステムの得手・不得手を最大限に活用できるメリットです。
個別の判断が必要になる、複雑なプロセスを辿る業務、商品開発などの創造性が必要な業務はまだまだ機械による代行は難しく、人の能力が必要です。このような業務は企業の成長に繋がります。企業の成長のために、適材適所の配置が実現できると言えるでしょう。
24時間365日稼働できる人間が業務を行う場合は平日に最大8時間程度度ですが、RPAは24時間365日稼働し続けることができます。
通常の稼働でも人間より迅速に作業を進められるRPAですので、大量であればあるほど成果を実感できるでしょう。さらに単なるパソコン上の作業だけではなく、営業活動にも活用できます。
例えば、チャットボットと組み合わせてカスタマーサポート業務に活用する事例もあります。有名な企業では、JALのバーチャルアシスタント「マカナちゃん」のようにAIチャットボットとRPAの掛け合わせでお得に旅行できる時期と商品のリアルタイム提案ができるようになるなど新しい顧客体験も始まっています。
これは高度な事例ですが、チャットボットとの連携はRPAの代表的な活用方法です。Webサイト上にチャットボットを仕掛けておいて、問い合わせがあった際にはあらかじめ決まておいた定型の回答を返すような仕組みを提供できます。
参照:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000281.000030684.html
人件費やの削減や退職リスクの回避
RPAはコンピューター1台で何人分もの働きをすることが可能です。RPAで1アカウントを運用するコストは同時間人を雇うコストよりはるかに安く済む可能性が高く、人件費削減効果が見込めます。更に休日手当や残業代などの特別手当も発生しません。さらに、人ではないため異動や退職リスクによるノウハウの消失や採用工数も発生しません。
削減時間については、損保ジャパンさんの事例が顕著で、年53万時間の削減に成功しています。自社でも必ず人件費より安くなるかどうかは、対象となる業務量やかかっている時間・作業内容によって判断すべきですが、業務が多ければ多いほどシステムで代用できるメリットは大きくなることでしょう。
参照:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01061/122600009/
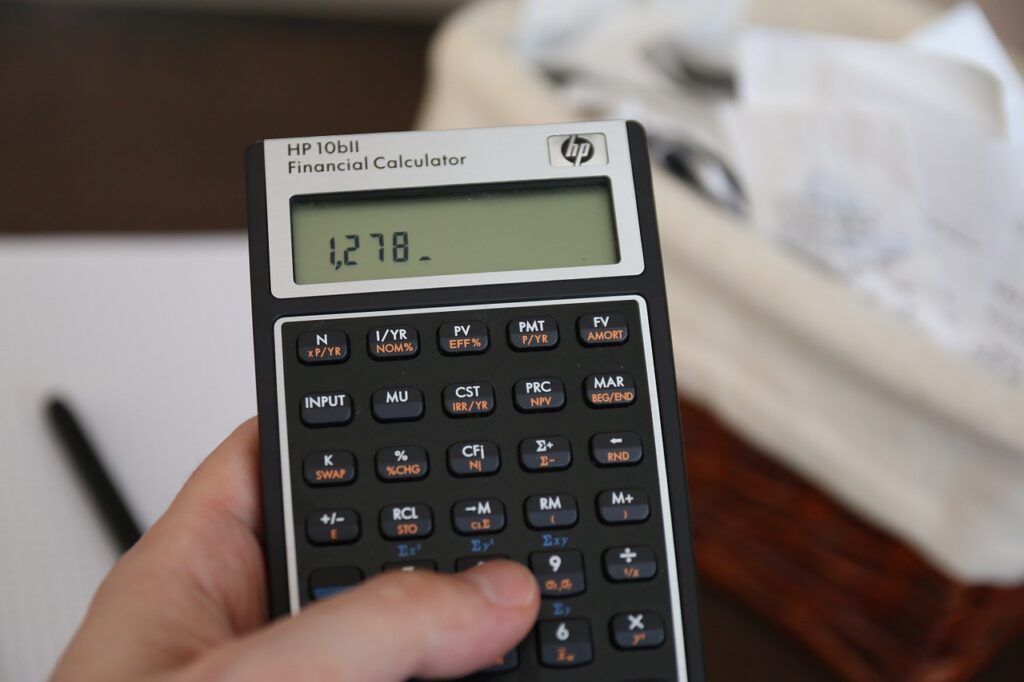
それでは、他社はRPAを具体的にどのような業務活用しているのでしょうか。細かな業務ごとの事例をご紹介していきます。RPAの活用事例は多くの業種、業態、職種で取り入れられてますのでここで全てはご紹介できませんが、自社の状況と照らし合わせ、ここまで対応できるのであれば自社で検討しているものもあるかもしれないと何かしらのヒントになれば幸いです。
活用ケース1:通勤費、交通費精算のチェックができる
ワークフローシステムなどの活用をしても、通勤費や立替交通費が適正金額であるか、会社のルールに沿った申請であるかのチェック作業は人の手が入っている企業も多いのではないでしょうか。
交通費計算は、社員の自己申告を鵜呑みにするわけにいかず、個別ルートの検索、最安値であるかのチェックは一つ一つを行うと膨大な時間がかかります。また人の行う作業のため、結局はミスも発生します。それが社員全員分となると、それだけでリソースを大きく使わなければなりません。この作業に、RPAを導入するだけで上記のすべての工程を自動化できるようになります。
申請された交通費が適正かどうかを判定し、適正でない場合はアラートを立てて責任者に知らせるといった仕組みを作ることができます。これにより、経理部門の負荷を大幅に減らせることが可能になります。
活用ケース2:請求書発行業務
活用できる代表的なバックオフィス作業として、請求書発行業務が挙げられます。作業量も多く、ルールが定型化されている業務のため真っ先に考える人も多いでしょう。売上伝票やEXCELデータから販売管理システムに入力し直しを行っていることで作業時間も倍かかり、人が行うと入力ミスが発生しやすくなります。
請求書のミスは企業の信頼性を損ねる可能性があります。また、クレームにも繋がりやすいでしょう。作業の軽減、コスト削減というだけでなく企業の信頼力向上にもつながります。
パソコン内のアプリケーションであれば横断して作業することが可能なため、請求書作成、発行業務はRPA代替に最適です。
活用ケース3:ダイレクトメールの自動生成
ダイレクトメールの生成も、RPAで自動化することが可能です。ダイレクトメールで効果を高めるには、顧客の購買履歴やサイトへのアクセス履歴などから欲しい商品を予測したり、欲しいタイミングを見計らってメールを送るといった作業が必要でした。
またイベントの案内のメールを送るのにも、参加者1人1人の情報を確認して、名簿を作成するだけでも大きな手間が掛かってしまいます。
RPAを活用することで上記のような作業を自動で行うことができるようになります。顧客1人1人に対する分析も、人が行うよりも正確に行えるようになるでしょう。
活用ケース4:営業やマーケティング部門も効率化へ
営業部門にも非生産的な業務はたくさんあります。契約書類、受発注や納品などの売上に関わる書類、出荷・在庫確認など営業事務の人たちの手助けなしには売上を作ることはできません。そのため営業活動にもRPAによって効率化できる業務は多くあります。まだ紙文化が多く残る営業活動ではOCRとの組み合わせが特に便利でしょう。
例えば受発注業務や購買業務を紙ベースでやり取りしていれば紙からシステムへの入力に人手がかかります。この一連の業務をOCRとRPAで自動化が可能になります。同様に、名刺管理や顧客情報の管理にも活用できます。
営業活動を支援するマーケティング業務も同様です。顧客情報の管理、ステータスの管理など多くの情報とデータを収集し管理する必要があります。人が行うとミスも起こりがちで正確な分析につながらないリスクもありますが、システムで対応できればミスなく素早く営業活動に活用でき会社のいち早い成長に繋がるのです。
大手のRPAベンダーUipath社が名刺管理SansanやCRMのSalesforceと連携が進んでいることもこのようなニーズの多さが伺えます。
参照元:
・https://www.uipath.com/ja/newsroom/connector-for-salesforce-sansan-2020-08-07
・https://www.uipath.com/ja/solutions/technology/sansan
活用ケース5:勤怠管理、労務管理
勤怠データの管理は、人事・総務における重要な仕事です。出退勤や休憩時間から社員の労働時間を把握するだけでなく、休日の管理、時間外労働時間は法律でも定められているため、厳重に管理しなければなりません。
また、社員の給与・税金の計算のベースにもなるので、ミスや把握漏れが許されない業務でもあります。勤怠データの管理・収集は、会社の規模が大きくなり、人数が増えるほど作業が大変になります。
勤怠管理システムの導入で解決する場合もあれば、規模や業態によっては紙の勤怠管理を手放せない会社もあるでしょう。特に、FAXやEXCELデータなど複数の媒体を活用して手作業で集計している場合にはOCRとRPAの組合みわせでぐっと業務が効率化できる可能性が大きいです。
人がやると煩雑で大変な業務ですが、作業内容自体は非常に単純で、ルールが明確化されているためRPAの得意分野と言えます。
勤怠の話では、キリンビールさんが有名です。21年に労働時間削減で9万時間を掲げ、RPA導入を加速しています。取組の一つとして名古屋工場で残業時間の集計、分析などの労務管理をRPAで行っています。今後3工場に増やしていくとニュースがありましたが、いきなり全社ではなくスモールスタートして改善しながら拡大していくという最適な進め方の見本と言えるでしょう。
参照:https://news.line.me/issue/oa-newswitch/27255948c7b5
活用ケース6:在庫管理を徹底できる
製造業や流通業における重要な業務のひとつが在庫管理です。資材・商品などの在庫管理は正確に把握することが求められます。実際と管理するシステムデータの在庫にずれがあると、在庫がないにも関わらず受注するなど大きなトラブルになり得ます。
例えば流通業であればネット通販が主流になっている今はリアルタイムに正確な在庫管理、販売ができれば機会損失せずに売上に繋がります。
また、注文に迅速に対応するためにも、在庫の出入荷は正確に管理し、部門を超えた情報共有が必要です。メールシステムとも連携させることで関連部署の人もすぐに在庫状況を把握することが可能になります。
在庫管理や出荷連絡などは人の管理が主流でミスが発生しがちで社内外のクレームとトラブルが絶えない問題でした。このようなヒューマンエラーも減らせて、正確で迅速な対応が可能になるため、受発注から在庫管理、出荷などの一連の活動をRPAに代替させることはおすすめの活用法です。
活用ケース7:会計・経理業務の自動化
会計・経理業務はRPAとは非常に相性の良い業務になります。これらの業務は定常的に決められたルールと手順に基づいた作業が多く、RPAの得意とする領域だからです。
伝票入力や支払い処理、決算書の作成各種書類の作成など作業が発生するタイミングが決まっています。たとえば、毎月の経営会議で使用する財務情報資料についてもテンプレートが決まっていれば、RPAによる自動入力が可能となります。
例としてWinActorを導入した立命館大学さんでは、支払手続きの確定操作をRPAに移行したことで年間25万件の定形作業が人の手から離れました。週に一度4時間かかる3000回のクリック作業を毎週行っていたのです。ひとつひとつの作業は小さくても年間を通してみれば膨大なものになります。このような業務を可視化していくことが大切です。
参照:https://winactor.com/case/educational-initiatives/5531/

RPAはほかの技術と組み合わせることによって、より高度な領域でも機能するようになります。よく組み合わされる技術にAIがあります。AIを活用した業務効率化や、AIとRPAの違いについて見ていきましょう。
AIを活用して業務自動化
総務省ではRPAを性能によって3クラスに分けており、そのクラスにはAIが密接に関わっています。
| クラス | 主な業務範囲 | 具体的な作業範囲や利用技術 |
|---|---|---|
| クラス1RPA(Robotic Process Automation) | 定型業務の自動化 | 情報取得や入力作業、検証作業などの定型的な作業 |
| クラス2EPA(Enhanced Process Automation) | 一部非定型業務の自動化 | RPAとAIの技術を用いることにより非定型作業の自動化自然言語解析、画像解析、音声解析、マシーンラーニングの技術の搭載非構造化データの読み取りや、知識ベースの活用も可能 |
| クラス3CA(Cognitive Automation) | ・高度な自律化 | プロセスの分析や改善、意思決定までを自ら自動化するとともに、意思決定ディープラーニングや自然言語処理 |
参照:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin02_04000043.html
クラス1はいわゆる一般的な『RPA』と呼ばれるクラスです。オフィスワークで行われる、データ入力などの定型業務を対象とし、決められたシナリオに沿って作業するだけなので、思考や判断の入る余地はありません。
次にクラス2の『EPA(Enhanced Process Automation)』があります。こちらは「Enhanced(強化された)」という言葉が示すように、AIを用いることによって、単純なRPAでは対応できない例外処理の発生する非定型業務を自動化します。画像や音声解析、蓄積されているデータと照会して、欲しいデータを抽出することも可能です。
最後にクラス3の『CA(Cognitive Automation)』と呼ばれるものには、高度なAIが用いられます。「Cognitive」とは認識・認知を意味し、CAは経験に基づく知識を蓄積して、業務のプロセスや結果を分析して改善策を出す仕組みを指します。ディープラーニングや自然言語処理も可能にする機能を有しています。
このように、AIを活用したRPAの業務自動化は、生産力を高める手段として国からも注目されているのです。
RPAとAIの違い
RPAとAIは組み合わせて利用されることがあるため両者を混同する方が多くいます。しかし明確な違いがあることは導入を検討する以前に覚えておかなければなりません。
RPAとは、一般的には上記で紹介したクラス1までを指します。決められたプログラムに沿って対応するのみで、自律的な判断は不可能です。イレギュラーがあればエラーを返してきます。
一方でAIとは、「Artificial Intelligence」の略称で「人工知能」の直訳で示すとおり、学習を深めることでAI自身で分析や判断ができるようになります。上の表でいうとクラス2のEPAに親しいと言えるでしょう。
過去の蓄積したデータを元に自律した判断ができます。AIをRPAに組み合わせることで単純な反復作業だけでなく、学習させて判断が必要な領域まで業務の幅を拡げることが可能になるのです。

前述している通りRPAとOCRの技術も相性が良く、しばしば組み合わせて使われていることをご紹介してきました。RPAとOCRを組み合わせることで効率化できる業務の幅が広がります。しかし、OCR自体がRPAにそもそも備わっているものではないということをしっかりと認識しておきましょう。最後になりましたがOCRとは何かRPAとの違いを理解して、最適なRPAツールを選ぶための知識を備えておきましょう。
OCRとは
OCRは「Optical Character Reader」の略で、画像の中にある文字を読み取る光学文字認識技術のことをいいます。
本来、コンピューターでは画像は画像としてのみ認識するため、中に文字があっても抽出は困難です。そのため手書きの書類や紙の文書はただの画像としてしか認識されず、書いてある内容を読み取ることができません。
OCRは画像をデータとして一旦取り込み、テキストデータへ変換する技術のことを指します。紙文化の根強い日本企業で、ペーパーレス化の促進には欠かせない技術とも言えます。
AI-OCRとの違い
OCRとRPAを組み合わせた業務効率化の活用シーンはすでにご紹介した通りです。ただし、OCRと一言で言ってもAI-OCRというAIの技術を実装しているものもあるのです。
普通のOCRとの違いとしては、「識字率が高い」「ディープラーニングによる精度向上」「非定型フォーマットへの対応」の3つが挙げられます。つまり今までのOCRでは課題であった柔軟な対応が可能になったのです。
例えば「非定型フォーマットへの対応」です。今までは予め設定した定型化された項目しか読み込めなかったのですが、AI-OCRでは項目を決めずにどのような書式でもテキスト化ができるようになりました。
また、「ディープラーニングによる精度向上」ができるという点も大きなメリットです。今までは「この文字はどうしても識別しない…」と思い通りの修正ができなかったところを学習してくれるため、利便性が高まりました。
業務のプロセスに紙が介在すると人の目と手で作業が必要でしたが、このOCR(AI-OCRも含む)とRPAの組み合わせで従来実現できなかった業務も人がいなくても可能になるのです。
RPAの技術は業務効率化、経費削減といったメリットがあり、多くの企業が導入を始めています。他の部署や部門と連携して、作業工数を減らす試みは多くの事例が存在します。
AIやOCRといった技術と組み合わせて、より幅広い領域の業務を自動化することも可能です。RPAを導入する際には、すでにある事例から自社でどの業務を自動化するのかを検討してみると良いでしょう。
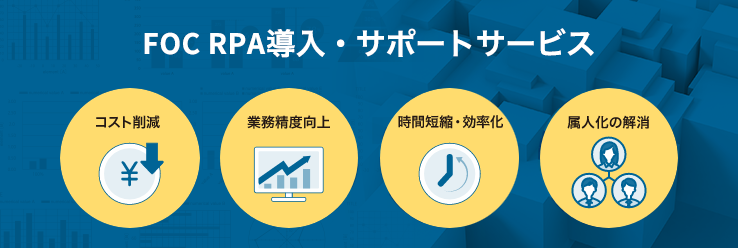
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE