くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」
MENU

RPA導入率はは大企業と比較して中小企業では進んでいないと言われています。なぜ中小企業ではRPAの導入が進んでいないのでしょうか。その理由と、中小企業におけるRPAの役割、導入するメリットを解説します。
この記事の目次

IT系リサーチ・コンサルティング会社「MM総研」の調査によれば、2019年11月時点で大企業がRPAを導入している割合は51%であるのに対し、中小企業の導入率は25%と、大企業の約半分であることがわかっています。なぜ、このような差が生まれているのでしょうか。
それについて言及する前に、まずはRPAの仕組みそのものについて見ていきましょう。
出典:https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=391
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、ホワイトカラー業務をロボットによって自動化する技術のことです。データベースへの情報の出入力や伝票の作成、勤怠管理などの定型業務を人間の代わりに行います。
そのことから「仮想労働者」(デジタルレイバー)と呼ぶこともあります。
労働人口の不足や働き方改革によって業務効率化が課題となっている企業が多い中で、日本でも導入企業数は年々増えています。
前述のMM総研の調査によれば、2019年11月時点で年商50億円以上から1000億円未満の中堅・中小企業のRPA導入率は25%であり、大企業の半分程度となっています。
しかしながら、2018年6月時点での導入率は17%だったのに対し、8%の上昇を見せ、検討中の企業の割合は2018年6月時点では33%だったのに対し、2019年11月時点では44%と11%もアップしています。このことから中小企業でも、RPAに対する注目度が年々高まっていることがうかがえます。
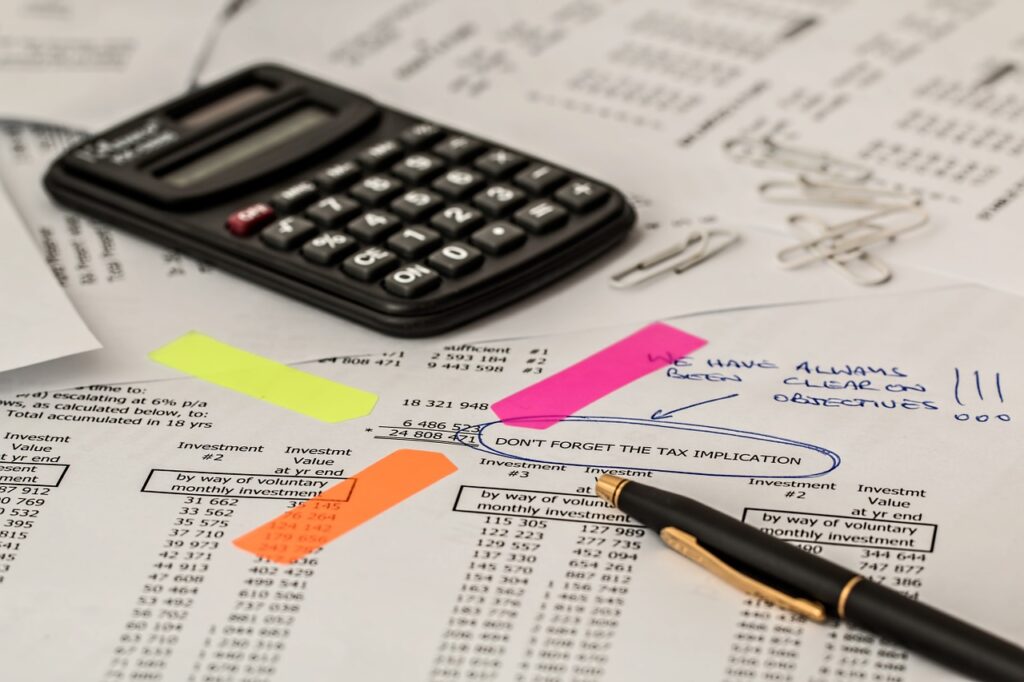
中小企業のRPA導入率が年々上昇傾向にあるとはいえ、日本の中小企業のRPA導入率はまだ高い水準とは言えません。なぜ、中小企業ではRPAの導入率が芳しくないのでしょうか。その理由を考えてみました。
RPAには年間数十万円から、高いものになると数千万円の費用が掛かるものもあります。自社の業種・業態に合わせてカスタマイズすると、より費用が高額になる可能性もあるでしょう。
大企業の場合は資金力もありますし、長期的な展望を持ってRPAを導入できますが、大企業と比べて資金力に乏しい中小企業の場合、RPAを導入・運用するだけの予算を捻出できないというケースも珍しくはありません。
また、RPAを導入するとしても、きちんとした準備期間や有料サポートを受けられなければ失敗する可能性も高くなり、工面した資金が無駄になってしまう可能性も高くなります。
こうしたリスクに対する懸念から、RPAの導入に踏み切れない企業もあります。
一例として勤怠管理を例に挙げてみましょう。RPAを活用すれば、労働者の出退勤・休日・月の総労働時間などさまざまな項目を管理することができます。
これは、社員の人数が多くなるほどに効果が高くなるでしょう。部署・部門を超えて一様に管理できるため、大人数を管理する大企業においては高い費用対効果が期待できます。
一方、中小企業はそうではありません。少人数の勤怠を管理するだけなら管理コストは少なくて済みます。業務が狭い範囲で完結するのであれば、RPAを導入する効果も薄れるでしょう。
大企業と比べて、中小企業ではRPAを導入する費用対効果に期待が持てないため、導入をためらっている企業もあるようです。
大企業であれば、社内のシステムを管理する部門があるのが一般的ですが、中小企業の場合、システム管理のためだけに一部署を設けるのが難しいことも多々あります。
こうした場合、社内サーバーやネットワークを扱う技術やリテラシーを有している社員がいないため、RPAを導入したとしてもその後の運用・保守に支障をきたしてしまうケースが見られます。
RPAを導入するためには、社内にRPAのシナリオ設計や導入を行える人材の採用・育成を並行して行う必要がありますが、中小企業の場合はそのハードルが高いため、導入に踏み切れないというケースも見られます。

中小企業においても、RPAの導入を検討している企業は増加傾向にあります。その理由はどのようなものでしょうか。RPAを導入することで生じるメリットを解説します。
RPAの中には、数万円から数十万円の運用費で始められるものもあります。無料のトライアル期間があるツールを選んで、試してから導入するのも良いでしょう。まずは1部署・1業務に対応したRPAから導入していくことで、リスクを抑えてコストを削減できる可能性が高まります。
RPAは人間が行うよりもはるかに早く作業が可能です。業務内容によっては人間数人分の作業をコンピューター1台で賄うこともできます。こうした業務遂行能力の高さから、社内のコスト削減効果を期待されています。
機械が行う計算や入力は、人間が行うよりもはるかに正確です。しかも、長時間作業を行ったからといって疲労によるミスも発生しません。
RPAの導入は経理業務や在庫管理など、人の手で管理した場合に間違いが起きやすい業務において、ヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
ミスが防げるということは、確認のためのダブルチェック人員やトラブル発生時の工数なども不要になります。将来的にミスから派生するコストや工数も削減ができるメリットと、ミスがないことによって、業務に関連する社内のメンバーや取引先からの信頼も担保できます。ミスがなくて当たり前のバックオフィス業務であるからこそ真価が発揮できることでしょう。
RPAは人間よりもはるかに速い処理能力を備えています。その上、休息も必要なく働き続けることが可能です。オフィスワークに従事する労働者数と労働時間を抑えることができ、結果として労働生産性を向上させることになります。
それだけではなく、RPAの導入によって、資料作成や管理業務に割いていた人的リソースを、商品開発や営業活動など、売上や利益に直結するコア業務に割り当てることができるようになります。
結果として商品やサービスの付加価値が高まるので、これも労働生産性の向上に寄与することができます。

RPA導入のメリットについては上述したとおりですが、これらは大企業にもあてはまる一般的なRPAの特徴です。中小企業にもスポットを当てた場合、RPAの導入によってどのような効果を得られるのでしょうか。
総務省の記事によると、2025年までに事務的業務の1/3がRPAに置き換わるインパクトがあると言われています。(※)これには、RPAが人より処理能力が高いことに加え、RPAの種類によってはパソコンのスペックに依存しないことも要因として挙げられるでしょう。
サーバー型・クラウド型のRPAは大量のデータを扱ってもサーバー内でRPAが処理するため、パソコン端末自体の処理は重くならず、事務処理をそれだけスムーズに行うことができるようになります。
※https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin02_04000043.html
中小企業の抱えている大きな懸念の一つが、人材不足です。中小企業では、大企業ほど採用や育成に掛けられるリソースがなく、即戦力が必要になってきます。
RPAの場合、最初に作業するルールを正確にプログラミングさえすれば人以上に働くことができ、明確な即戦力です。急な退職なども発生しないため、採用や育成に掛けるコストを削減することにもつながるでしょう。
RPAは1台のパソコンで数人分の作業をこなすことができるため、中小企業における人材不足解消に大きく貢献します。
RPAの導入によって、社員のストレスを軽減することもできます。
人には向き不向き、好き嫌いがあります。そのため例えば細かい数字の入力、転記作業などの細かな事務作業をストレスに感じる社員もいるでしょう。そのような社員にミスを起こさず、ひたすらの入力作業や確認を求めるのはストレスになります。
また、コミュニケーション面で伝えにくいことを、ロボットに代行させるということも可能です。ある企業では、社員が経費として申告した金額と実際の利用金額が異なっていた場合の問い合わせなどをロボットにさせています。
こうした人間同士で行えば角が立ちかねないやりとりを、ロボットに代行させることで担当者のストレスを軽減させることが可能です。

中小企業でRPAを導入する場合、大企業とは違う方法で導入を行わなければ、コストがかさんでしまいます。
現実的にRPAを運用するためにも、次のようなポイントを踏まえると良いでしょう。
RPAはオフィスワークを自動化できる便利なものですが、いきなりすべての業務・部署で導入することは現実的ではないでしょう。
高い製品を購入し、技術者を雇い入れてもさまざまな要因によって普及がままならずに運用に失敗してしまった事例は過去に多くあります。高い導入費、運営費が無駄になってしまう可能性も否めません。
そうならないために、まずは適用業務を絞って小規模で導入してみるスモールスタートが良いでしょう。そうすることで、RPAを導入する際に必要な準備や問題点が可視化され、大きな改革へのステップを踏むことができます。
スモールスタートは、あくまで試用の一環と考えましょう。会社が将来大きくなったときや事業を拡張するときに備えて、データを採取することが重要になります。
スモールスタートの低予算から始めると言っても、特に目標や期間もなく見切り発車的になるのは、得られる情報が少ないためおすすめしません。
まずは、導入する範囲や期間の決定、想定される課題や効果、それらを実際の状況と照らし合わせて検証することが重要になります。
そして、将来に人数や業務が増えたときのことを想定して、何ができるかを考慮して運用していくことが重要です。
RPAの導入を成功させるには、社内の受け入れ態勢を整えることも重要です。現場からの反発や担当者不在により、導入がうまくいかないといった事例もあります。
RPAを導入する際には、導入する現場の人間から問題点を吸収し、ヒアリングや事前の説明をきちんと行った上で、導入に踏み切ることが大切です。
また、RPAを管理・運用ができる担当者の採用や教育できる環境も整えましょう。社内にノウハウがない場合は、RPAツールのサポートを受ける、アウトソーシングを使ってノウハウを社内に取り込むといった施策を行っても良いでしょう。
社内の担当者を決定し、RPAを作成する際のルール作りをしておかないと、不要なRPAシナリオの作成によって無駄が発生してしまったり、現場が混乱してしまう可能性もあります。

RPAを導入する際には、以下の点に注意する必要があります。以下の点について対策を巡らせた上で、導入するかどうかを検討しましょう。
RPAも機械ですので、例外処理が発生した場合にエラーが起きたり、アップデート時などに思わぬ誤作動を生じたりする可能性も否めません。そうした場合にRPAに依存しすぎる組織体制、技術者がいない場合は業務が止まってしまうリスクが考えられます。
エラーや誤作動が起きる場合を考慮して技術者を採用しておく、またはRPAを提供しているベンダーとは普段から連携し、アップデートやプログラミング変更のタイミングで業務が停止しないよう、注意を払いましょう。
RPAの導入は業務効率化の手段であって、目的ではありません。導入が成功したことを最終地点とするのではなく、その後のことも考えた上での仕組み作りが大切になります。
例えば、RPAの導入によって経営陣は「作業の効率化が図れる」ことを想定し、現場では「業務負荷の軽減」が想定されていたとします。RPA導入の結果、現場の人間は定型業務が減った結果、代わりに複雑かつコアな業務が入ってきて、かえって負担が増してしまうことも考えられます。
こうなってしまっては、現場から不満の声が上がってしまいます。このように、経営陣と現場で共通の目的が持てていない場合や、RPAの導入がプロセスではなく目的となっている場合には、こうした問題がよく起こりえます。
こうならないよう、RPAを導入する目的を全社でしっかりと共有する必要があります。
RPAの導入は大企業と比べると中小企業はまだ遅れている傾向にあります。記事でもお伝えした通り、人員や予算が潤沢でないことが大きな理由です。
大企業のように人員が潤沢でしっかりと部署やチームごとに作業分担が明確であれば、RPAの導入もスムーズです。組織と分担が明確であるため、作業の切り出しが簡単だからです。反面、中堅・中小企業のように分業するほどの人員もおらず、一人ひとりがマルチタスクで広範囲を担当していることが多いでしょう。その場合、作業も案件ごとに属人的になっていたり、RPAに任せる業務の切り出しが難しくなります。少ない人員で頑張ってるからこそ、「今いる人でカバーできているから現状で満足している」「無駄に予算を出したくない」という悪循環になりがちです。
このような環境で重要になるのは、本質的な企業活動を目指し全社の舵取りができるキーパーソンの存在です。会社の成長のために、一人ひとりの生産性を向上させることを考えましょう。まずは事務にフォーカスをするなら、関わっている全員の業務全体と詳細を洗い出してみましょう。現在のコストとRPA導入運用費用を照らし合わせるだけでなく、RPAにより浮いた人材が他業務に活用できる将来的に得られるメリットもしっかり把握しておくことが重要です。
システムを取り巻く環境はここ数年で大きく変わっています。現状に満足せず、常に新たなる技術でカバーできる施策を積極的に検討してみてください。きっと、企業の成長につながることでしょう。
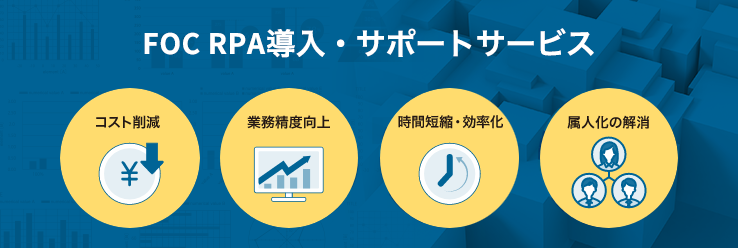
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE