パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。
MENU

RPAもAIも業務効率化やコスト削減に利用されるツールですが、両者はなにが違うのでしょうか。定義や機能の違いについて解説します。また、両者を連携させることでどのような活用が可能になるのかも合わせて見ていきましょう。

RPAとAIはどちらもともに近年注目されている技術です。ともに業務効率化やコスト削減に活用されるという共通点もあります。この2つはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの定義と違いについてまずは解説します。
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、ロボットによって主にデスクワークなどで発生する定形作業を自動化することです。
製造業を中心とするブルーカラー業務の自動化は目覚ましい進歩を遂げてきましたが、近年はホワイトカラー業務を自動化するこの技術に注目が集まっています。
RPAは人の代わりに作業を行うことから仮想知的労働者(デジタルレイバー)と呼ばれることもあります。日本では金融業界や保険業界などの大手を中心にシェアが拡がっています。
AIとは「Artificial Intelligence」の略で、日本語では「人工知能」と訳されます。
AIには厳密な定義はなく、研究者によって解釈は分かれています。そのため「コンピューターシステムによって実現する知的活動」「人を模倣するコンピューター」など、さまざまな解釈があります。
AIは限定された領域に特化した「特化型AI」、さまざまな課題に対応する「汎用型AI」という分け方と、自律的にものごとを判断する能力を備える「強いAI」、人間の一部のみを代替する「弱いAI」などといった分け方がされます。
RPAにもいくつかの分類がありますが、一般的に言われているRPAとは、業務を自動化するシステムそのものを意味し、あらかじめ組んだシナリオ(人間によって設定されたルール)に従って作業を行うものです。自らルールを分析したり、非定型業務をしたりといったことはできません。
対してAIは、データを基に分析して自らで判断を下したり、より複雑な処理に対して対応したりすることができます。RPAは独自に判断を下したり成長することはありませんが、AIはデータを蓄積することで精度をより高めていくことが可能です。

総務省によって、RPAは3クラスに分類されています。組み込むAIの種類によってそのクラスは異なります。どのように分類されるのか、それぞれのクラスを紹介しましょう。
RPAのクラス
| クラス | 主な業務範囲 | 具体的な作業範囲や利用技術 |
|---|---|---|
| クラス1RPA(Robotic Process Automation) | 定型業務の自動化 | 情報取得や入力作業、検証作業などの定型的な作業 |
| クラス2EPA(Enhanced Process Automation) | 一部非定型業務の自動化 | RPAとAIの技術を用いることにより非定型作業の自動化自然言語解析、画像解析、音声解析、マシーンラーニングの技術の搭載非構造化データの読み取りや、知識ベースの活用も可能 |
| クラス3CA(Cognitive Automation) | ・高度な自律化 | プロセスの分析や改善、意思決定までを自ら自動化するとともに、意思決定ディープラーニングや自然言語処理 |
出典:総務省
まずクラス1は、AI非搭載のクラスとなります。近年、RPAと言えばこのクラスのものを指すのが大半です。共通のルールに基づいた反復作業を業務範囲としています。
例えば、伝票の発注や勤怠管理、在庫管理などをはじめ、データの入出力などの単純業務をこなします。あらかじめ入力されているルールに基づいて業務を行うため、イレギュラーな処理や複雑な判断については、人間が処理することになります。
クラス2は「Enhanced Process Automation」と呼ばれるクラスで、EPAと略されます。このクラスでは、AIと連携することで一部の非定型業務を自動化することを可能としています。
非定型業務というのは、構造化されていないデータの識別処理や収集、分析などを指します。「Enhanced」(強化された)の言葉の通り、クラス1よりも複雑な作業をこなすことができます。
例えば、音声や画像データの解析、ログの解析、過去の売上結果に基づいた売上予測などを行うことが可能です。マシンラーニングの技術も搭載され、自らデータを基に学習することもできます。
クラス3は「Cognitive Automation」という名前で、CAと略されます。Cognitiveは「認識・認知」の意味で、単純に言えば、獲得知識の蓄積によってクラス2もさらに高度なAIを組み込み、より複雑な業務にまで対応できるようになっています。
自然言語処理、ビッグデータの分析、ディープラーニングなどを行い、データを基にした経営判断を下したり、売上や営業の分析や予想を立てることも行います。
経済状況や天候、トレンドに基づいた情報までを加えて判断を行うため、精度も高く、与えられた指示に対して自ら判断しながら仕事をこなすことも可能です。
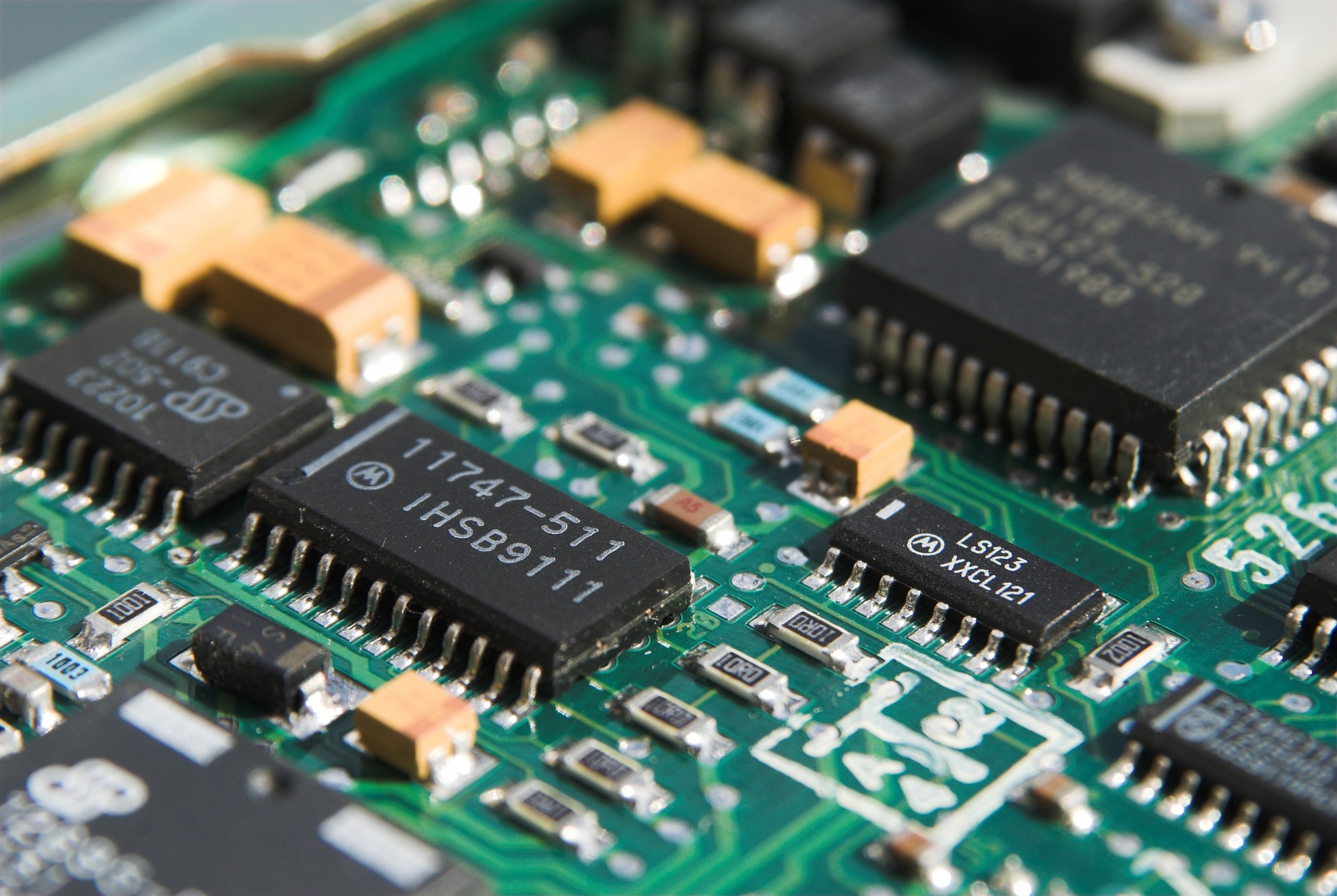
RPAとAIを組み合わせることによってどのようなメリットが生まれるのでしょうか。企業にとって分かりやすいメリットについて解説します。
クラスの部分で見てきた通り、AIと連携させることによってRPAはより高度で複雑な業務に従事できるようになります。
AIが「頭脳」として業務に対する判断を担い、その判断を基にRPAが「手足」として確実に処理を実行するというフローによって業務処理がなされるのです。
これによりRPAが担える業務の領域を拡げることが可能となります。
カスタマーサポートの業務においては、顧客ごとに、さまざまな要件を受け付けることになります。RPA単体の場合、シナリオに組み込めない部分については人間のオペレーターに一任することになります。
AIと連携することで自らの処理に基づき判断を下せるようになるため、対処できる範囲が拡がる結果、オペレーターの人数を減らして人件費を削減したり、分析に基づいて業務の改善点を洗い出したりといったことが行えます。
AIはRPAとの連携以外にもさまざまな場面で活用されていますが、ビジネスの現場ではなかなか導入されにくい理由があります。それは、AI導入よる費用削減効果や企業収益改善につながるのか、といったメリットの具体的な算出が難しいためです。
AIを導入したツールやアプリの運用は、高額になりがちです。そのため、それに見合うだけの効果が具体的に試算できなければ、導入に踏み切る判断は下しにくいでしょう。
この問題は、RPAと組み合わせることで解決を図ることができます。RPAであれば、工数や人件費の削減といった定量的観点から、費用対効果の試算がしやすいためです。どのような業務に対応できるかも明確になるので、受け入れ態勢をあらかじめ準備することもできます。
すでにRPAとAIを組み合わせたツールを導入している企業も多いため事例も豊富にあり、活用方法や効果の予測が立てやすいのも、RPAとAIを連携することで生じるメリットと言えるでしょう。

RPAとAIを組み合わせることで、実際にどのような業務に対応することができるようになるのでしょうか。具体的な活用事例を紹介します。
企業や自治体では、デジタル化への移行に伴い、紙文書の資料を電子文書に移行する作業を行っているところも多くあります。
この際、紙文書をスキャンするだけでは画像データとしてしか認識されないため、画像データの中から文字を抽出するOCR(光学文字認識)という技術が必要になります。OCR・AI・RPAを組み合わせて紙文書のデジタル化に際して、文書データとして保存するというプロセスを自動化することが可能です。
AIによって、フォントや手書きの文書を文字として認識することが可能となります。紙文書のデジタル化への移行だけでなく、例えば経費の申請や受発注の際に手書きで書かれた文書など、普段の業務で使う文書についてもデータとして保存できるようになります。
RPAは基本的に、文書を読んでその意味を理解することはできません。そのため、文字起こしや文章の要約といった作業は難しいのが現状ですが、AIと組み合わせることによってこれが可能となります。
AIによって、私たちが普段話しているような「自然言語」の処理ができるようになるためです。蓄積されたデータの中から学習し、自然な日本語としてアウトプットができるようになるので、専門的なスピーチの文字起こしや、長文の要約といった業務もできるようになります。
こうした技術はカスターマーサポートにおいて顧客から寄せられる相談や意見を理解するなど、幅広い分野で有効活用されています。
マッチングサービスにもRPAとAIは活用されています。保育園の例を挙げると、兄弟姉妹の入園や利用調整、その他の条件面のルールをAIに学習させ、入所選考をAIによってマッチングする試みを行っている自治体もあります。
これにより、保育園の職員が入園者の選考に掛ける時間を削減できるだけでなく、入園内定通知もその分早く発送できるようになるといった、保護者にとっても保育園にとってもメリットのある改善を行うことが可能です。
こうしたマッチングの面でのAIとRPAの活用は、その他には顧客ごとに最適な商品の選出や、入社時の選考などでも利用されています。
チャットボットとは、ユーザーからの問い合わせやサポート対応について、機械が自動で応対するツールのことです。
例えば郵送における再配達の時間指定や、商品に関する問い合わせなどによく使われています。
このチャットボットにRPAを組み合わせ、ユーザーからの問い合わせの対応後に、どのような問題が生じていたか、誰から問い合わせがあったのかといった情報を自動でデータベースに入力するといったことが可能になります。
さらにAIと連携することで、入力したデータを分析したり、より複雑なユーザーからの問い合わせに対しても対応できるようになります。RPAによって24時間体制でスピーディーに処理ができるとともに、聞き間違いや入力ミスの発生などを防止することができます。

RPAとともによく使われる言葉に「IoT」「BOT」などの言葉があります。それぞれの特徴や機能について把握し、RPAと使い分けましょう。
IoTは「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」と訳します。車や建物、電化製品などの本来インターネットに接続されていないモノを、インターネットを通じて相互に情報交換をする仕組みのことです。
例えば、家電に対してスマートフォンからの遠隔操作を行ったり、医療分野で患者のバイタルの情報を担当医に送信したり、最近ではカーナビの技術などにも使われたりしています。
ネットに家電を接続することでスマートスピーカーから家電が操作できるようになったり、留守宅の安全安心を見守ったりすることができるようになるなど、IoTは、現代社会に広く浸透し、欠かせない存在になりつつあります。
AIとIoTの違い
AIとは知能であり、さまざまなハードウェアに搭載されています。一方で、IoTとは、あくまでモノの方が主体となります。ネットワークを通じて情報を収集したり、モノに最新のプログラムをインターネットを介してダウンロードさせる場合などに用います。
IoTの技術だけでは、収集した情報をどう活かすかまでにはつながりません。例えば、工場のセンサーにIoTを導入し、温度や振動などの情報を蓄積したとします。このとき、それが異常であるか正常であるかの判断を下すのは、AIを用いるのが適切です。
AIとIoTは、組み合わせて使うことが各分野で研究されており、相補的な関係にあると言えるでしょう。
BOTとは、ロボットから生まれた言葉です。アプリケーションの補助、タスク処理の自動化などに用いられるプログラムのことを指します。近年ではBOTと言えば、人とのコミュニケーションを補助するツールに対して使われる言葉です。
先ほども紹介した「チャットボット」がその典型でしょう。ユーザーとのコミュニケーションを人間の代わりに機械が行うことで、人件費の削減やカスタマーサポートサービスの質の向上に貢献します。
他には話しかけるだけで操作を行うことができる「Siri」なども、BOTの一種であると言えるでしょう。
RPAもBOTも、あらかじめ入力されたプログラムに従い、人間のこなすべきタスクを自動化するという点で差異はありません。
RPAがデスクワークなどで発生する定形業務の自動化に使われる言葉であるのに対し、BOTはコミュニケーションの面で使われるという点での違いが見られますが、広義的に大きな違いはないようです。
どちらも人工知能(AI)を搭載することで、より高度で複雑なタスクをこなせるようになります。
RPAもAIも、どちらも現代のビジネスでは欠かせない存在になりつつあります。人間の行っている業務タスクを軽減し、効率化や自動化のために導入する企業は着実に増えています。
RPAとAIは、組み合わせることでより高度な業務をこなせるようになります。導入の差異にはRPAのみで可能な業務範囲か、それともAIと組み合わせることでより効率的な処理を行えるようになるかを検証し、適切に運用することで企業の発展に大きく貢献するでしょう。
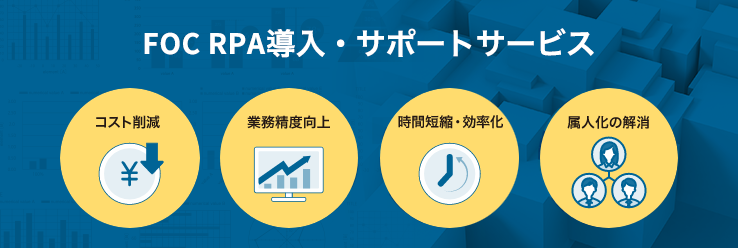
RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
パプリカ
外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE