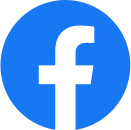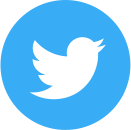プライベートな投資のため、自社より他社の財務情報に興味ある社員が潜在?
BS(賃借対照表)、PL(損益計算書)、CF(キャッシュフロー計算書)といった財務情報は財務パーソンにとって、大切で身近な存在であり、本業に大いに関わる位置にありますが、財務部以外の社員にとっては、いかがなものなのか疑問視してしまう場面はないでしょうか。
勿論、上場企業であれば、四半期ごとの財務情報が全ての人達に開示され、自社のホームページ上でも掲載するのが一般的ですが、財務部門以外の社員らの中には、プライベートな場面で株や投資信託に自身の資産を投ずる際の参考資料として、他社の財務情報については多少の興味を持っていても、肝心の自社についての財務情報は『それ程、気にしない・・・』といった本音を隠している人が少なくないかもしれません。
しかしながら、いまだに終息の兆しが見えないコロナ禍の中で、V字回復をしている企業は一部の業種であり、自社がそれに該当しないのであれば、巻き返しを図るためにも、尚一層、社員に有効な働き方を求めるのは、不可欠なはずです。
すなわち、社員一人一人がどのような仕事を成すべきか、思案し、具体的に実行してもらうためにも、自社の財務情報を参考資料として、しっかりと読み取ってもらうことは、必須でしょう。
それでは、財務パーソンとして、どのような取り組みをするのが有効なのか。
今回は、正に財務パーソンの本業に大きく関わる財務情報を社員にいかに浸透させ、有効活用していくのが相応しいか、良策を考えていきます。
お仕着せにならない取り組みが肝要!
社員に『自社の財務情報を熟読するように!』と声高に伝えたところで、浸透するケースなど稀です。
よって、社員一人一人が自ら自社の財務情報に着目して、今後の活動にどのように繋げるべきか模索し、実行するのが最良の方法でしょう。
つまり、お仕着せにならないように取り計らうことが基本・・・なのですが、筋書き通りにいかないこともあるかもしれません。
ここで、筆者から効果が期待できる方法をお送りしていきます。以下にヒントとして三点示しますので、自社に見合った方法を思案しながら、試してみてはいかがでしょうか。
◆HINT 1:財務情報の解説番組を配信する!
まずは、社員に決算情報について、出来るだけ興味を持ってもらうところから、スタートを切ってはいかがでしょうか。
長引くコロナ禍において、テレワーク・リモートワークを導入している企業も多いでしょうが、中には、『対面スタイルにはかなわない!』との理由から、徐々に出勤スタイルに戻りつつある企業も多いでしょう。
いずれにしても、昨今のコロナ影響も盛り込みながら、自社の経営事情を実感してもらうため、働き方の “オン・オフ”に関わらず、財務パーソンが、自社の財務情報を解りやすく発信することは、極めて重要なはずです。
たとえば、オンライン上でも、財務データの数値を淡々と述べるに留まらず、図表や動画も盛り込みながら、各部署や事業ごとの稼働状況がどのような影響を受け、今後、どのようなストーリー展開が予測されるのか・・・といったリアリティーある番組を作成して配信したり、少人数体制の対面形式で、同様な内容をプレゼンしたり、他の財務パーソンと意見交換をしながら、諸々工夫を凝らして進めてはいかがでしょうか。
勿論、日常業務も続けなければならないでしょうから、制作等に当てる時間を捻出すること自体が難しいかもしれません。
でも、財務部のこうした取り組みにより、他部署の社員の多くは、新鮮味を感じながら、自社の財務情報を通じて、自身の働き方を再考し、効果的な仕事を追求する期待が出来るでしょう。
すなわち、財務数値を全面に表すよりも、財務パーソンが前にでて、行動を執ること。徐々にでも、出来るところからスタートを切ってみてください。
◆HINT 2:財務パーソンの視点で見極める。⇒発信する!
次に財務パーソンの本業の方に視点を戻しましょう。
自社の財務情報を咀嚼し、人材の有効活用の面でリスクが潜在しているか否か、プロの財務パーソンとして、真摯な姿勢で読み解いてみてください。
たとえば、稼働状況が良好ではなく、営業利益率や売掛金の回収率といった財務指標も悪化しているにもかかわらず、人員体制に変化がないといった事業が継続されているなど、何かしらの疑問を感じるところはないでしょうか?
上場企業は自社の企業価値を高めて、投資家に選んでもらう経営体制を維持していく必要がありますが、昨今の未曽有な事態からの脱却が難しい日々が続くのであれば、株主への配当増も厳しいはずです。
よって、ステークホルダーでもある社員らが適材適所で仕事を進め、生産性向上を実現出来るような取り組みがされているか、不明なのであれば、潜在リスクがあるとして、上司に対して発信したり、財務部内のミーティングなどで議論したり、具体的な行動を執ることは肝要でしょう。
ハードルが少々上がりますが、ここは、財務パーソンが実務家の視点を持って、先輩や同僚とも意見交換しながら、遠慮することなく、ステップを踏んでみてください。
◆HINT 3:人事部との連携を!
筆者は、本連載で財務パーソンが他部署との連携を図ることの重要性を説いてきましたが、今回のテーマについても、外せないでしょう。
特に人的リソースの有効活用なので、人事部との連携は欠かせません。
まずは、自社の体制として、財務情報開示と人材育成ならびに人材活用について、何らかの繋がりが構築されているか否か、振り返ってみてください。
もし、なされていないのであれば、ゼロからでも、スタートを切る必要があるでしょう。
たとえば、配属先を問わず、新入社員に対し、財務データの見方・活用策関連の研修を行い、将来的に自身の実務に繋げてもらう。
或いは、各部署の部門長が月次に財務データを開示して、今後はどのような活動をするのが相応しいか、部署内のスタッフの意見をヒアリングする場を設けるなど、アイデアは、諸々出てくるのではないでしょうか。
ただ、そうは言っても、あなた一人の力では、難しいケースもあるかもしれません。
もし、懸念されるのであれば、財務部や人事部の同僚とチームを組んで企画立案したり、経営企画室に持ち込んだり、可能性の高い方法を選択して、当たってみてください。
又、こうした企画立案は、人材育成を軸にした自社の発展へと繋がることなので、反対されるケースは僅少だと考えられますが、もし、受け入れられない事例が発生したのであれば、何が足かせになっているのか、問題・課題点が浮き彫りになる契機になり得るでしょう。
あなたの行動が自社の経営スタイルの刷新に一石を投じるのです。是非、行動を興してみてください。
経営情報が発信できる上場企業ならではの良策を!
未曽有な事態は、やがて終焉を迎えるでしょうが、また近い将来、同様の出来事が絶対に起こらないといった保証はありません。
又、たとえ平穏な日々が戻ってきたとしても、自社の持続可能性について真摯に考え、どこにウェイトを置くか、どのような方向性で経営活動を進めていくか、といったスタンスは代り映えしないはずです。
よって、ステークホルダーの判断基準として大きな役割にある、財務情報を軸とした人材活性策は、シンプルな策であり、これまで述べた方法が何ら採用されていない企業が存在するのであれば、既に経営面が危うくなっているケースの方が殆どでしょう。
もし、本稿をお読みの財務パーソンの中で、自社を懸念している方がおられるのだとしたら、具体的な行動を執るのは急務でしょう。
まずは、当事者意識を持って、上司や先輩、同僚の方々に本項を情報共有するからでも、始めてみましょう。
今から、前進あるのみなのです。