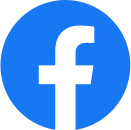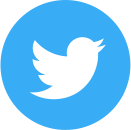国際会計基準導入の幕開け。財務パーソンの役どころを見つめ直す
いよいよ自社にもIFRS導入!こんな大イベントが訪れるとなると、大元の会計ルールのみならず、諸々の社内システムや外部のステークホルダーらに向けたIR情報の内容についても大がかりな変化が生じるはずです。こうした変化にともない財務パーソンにも様々な役どころが求められているでしょうが、なかなか教科書どおりには進まないのでは・・・と感じている方も少なくないのではないでしょうか。
今回はこうした立場に置かれた方々のために、IFRS導入をテーマに財務パーソンが具体的にどのような役回りをすれば、財務部門のみならず各セクションにとってもスムースな仕事運びが可能になり、ひいては各ステークホルダーらにも貢献が出来るのか、考えていきます。
既に切磋琢磨しながら、舵を切っている方もおられるでしょうが、本項も参考にしながら取り入れてはいかがでしょうか。
IFRSの特徴。基本中の基本
本項をお読みの方々であれば、IFRSの特徴など既に心身に刷り込まれているところでしょうが、まずはおさらいがてら、確認してみましょう。以下の5点にまとめてみました。
1、原則主義
日本の会計基準は細則主義を採用しています。従って諸々の指針や税法が詳細な規定を設けているので、これらに則って実務に当たるようなスタイルで特に支障はありませんでした。その一方で、IFRSは原則主義を採用しているので、詳細な実務指針は設けられていません。すなわち、事例に応じて担当者が都度判断しなければならないため、会計・財務のジャンルのみならず、自社の業種の動向や社会的にどのような位置にあるのかなど、幅広い視野での情報収集や知識習得が求められるでしょう。
2、演繹的アプローチ
演繹法・帰納法など、高校時代に習って以来、馴染みのないワードと思われている方もいるかもしれませんが、前者は『〇〇だから、△△である』といったように、どちらかと言えば普遍的な論理で結論づける方法で、後者は複数の事例の中から妥当なものを選んで結論づける方法を指します。日本の会計基準は後者の“帰納的アプローチ”が採用され、実務の中で既に慣習化されたものの中から妥当なものを選択する方法を採用しています。
ところが、IFRSが導入されれば、前者“演繹的アプローチ”が採用されるため、あらかじめ自社の財務諸表について、“こうあるべき!”といった姿を定めた上で、個々の会計基準を設定して実務を進めます。
つまりIFRS導入後はあらかじめ財務処理の方向性が決められているため、実務者が会計処理について悩むシーンが減るので、効率性が高まるとも言われています。
3、資産・負債アプローチ
ご存知のように日本の企業の多くは、期間損益が表れている損益計算書上の数値を重視してきました。このところ話題になった“PL脳”は、ここから生じているとの説もあります。
しかしながらIFRS導入後は、期首と期末の資本の変動を表す包括利益が重視されると共に公正価値による測定が基本となります。これまでPL上の数値を中心に経営判断してきた企業は、自ずとBSにも注視せざるを得なくなるでしょう。
4、実質優先主義
IFRS導入後は法的な形式よりも、経済的な実質を優先して企業の経営的実態を明らかにします。よって、“1”と同様に会計に関する法規に詳しいばかりでは、実務担当者としてはNGです。
自社の財務内容についてシビアに客観視して、世の中の経済状況と照らし合わせての価値判断できるか否かが問われるでしょう。
5、経済的単一体説
連結財務諸表を作成するにあたり、日本では親会社の株主の観点から財務諸表を作成する「親会社説」を採用してきましたが、IFRS導入後は、企業集団全体の観点から「経済的単一体説」が採用されるため、単体よりも連結財務諸表が重視されます。
もしも、子会社等の会計基準や決算期が異なるのであれば、統一を図らなければならないため、特に本部の財務会計の実務部隊に属する方は、子会社等へ細部にわたる支援に当たるなどのサポートが必要になることもあるでしょう。
現場と上層部のパイプ役として、財務スタッフならではの役どころに当たる!
IFRS導入を迎えるために、自社の経営陣らは導入の意図や今後の期待、そして何がどのように変わるのか、社員らに対し、諸々の説明を尽くし、プロジェクトチームを主導して準備を進めてきたはずです。
しかしながら、いくら“自社”と一口に言っても、個々の人で構成された集団です。すなわち、機械的な導入処理など出来るはずがないため、いくら経営陣らが説明責任を果たしたとしても、現場の社員に戸惑いが生じたり、実務がやりづらくなったり、諸々の負の影響が表れることも充分にあり得るでしょう。
こうした中で、財務スタッフは、受け身になることなく、現場と上層部のパイプ役として臨むことで、より良い体制を築けるはずです。
それでは、お勧めしたい具体的な内容を以下3点にまとめてみました。
Ⅰ、経理部との深い連携は必須!
自社内において財務部と経理部がそれぞれ分割して機能を有していたのであれば、これまで会計の専門知識については、経理部員のみが備えていれば支障がなかったところも多かったでしょう。しかしながら、IFRSが導入されれば、収益認識や減価償却などの方法が変わるばかりではなく、前述した“1”の原則主義により、導入前とは類の異なる判断が下され、会計処理される場合も充分にあり得ます。
よって、財務パーソンも、ある程度の会計知識を身につけて、経理部との連携を深めることが不可欠です。導入前と比較して財務数値がどのように変わるのか事前予測しながら、そして、各ステークホルダーらにどのようにアプローチすべきか、入念に思考・判断しなければならないこともあるでしょう。
もしも、財務パーソンのあなたに情報が届きにくい体制なのであれば、担当実務にも支障が出るはずです。あなたから上司に対して声を出して情報を得るようにしたり、経理部、財務部のスタッフも含めた双方の情報交換会の開催を提案したり、具体的な行動をとる必要があるでしょう。
Ⅱ、IFRS導入を契機ととらえ、データ管理・情報取集方法を見直す
IFRS導入による会計処理変更にともない、財務パーソンのあなたが日々分析・処理していたデータについても見直しが必要なのは言うまでもないでしょう。たとえば、導入後は財務データの中で何を注視・分析していくのか方向性を変える必要があるか否か検討したり、財務諸表上の注記が格段に増えるため、投資家に向けて良きアプローチとなり得るよう、有効な情報をどのように収集するか工夫したり、財務パーソンの実務そのものの刷新が迫られます。まずはあなたが担う職務については、自身が検討して具体案を策定した上で上司に提示しましょう。
又、筆者が更にお勧めしたいのは、より良い体制を築くことです。前述した“5”の『経済的単一体節』のとおり、投資家らが自社の連結決算書をこれまで以上に注視するようになれば、各セクション、子会社等の関係者の方との連携強化が不可欠です。もしも、これまで、データが締め切り日に届かなかったため、集計や分析が困難だった、あるいは財務部内の役割分担が上手く機能していなかった等の課題・問題点が潜んでいたら、クリアしなければならないでしょう。財務・経理部員らと実情を共有し、上司にも働きかけながらの改善行動を図る必要があるはずです。
IFRS導入を契機ととらえ、実務目線での対応に臨みましょう。
Ⅲ、各セクションのオペレーション確認
導入後は各現場も大きな変化が訪れます。たとえば収益認識が検収基準に変われば、売上計上や請求書発行のタイミングにも影響するので、営業部は顧客に対してアナウンスが必要になるでしょうし、あるいは、固定資産の減価償却方法等が変われば、管理する側の製造部・総務部が固定資産の選定方法や管理システムの変更を検討するかもしれません。他にも、有給休暇の未消化分は負債科目計上するため、人事部側も社員らの労務管理の手法を見直すなど、影響を受けないセクションのほうが僅少のはずです。
こうした中で各々のセクションにおけるオペレーションが良好に進んでいるのか否か、財務パーソンが現場の実情をすくい、何かしらの課題・問題点が生じていれば、あなたの上司を介してしかるべき上層部に情報を共有し、改善を求めるなど、ここでも“パイプ役”としての出番が期待されるところです。
IFRS導入のために、各セクションの機能性が悪くなれば本末転倒です。これまで、デスク上で職務に当たることが主流であったのであれば、各セクションにも視野を広め、行動的な職務にシフトしていきましょう。
財務パーソンとしても“国際基準”以上に!
既に身に染みて感じている方も多いでしょうが、本項で説いたようにIFRS導入前と導入直後は、変更事項に沿いながら、広い視野を持って、職務に当たらなければなりません。また、2019年1月にはIFRS第16号が発効され、リース契約の変更が盛り込まれました。
このように新基準についての情報を都度つかんで、実務への影響を考えて対策を練ることも求められるため、これまで以上に財務パーソンの力量が問われるでしょう。
ただ、何よりIFRS導入のメリットは、世界中の資本市場で資金調達が可能になる点です。よってメリットを最大限に活用するため、投資家にアピールできるよう、企業価値をより高める職務について優先してあたる必要があります。そのためにはこれまでの職務内容を冷静に見直し、必要性の低いものは省いたり、他のセクションに移行できそうなものは分担を提案したりといったセルフマネジメントが必要です。
これまでの記述を参考にされ、あなたなりの職務に尽力すれば、会計基準のみならず、財務の役割の面でも“国際基準”以上になり得るのです。
参考文献
・IFRS国際会計基準の基礎 第3版 (中央経済社)
・図解雑学よくわかる〈国際会計基準〉IFRS (ナツメ社)