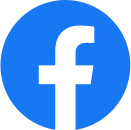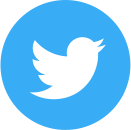前回のコラムでは、「タコつぼ化」した組織の改善方法のひとつである「組織横断での問題点の抽出と共有」を書きました。今回は、「組織横断でのプロセス定義」についてご説明します。
「組織横断でのプロセス定義」は、「組織横断での問題点の抽出と共有」で問題が見つけられない場合に有効になります。
「組織横断でのプロセス定義」では、仕事の上流から下流までどの部署がどのような仕事をして、各部署と連携していくべきであるのかを明らかにすることです。
手順は、
- 現状プロセスの確認
- 問題点の整理
- 解決策の検討と新プロセスの定義
です。
順番に見ていきましょう。
01.仕事の現状プロセスの確認
はじめに、各部署が集まって仕事の流れを確認していきます。実際に私が行った事例をお話ししましょう。建材を作っている会社の事例です。
建材メーカーX社では、営業部の問題として、出荷時に在庫があるのに出荷ができないということが懸案になっていました。一方、物流では在庫が多すぎてスペースがどんどん増え、倉庫の賃借料が高くなり、動かない在庫の廃棄も増えている問題を抱えていました。
主な原因は、営業が在庫を確保してしまい、出荷できなくしていたことです。この会社では、確保された在庫を「保留」在庫と呼びます。「では、在庫を保留できなくしてしまおう」との解決案が物流部から示されましたが、今度は営業から不満が続出です。
そこで、何が起きているのか確認してみました。すると、営業はお客様からかなり長い納期の注文を受けていることが分かりました。3か月先の出荷のための注文をもらう場合もあるのです。かなり先の出荷でも、今の仕事のやり方では、受注登録すると在庫が引き当てられてしまいます。営業としては、そんなに早く出荷されても困るので、出荷を「保留」するのです。「保留」在庫の誕生です。
こうなると、「保留」が解除されるまで、その在庫は動かすことができなくなります。別のお客様が注文をしてきて物理的に在庫があっても、その在庫は使うことができず、出荷ができないのです。
ある営業マンが、他の営業マンが押さえた保留在庫を出荷したいと思い、どの営業マンが押さえているのか確認しようとしても、そのすべがありません。そこで、物流部門に聞いたり、他の営業マンに聞いたりして突き止め、交渉に入るのです。営業マンもだいぶ納期が先とはいえ、注文をいただいたお客様の在庫は手放したくありません。営業マン同士の交渉はもめ、大問題化してから上司が解決に乗り出します。

一方、生産部門は知らないふり。計画に基づいて粛々と生産をこなすだけです。在庫がなくて困っている営業が、いつ出荷できるのかを必死に聞いてきますが、窓口の生産管理部は生産進捗が分からず、製造現場に問い合わせて初めてわかります。しかも、製造現場が勝手にまとめて製造したり(いわゆる「だんご生産」)するので、生産計画もかなりの頻度で変わり、そのたびに出荷の回答が変更されてしまいます。営業マンも安心して生産上がりを待っていられず、生産管理には毎日納期確認と督促の電話とメールをします。生産管理も不満が溜まっていました。
このように、仕事の一連のプロセスをまとめただけでも多くの問題が見つかりました。次はこれを整理していきます。
02.問題点の整理を組織横断で行う
最初の在庫を“保留”できないようにするという案は短絡的で解決策になりませんでした。対処療法ではだめなので、仕事の流れを洗い出し、組織横断で根本的な問題を抽出し、原因を探ります。その結果、以下の問題点を抽出しました。
- 受注はどれほど先の納期でも登録できる
- 受注登録のタイミングで、今ある在庫しか引当できない
- 生産管理の指示を無視して製造現場が生産計画を変えてしまう
- 営業マンが在庫を自由に「保留」でき、誰もチェックしていない
- だれが保留しているのかわからないので調整が困難
など。
こうしたことが明らかになったので、対応策を考えます。そのために各部門から人が集まって、組織を横断した業務の流れの中でどう解決していけばよいのかを検討します。
03.解決策の検討と新プロセスの定義
そもそも論からすると、受注即在庫引当しかできないことが問題視されました。先の納期でも「今の在庫」を引き当てていては在庫がいくらあっても足りません。そこで、生産計画を引き当てることを可能にしました。これで、納期に合わせて引当ができるので、今の在庫を「保留」にする必要がなくなりました。
生産計画も事情により変更されますが、先2週間は絶対に変更しないことがルール化され、生産計画の引き当てもルール化しました。
また、どれほど先の注文であっても受注可能という件ですが、こちらは変更しませんでした。対お客様への影響を考えると、変えるべきでないとの結論に達したのです。あとは、受注⇒在庫だけではなく生産計画引当⇒出荷のプロセスも可能にして、システムも変更しました。

対処療法の「保留」禁止は、実ビジネスにそぐわない解決策でしたが、組織を横断してルールを変えることでお客様との関係も壊さずに合理的な解決策に到達できたのです。
多くの場合、各部門で問題解決をしようとすると、タコつぼ化した対処療法しか思いつかないことが多く、結果的に問題が解決しないことが頻繁にあります。そのような対処療法ではなく、今回の事例のように、組織横断で企業競争力を維持・強化できる解決策を描くべきなのです。
簡単なように見えたかもしれません。しかしこのように解決策を考えたり、実際に解決策を実行することはとても難しいのです。なぜ難しいのか。そして、どうすれば意味のある有効な解決策が考えつき、実行していけるのか、次回明らかにしましょう。