湯瀬 良子
DC運用・ブログ担当
金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」
MENU


DC(確定拠出年金)に改めて注目が集まっている昨今、DC制度への理解は進んできたように思われますが、その具体的な中身についてはどうでしょうか?
今回は、よく似ているからこそ違いを知ってほしい二つの制度を見比べてみたいと思います。
この記事の目次
そもそも企業型DC制度は「企業年金制度」の一つであるため、掛金は事業主が拠出する「事業主掛金」として法令上に明記されています。
つまり、「会社が退職金制度の一環として企業型DC制度を導入」し、「会社負担で掛金を拠出する制度」でありながら、「掛金の運用は加入者自身が行う」というところが積極的な運用に繋がりにくいという側面を表しています。
では、加入者が自主的に確定拠出年金制度を活用するためには、どのような制度を設計したら良いのでしょうか?
まずは、加入者の自助努力として掛金を上乗せ拠出できるように法令で整備された「加入者掛金」いわゆるマッチング拠出です。
そしてもう一つが、総人件費の見直しという観点で、「給与の一部を前払退職金として再定義し、従来どおり給与支給の際に現金で受取るか、企業型DCに拠出するかを従業員が選択できる」ように設計した制度「選択制DC」であり、従業員が選択するDC掛金は「事業主掛金」ということになります。
根本的に違う制度でありながら、非常によく似たしくみであることから混乱が生じやすいものとなっていますので、それぞれのポイントについて整理してみたいと思います。
マッチング拠出には以下のようなポイントがあります。
1.事業主掛金に加えて、加入者本人も掛金を拠出できる
2.加入者掛金は給与天引きで拠出され、全額所得控除の対象となる
3.加入者掛金の変更は、年1回行うことができる
それぞれのポイントについて、加入者目線で見たメリット・デメリットを見ていきましょう。
1.事業主掛金に加えて、加入者本人も掛金を拠出できる
メリット:企業年金でありながら、加入者も掛金を拠出し、定年退職後の資産形成が図れる。
デメリット:事業主掛金が少額の場合には、加入者掛金も少額しか拠出ができない。
加入者掛金については、以下の二つの条件を満たす必要があるため、例えば事業主掛金が5,000円の場合には、加入者掛金も5,000円までしか拠出できず、法定の限度額までの枠が使い切れないということになります。
①事業主掛金との合計額が法定の拠出限度額(※)以下
②加入者掛金は事業主掛金と同額以下
(※)拠出限度額:厚生年金基金等、他の企業年金がない場合は月額5.5万円(年額66万円)
厚生年金基金等、他の企業年金がある場合は月額2.75万円(年額33万円)
2.加入者掛金は給与天引きで拠出され、全額所得控除の対象となる
メリット:全額所得控除の対象となるため所得税・住民税が軽減できる。
デメリット:退職時に2ヶ月分の掛金が控除される場合がある。
会社が拠出している確定拠出年金口座に、事業主掛金とあわせて加入者掛金を拠出するため、会社側で給与控除(天引き)を行ったうえで、合計額を拠出することになります。
その際、加入者掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります(企業規模に関わらず対象となります)。
なお、加入者掛金は前月分の掛金額を当月の給与から控除する必要があるため、退職月分の加入者掛金額を当月の給与で控除する場合は、2ヶ月分の掛金額が控除されることになります。
3.加入者掛金の変更は、年1回行うことができる
メリット:ライフプランにあわせて柔軟に資産形成に取り組める。
デメリット:事業主掛金同様、原則60歳まで中途引き出しができない(将来的に65歳に引き上げられる可能性があります)。
加入者掛金の額については、定額で複数の選択肢を設定する必要があり、金額の変更は「年1回に限り」認められています。
ただし、以下の場合には「年1回の変更」とみなされないため、随時(毎月)変更することができます。
①事業主掛金の額が引き下げられることにより、事業主掛金額が加入者掛金の額を下回る場合
②事業主掛金の額が引き上げられることにより、拠出合計額が法定上限を超過する場合
③加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、加入者掛金の額を拠出できなくなる場合
④加入者掛金の額を0円に変更する場合
前述のとおり、事業主掛金の額によって、従業員の拠出できる金額に差が出てくる制度です。
一定額以上の事業主掛金拠出を行わない場合には、従業員が拠出したい額まで拠出ができず、運用機会の損失にもつながりかねません。
また、社保削減等の副次効果がないため、導入後の制度運営が積極的に機能せず利用率が高まらないという側面もありますので、従業員への周知が非常に重要になることも抑えておく必要があります。
選択制DCには以下のようなポイントがあります。
1.加入(拠出)するかしないかは本人の自由意思
2.DC掛金として拠出する金額は、全額非課税
3.金額変更は、自由に行うことができる
それぞれのポイントについて、加入者目線で見たメリット・デメリットを見ていきましょう。
1.加入(拠出)するかしないかは従業員の自由意思
メリット:従業員の自由意思のため、強制感がない。
デメリット:特になし。
選択制DCとして導入する場合には、従業員本人が加入するかしないかを選択するため、強制的に掛金を拠出するわけではありません。
このため、導入する会社としても強制感がなく、従業員の理解が得られやすいという利点があります。
全員拠出+選択制DCとして設計する場合でも、選択制DC部分は任意のため、希望者のみ掛金を増額できることになります。
2.DC掛金として拠出する金額は、全額非課税
・加入しない場合
メリット:給与水準が変わらない。
デメリット:課税される(導入前から変更なし)。
・加入する場合
メリット:所得税・住民税が軽減できる。
デメリット:給与の支給水準が減る。
選択制DCの場合は、給与の一部を原資として退職金に再定義したうえでDC掛金として拠出できるようにしているため、DC掛金として拠出する金額は「そもそも給与とはみなされていない」金額となります。
このため、DC掛金として拠出する金額の分だけ給与の支給水準が減る反面、DC掛金は全額非課税で拠出することができるため、税負担を軽減しながら定年退職後の資産を形成できるとともに、拠出額によっては社会保険料の負担も軽減することができます。
ただし、社会保険料の負担が減る場合には、将来の老齢厚生年金の給付が減少する可能性もあるため、事前にシミュレーション等で確認しておく必要があります。
3.金額変更は、自由に行うことができる
メリット:マッチング拠出同様、ライフプランにあわせて柔軟に資産形成に取り組める。
デメリット:選択制DCのみで全員拠出分がない場合、0円に変更することはできない。
事業主掛金額の変更については、制限なく毎月変更することができます。
しかしながら、選択制DCの場合は「本人が金額を選択」するため、事務負荷を考慮し実態としては年に1から2回変更機会を設ける場合が多く見受けられます。
少なくとも毎年1度は金額を見直せる反面、自己判断で0円にはできず最低金額と言われている3,000円は拠出を継続する必要があるため、その点がマッチング拠出とは異なります。
前述のとおり、選択制DCは給与の一部を「前払退職金」として再定義するため、給与の枠組みを変更する必要が出てきます。
給与について定めた規程の変更や給与システムの変更等、導入前に対応しておくべきことが多岐に亘るため、必ずしもスムーズな導入が行えるわけではありません。
しかしながら、選択制DCは従業員への福利厚生の充実という観点からも導入企業が増えている制度設計ですので、一つの選択肢として考えておくべきものと言えます。
社保削減の副次効果もあり、相対的に加入率は高くなりやすいため、労使双方にとって効果的な年金制度であると言えるかと思います。
以上のように、それぞれの制度にメリット・デメリットがあります。
どちらの制度を導入するのが自社にとって適しているのかを検討する際には、以下のどちらの考えに近いのかを確認していただくと判断しやすくなります。
●会社が負担する掛金を、法定の拠出限度額に対して半分 (他の企業年金がない場合であれば、月額2.75万円)以上は拠出しようと考えている。
加入者掛金の条件の一つ「事業主掛金以下」を考えても、法定の拠出限度額までの拠出が可能なため、マッチング拠出の導入を検討いただくと良いかと思います。
●会社が負担する掛金は、それほど高い金額ではない、あるいは会社の負担は最低限にしたいと考えている
マッチング拠出では、法定の拠出限度額まで拠出できない可能性が高いため、選択制DCの導入を検討いただくと良いかと思います。
なお、会社で財源を捻出できないかもしれないと不安に思われる場合は、まずは福利厚生の拡充という観点から選択制DCを導入し、数年後に会社から全従業員に対して拠出を行うという制度変更をご検討ください。制度の設計は柔軟に行えるものですので、従業員へのCS向上の観点からもまずは選択制DCの導入をご検討いただければと思います。
企業型DCに関するよくある質問はコチラ☟
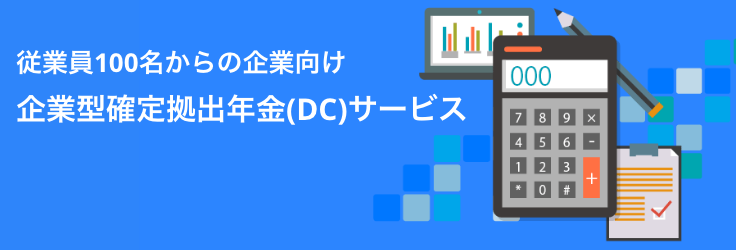
FOCのDCサービスは、企業と従業員の双方にとって、本当に有用なDC制度の導入を支援するサービスです。さらに、導入前の書類整備から導入後の継続教育までをトータルサポートする、ベストパートナーを目指しています。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
湯瀬 良子
DC運用・ブログ担当
金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE