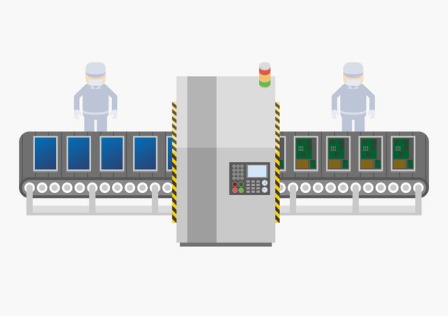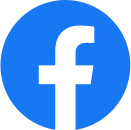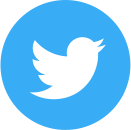前回のブログ記事では、組織横断での問題解決を指向してもなかなかうまくいかないということを最後に申し上げました。その原因は、以下の二つです。
- 個別最適化を推し進める評価制度
- 専門特化した昇進・教育体制による組織への無知
これは、既に述べた大きな問題点の二つでもあります。組織横断で新しいプロセスを定義しようとしても上記、個別最適化を推し進める評価制度と専門特化した昇進・教育体制による組織への無知が邪魔をします。
それでは、1. 個別最適を推し進める評価制度とその解決策ついて説明します。
個別最適を推し進める評価制度が企業全体を崩壊させる
企業は組織で運営されます。企業そのものの評価、その企業の経営の良否は主に企業の財務成績で評価されます。売上の成長、利益率、配当の多寡、借金の多寡、在庫の多寡などで、企業一体で評価されます。
しかし、企業を構成する各組織はどう評価されるでしょうか。一般的に言えば、組織単位で評価されます。たとえば、営業部門は売上の向上です。製造(工場)部門はコスト(原価)低減、物流部門は物流コスト低減です。在庫はどこにあるかで評価先が分かれますが、どこにあるにせよ、在庫の管理部門が求められるのが、在庫削減です。
高度経済成長期という経済の拡大期で、作れば売れる時代の管理は単純でした。作れば売れるので、出来上がった組織に対し、個別に評価項目を設定し、それぞれの評価で良かったのです。各組織の頑張りの足し算が、そのまま企業の成績に直結していました。
営業は売上さえあげれば良し。製造は少ない品種を大量生産するので、ひたすら効率化だけしていれば良し。物流は、大量に運ぶのでトラックの積載を増やし物流コストを下げるだけでよかったのです。
各組織が、組織単位で頑張って、その効果の足し算が企業の成績に直結していました。個別組織は、個別に設定された評価に向かって頑張れば、その足し算が企業の業績になった単純な時代でした。
しかし、時代は変わりました。作れば売れる時代は終焉し、少量多品種の販売・生産の世の中になりました。顧客のニーズも高度化し、今まで通りの売り方では売れなくなりました。つまり、効率よく大量に作って、大量に運んで、大量に売れれば、利益が出る時代ではなくなったのです。こうなると、生産効率を求めすぎると過剰在庫になり、在庫低減を言い過ぎると工場稼働が落ちて高コスト化するなど、どこかの部署の最適化が全体の最適化に結び付かない時代になったのです。
このように、組織単位の目標が達成されても、企業としての目標達成に貢献しない状況が発生し始めています。時代が変わったにも関わらず、相変わらず組織単位の評価が強固に生き残って、企業全体の儲けよりも個別組織の目標達成が優先されているのです。
なぜ、個別組織の目標達成が優先されるのでしょうか?それは、組織評価が自分の人事評価に直結するからです。自部門の目標達成を最優先するため、他部門の活動が邪魔になり、そのうち部門間の言い争いが始まるのです。
営業部門は工場がきちんと生産すれば良いから黙って言われたとおりに作れと言い、製造部門は営業がころころ要求を変えるからまともに生産ができないと言います。物流部門は、もっと輸送をまとめてくれと要求し、営業部門は顧客の要求だから無理だの一点張り。
こうして、企業は個別組織でばらばらに解体されていき、企業が一体で改革などできなくなっていくのです。
個別組織単位に設定された目標値が、企業の競争力を阻害する原因になっていることは多々あります。仮に、全社的な改革プロジェクトが出来上がって、部門横断で業務設計を行っても、問題の解決案が個別組織の目標達成を阻害するようなときには、部門の協力は得られず、部門間の対立をさらにひどくする場合があるのです。
個別最適を推し進める組織個別の評価制度が企業全体を崩壊させる事態とは、このようなことを言います。いわゆる「個別最適・全体崩壊」は日本中、世界中で発生しています。
企業体としての評価制度設定の必要性を実現するバランススコアカード
企業体として設定すべき目標は、企業全体の最適化を実現できる方法で設定しなければならないのです。

個別組織単位で目標値設定をやめ、全社目標から個別組織への目標を分解し、かつ全体に貢献するように整合させる必要があります。この手法として注目されるのがバランススコアカード(以下、BSC)です。
BSCは、財務の視点、顧客の視点、プロセスの視点、教育の視点で企業として実現すべき目標の関連を読み解き、各組織の目標値を関連させて設定することができる手法です。
BSCの手法を使って目標値を作る方法は組織横断の目標設定には有効な方法です。
営業部門から生産・物流部門をつないだ評価と計画を実現するPSI計画/S&OP
もうひとつ、営業部門から生産・物流部門をつないだ月次単位での評価ルーチンとしてサプライチェーンマネジメントを行う業務プロセスの導入があります。
それが、国内で言われるところの「生販在計画・仕販在計画と言われるPSI(P:Prpduction、S:Sales、I:Inventory)計画」、国外では「S&OP(Sales& Operation Plan)」です。
PSI計画またはS&OPは同じものと考えて構いません。月次で組織横断的に売上から生産・調達・物流までの活動結果を評価し、再計画を行い、目標値を組織横断的に再検証して、もっともフレキシブルでリスク対応的に計画を練り直してアクションすることで企業体としての意思決定を指向します。
BSC、PSI計画またはS&OPは、個別企業にタコつぼ化した評価に風穴をあける手法です。次回から2回にわたってそれぞれの枠組みを説明していきましょう。
■企業の目標と組織単位の目標の乖離例
石川氏の経験をもとにした「目標がずれていく例」を最後にご紹介します。
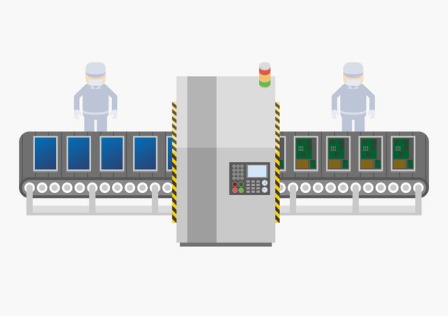
少量多品種でモノが簡単に売れない時代への変化に適応できない企業の中で起きていることは次のようなことです。
たとえば、営業が売上を上げるために、少量多品種の生産要求をかけているとします。工場は、品種が変わる都度機械のセットアップをし直したり、急な残業や手待ちが発生したりすることに耐える仕組みが必要になります。こうなると、生産の安定化は無理です。
しかし、工場は工場でコストダウンを要求されるため、残業規制に入って納期遅れになったり、安定生産にして稼働率を稼ぐために要求されない製品を作ったりします。余計な在庫が増えるのです。
物流は物流で、積載効率を上げるために、要らない製品まで積みこんで輸送しようとします。トラックが満載にならないようであればトラック便を減らして物流コストダウンを行います。こうなると要らないものを運ぶので、倉庫で過剰在庫が起きたり、便が減らされて荷物がこないため欠品したり、不都合が生じます。
製造や物流の都合で生じた在庫は滞留により、資金繰りに影響が出ます。廃棄が生じれば損失、納期遅れや欠品による売り逃しは売上そのものの達成に影響します。