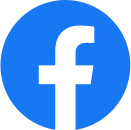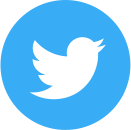バランススコアカード(BSC)とは
個別組織単位で目標値設定をやめ、全社的な視点にたって、全社の目標から個別組織への目標を分解し、かつ全体に貢献するように整合させる手法があります。この手法として注目されるのがバランススコアカード(以下BSC)です。
実は、日本でも従来から似たような手法がありました。TQC(トータル品質管理Total Quality Control)です。TQCは個別製品の品質や工程の品質改善手法を拡大して、全社的な目標設定を行い、その実現方法を課題として立案する手法です。
私も、かつて日系のコンサルティング会社にいたときは、TQCのコンサルティングを行っていました。通常は業務品質目標の設定、つまり、リードタイムの削減とかコストダウンなどが掲げられますが、私たちは財務目標の設定から目標展開をしていました。具体的に言うと、在庫月数の低減を全社目標にして、在庫月数を削減するために、各組織の目標に展開し、施策を考えたりしました。利益を目標にした時もありました。財務目標を作業(業務プロセス)上の目標にまで展開し、良品率の向上、作業時間の短縮、などに紐付けて行きました。
その後、アメリカからBSCというフレームワークが持ち込まれました。BSCは、ロバート・S・キャプランとデビッド・ノートンが開発した業績評価システムです。BSCは従来の財務的指標中心の業績管理手法の欠点を補うもので、戦略・ビジョンを財務の視点・顧客の視点・業務プロセスの視点・学習と成長の視点という4点で展開し、戦略やビジョンと連動して目標展開し、財務目標ならびに非財務的目標を設定するものです。
なぜBSCが個別組織にタコつぼ化した評価に風穴をあけるのか

なぜBSCが個別組織にタコつぼ化した評価に風穴をあけるかというと、財務目標という全社の目標から、顧客に対する指標を展開し、その顧客に対する指標を業務プロセスの視点で考え直すからです。すなわち、財務や顧客が視野に入ってくると、各組織は組織だけの目標設定や課題設定ではすまなくなってくるからです。
たとえば、「売上を10%上げる」という財務目標を持ったとします。そのためには、たとえば、競合企業に比べて競争力のない自社の顧客への「納品リードタイムを半減する」という顧客対応の目標を設定するでしょう。
「納品リードタイムを半減する」ためには営業部門だけが頑張ってもできません。営業部門単独でなく、物流部門や製造部門などが連携して頑張らないとできないのです。つまり、組織横断的に、財務目標や顧客目標に貢献するための目標設定を課題対策が必要になるわけです。
通常の場合、タコつぼ化した企業で良く起きる例で考えてみましょう。「納品リードタイムを半減する」という顧客に対する目標を会社として設定したときに、物流部門が物流部門の視点だけで「物流コストの半減」を目標設定したとします。
目標達成のための課題施策が今までの日に2回の輸送をやめ、「輸送は日に1回に削減し、そのかわり大型トラックで運んで輸送効率を上げる」だったとしましょう。こうなると、今までは半日に1回荷物が届いたのに、今後は日に1回しか届かなくなり、顧客にとっての物流リードタイムが半日から1日へと延びて、悪化することになるのです。これでは、物流部門の効率は上がるでしょうが、顧客サービスレベルが落ち、「納品リードタイムを半減する」という目標に反するのです。
BSCで目標展開し、各組織の業務プロセスの目標が整合して作られていれば、このような不整合は起きません。この例では、「納品リードタイムを半減する」ために、物流組織のコストダウンではなく、たとえば、より小口で多頻度配送するというのが目標になっていきます。さらに言えば、企業は物流部門に対し、年中行事のようなコストダウンを要求するのではなく、思い切った投資と業務改革を要求することになるでしょう。企業全体で考えれば、全体の目標達成のために、一部の組織の効率が落ちたり、資金投入が必要になったりしたとしても、全体で目標達成できれば、逆に合理的なのです。物流への投資など、売上増により数年で回収できます。
手法だけ真似るだけでは縦割り組織の弊害を排除できない危険も
BSCで目標展開をするなら、全社の税務目標への貢献や顧客視点での目標に寄与するように各組織の目標設定や課題設定をレビューしていかなければなりません。その点で、全社視点で統制をする機能なり組織が必要ですが、残念ながら、こうした点が欠落している企業が多くあります。
全社目標を設定したら、あとはそこから各組織が勝手に目標を展開し、施策を決め、最後に経理か事業企画が数字だけ集計し、形式だけ整えるというのでは、結局対応策が個別組織内で閉じたものになります。結果、タコつぼ化を解消するのにまったく役に立たなくなります。
年度予算策定のように、BSCが単なる全社をあげた年中行事になってしまうと、BSCがBSCとしての意義を喪失してしまうのです。手法だけ導入しても、その使い方を誤るとまったく意味のないものになり果ててしまいます。
現代の日本企業は、全社統制力を喪失しています。道具が良くても、「使い方」がなっていない、もしくは「使い手」がなっていないのでは宝の持ち腐れです。企業を有機的に統制し、マネージし、コントロールするには、別途全社を統合する機能を持った組織の設定とプロセスが必要になります。
BSCは、全社財務目標への貢献や顧客への貢献を考えさせ、個別組織最優先の考え方を改めさせることができる手法です。もし、BSCを採用するのであれば、上手に使って行かないといけません。次回は、組織横断的に目標設定する方法を解説します。