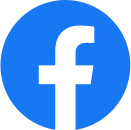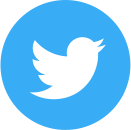日本では「仕事」も「成果」もきちんと定義されていない
私はいままで、会社員としてもコンサルタントとしても多くの企業でプロジェクトを回してきました。その経験からいうと、日本企業は自らの「仕事」を明確に定義できていないと考えています。さらに、明確な「成果」も定義されていないのです。
仕事が定義されているかどうかは、以下の質問に対しイエスと答えられるか、ノーと答えるかで判断できます。
「もし、あなたが突然ある部署に転属になったら、1日以内に1人で仕事ができるようになるでしょうか?」
いかがでしょうか。あなたの仕事が作業であっても、管理(マネジメント)であっても同じです。
この質問に対して、多くの会社での答えはノーです。先輩からやり方を学ぶ、見よう見まねで始める、わからないところは自分で創意工夫をするといった、長い期間の引継ぎが必要になることがほとんどです。
たとえば、私の知っている企業の多くは、部署移動後、1人で仕事ができるようになるまで1週間かかります。下手をすると1か月から数か月、仕事が回せないこともあります。この間、引継ぎと称して無駄な時間が過ぎていきます。
「仕事」が定義されていないと起きること
なぜこのようなことが起こるのか。それは、仕事が定義されていないからです。
たとえば、仕事が作業的なものの場合、自分の経験や勝手な判断で手順を変えたり省略してしまうことがよくあります。
本来であれば、業務マニュアルが整備され、そのマニュアルを読めば仕事が開始できる状態が必要です(トレーニングは別で考えます)。業務マニュアルで仕事が決められ、その手順に従えば「誰でも」、「同じような時間」で「同じような結果(品質)」が得られるようになっていることが重要です。
同じことが現場だけではなくマネジメントにもいえます。多くの場合、何をマネジメントすべきかが定義されていません。前任者からの引継ぎで管理項目を聞きますが、属人化しているので聞くだけで大変です。
聞けたとしても明確な基準がないため、結果的に前任者とはやや異なるフォーマットや仕組みをつくってしまい、そのためのシステム開発、エクセルの山、多重転記入力の洪水が生じ、日本中で付加価値のない作業が繰り返されているわけです。
日本企業の生産性は、このように「仕事」が定義されていないため、生産性低下を招いているといっても過言でありません。
「仕事」が定義されないので非効率になっていく
さらに言えば、「仕事」が定義されていないことで、各人の責任で行うべきタスクが決まっておらず、誰の責任で決まったのかが不明確になります。結果、トラブルが発生するとみんなが巻き込まれ、誰がやったのだという「不毛な犯人探し」が始まります。
問題は個人のせいにされるので、組織的な解決がされず、根本的原因が解消しないので、何度でも同じ問題を引き起こします。組織的な解決として「仕事」を定義して解決しようと試みないで、対処療法だけが行われるのです。これも、「解決策」が「仕事」として定義されない日本企業の悪習です。
また、社員一人ひとりが勝手に好みで「仕事」を決めてしまうため、「その人がやっているから内容はわからない状態」が誕生します。こうなると、その人が休むと仕事が止まったり、遅延すると全体がストップしたり、弊害が大きくなります。
「仕事」が定義されていれば、別の人でも代行できますし、遅れていればヘルプもできていたはずです。
会社の責任として「仕事」を定義すべし
会社は仕事を定義するために、最低限業務フローと各組織の業務分掌、業務マニュアルをそろえるべきです。
さらにいえば、会社が提供したシステムを使うことを強制し、データ改ざんできないように統制することが必要です。余計なシステムや帳票の作成は、相当な上位レベルのマネジメント層の承認がなければ作れないようにし、フォーマットやツールを統一します。そしてこれらを実行するには、経営層の強いリーダーシップが必要になります。
仕事の「成果」が定義されていないと投入時間と品質にばらつきが生じる

もう一つの問題は、仕事の「成果」が定義されていないということです。日本企業では、明確に「成果」が定義されていないので、非効率を生んでいます。
前回のコラム「日本の生産性が低い原因は経営層にあり」では、私の体験談を書きました。売上目標の達成している私に対し、「みんなが残業しているのだからお前も残業しろ」といった上司に代表されるように、いったい何を「成果」として組織や人を評価するのかが不明確で、無駄なことをたくさん行っているのです。
世界的に高い評価を受けている日本の製造現場では「成果」は明確です。たとえば、組立工程や加工工程では1時間に仕上げるべき「出来高」が定義されています。定義された「出来高」を大幅に下回っても、上回ってもダメなのです。「成果」として数値目標が設定され、成果を測る「幅」も設定されているのです。
この「幅」がかなり重要です。大幅に下回る場合は改善が必要ですが、逆に大幅の目標値を上回る場合は過剰効率・過剰品質です。定義された「成果」以上の過剰な結果を求めれば、それだけ時間の投入やエネルギーの投入が増え、計画通りに「成果」をコントロールできなくなるからです。
また、製造現場では「成果」を生むために投入する時間やエネルギーが定義されています。定義された「成果」を生むための「標準時間」、「標準エネルギー投入量」があり、必要以上または以下の投入を避けるのです。こうして、最小努力の最大効果が計画され、実行され、チェックされるのです。
しかし、製造現場以外の多くの職場では、仕事の「成果」が個人の裁量に任せられているので、ある仕事を成し遂げるのに、標準でどれくらいの時間で行うべきかの基準がありません。1日かける人もいれば、3日かける人もいます。その原因は仕事の「成果」が定義されていないからです。
「成果」はアウトプットとインプットで定義する
日本の組織に生じる非効率は、「成果」のためのアウトプットとインプットが定義されていないからです。それぞれは、日本の製造現場では成果を効率とすれば以下のように定義されます。
効率=アウトプット/インプット
アウトプットもインプットも測定可能な数値で定義されます。先の製造業の例では以下のように計算します。
時間当たり出来高=総出来高数/総投入時間
なおすべての変数は、数量、時間、お金、人員数、面積など測定可能な数値で計算されます。
あなたの仕事は「成果」の定義が明確でしょうか?もしそうでないならば、何が成果でどこまでやればいいのか不明確になっていませんか?。
日本の仕事のほとんどは、仕事そのものだけではなく「アウトプット」「インプット」そして「成果」が定義されていません。そのため、結果の検証もあいまいになります。
そこから脱却することが大事です。何があなたの「仕事」で「成果」なのか。これらが明確に定義されていれば、仕事へのモチベーションやスピードが間違いなく上がるはずです。そして定義するには経営層の助けが欠かせません。ぜひ、自身で考えたり上司と話し合ってみてください。