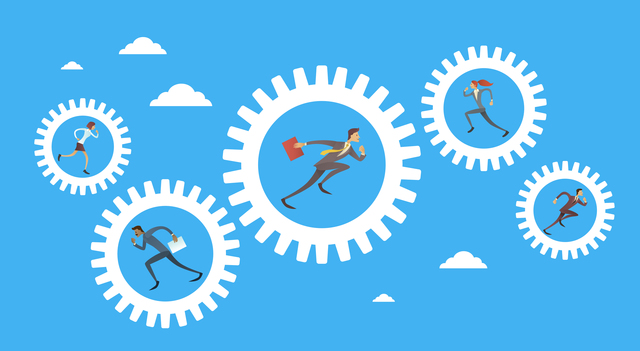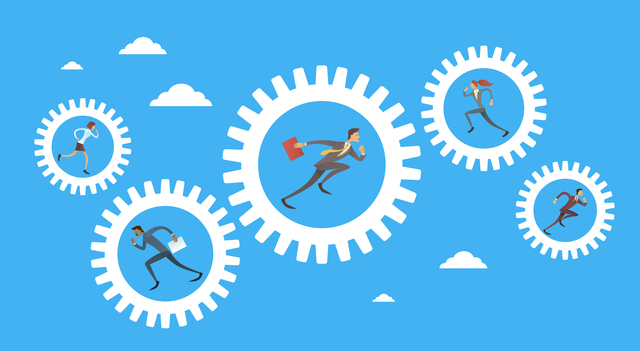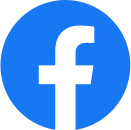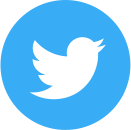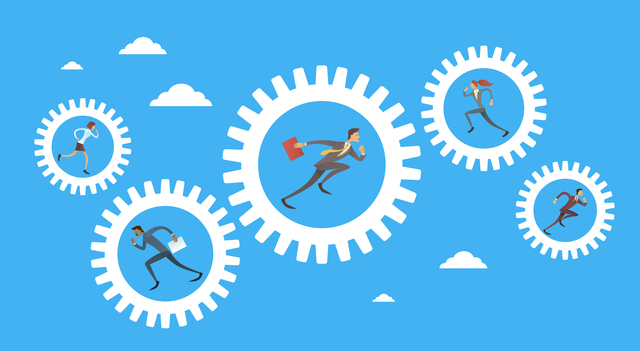
■仕事は誰のためにするのか、心配になる日本企業の実例
突然ですが、私の仕事は企業の業務改革やシステム導入を手伝うコンサルティングです。主に大企業が中心ですが、中堅企業も支援します。
企業を支援していて、ここ数年気になることがあります。それは、組織としての改革・改善能力を失い、リスク嫌悪が激しくなり、その結果競争力を喪失しているように見えることがあるのです。実はこのことに10年前から心配していましたが、この10年で過去私も関わった大企業が続々と破たんしていく様を見ると、いよいよ恐れていたことが始まったかとの印象がぬぐえません。
私が仕事を始めたばかりの25年前、日本企業にはたくさんのエキスパートが揃っていました。ほとんどの人は、会社で何が行われているのかを会社の隅々まで知っていて、コミュニケーションがしやすかったのです。
しかし、今はまったく違います。自分の部署の一部の仕事しか知らない人が増えています。隣の部署が何をしているのかもわからないし、自分の仕事の前後で誰がどのようなことをしているのかわからなくなっています。また、仕事がどのように一回りして完了するのかを知る人が本当に少なくなりました。
かつては数人と話せば業務の全体がつかめました。一方で今は、組織を横断して、何人と話してもヌケ・モレがあり、全体像がつかめなくなっています。
■過去の成功にとらわれすぎる
最近、こんなことがありました。役員に抜擢された方と話した際のでき事です。この会社は、商品の生産がうまくできず、納期遅れを引き起こして業績に影響が出ていました。
私は、営業が計画をたてずに短い期間で生産に指示をかけるため、サプライヤーが部品を作れず工場の生産が安定していないことを把握していました。サプライヤーは需要が読めないこの企業との取引から手を引きたがっていました。
取引量でも価格でも、また、あまった納品物の引き取り保証、あまった生産能力(作業者)の保証でも競合の方がきちんとしていて、この会社と付き合いの優先度は、サプライヤーから見て相当下がっていたのです。
私は、計画的にサプライヤーと連携して部品調達しないと生産の安定はないと考えていたのですが、そうした議論をする前に、この役員は「リスクはサプライヤーに押し付けるのが一般的なサプライチェーン・マネジメントだろう。弊社はもっとサプライヤーをこき使うべきだ」と言い出したのです。
いったいいつの時代の話でしょう。いまでは競合に負け、発注量が減って、取引条件の悪い会社なのです。自社の危機的状況が見えていなかったのです。
質の良いサプライヤーは競合との取り合いです。どうして、パートナーとして仕事ができない傲慢な相手も小さな取引を優先してくれると思うのでしょう。不思議で仕方がありませんでした。
この方は、自社の置かれた位置の変化、周りの企業との関係性の変化を全く見ず、過去の成功を糧に役員に上り詰めたのです。周りを見ない、唯我独尊、夜郎自大なこの会社の今後の苦境が予想されます。
これは決して珍しいことではありません。こういう会社はいま増えているのです。
■机上エリートの蔓延と“保身のための管理=管理のための管理”
別の会社でプロジェクト提案支援を依頼されたときのことです。ある大規模プロジェクトの提案が暗礁に乗り上げていたので私が呼ばれました。うまくいかない原因は単純で、提案依頼をしている顧客の要望を無視していたからです。
顧客は業務改革と一体のシステム改革を望んでいたのですが、作られた提案書はシステムインフラの話ばかりです。データを統合、データベースを統合、ネットワークを統合、セキュリティの話ばかりです。業務とは離れている部分にフォーカスしていたのです。一度だけ私も顧客とのディスカッションに参加しましたが、まさに顧客は業務の話を望んでいました。
さて、業務改革を組み込んだ提案にしようと議論していたところ、このプロジェクト提案に抜擢された部長に私が、「システムは後工程で、業務の件を入れないといけないですよ」とアドバイスしたのですが、結果から言うとこの会社は、ふたたびシステム提案だけをしました。
提案内容の報告が上層部にあがっていっても変わりませんでした。提案は、上層部に行くほど「できるのか?」、「安全か?」、「リスクはないか」と聞かれ、結局、自分たちの理解できないことは報告できないし、問題が起きれば対処できないということで、もとの提案書に戻ってしまったのです。
自分たちが理解でき、安全にできる範囲を考えると、システムの提案を中心にならざるを得なかったのです。そこに顧客の要望を叶える姿勢はありません。競合他社がこのプロジェクトをさらっていったのも当然でした。
顧客の要望ではなく、自社のリスクを最優先して、失敗しないことだけを言い募り、顧客の要求を聞かない姿勢、顧客の成功ではなく自社が失敗しないことを価値の中心に据えた企業が勝ち残れるはずがありません。
「良い提案をしよう」ではなく、「失敗しないように」と“保身のための管理=管理のための管理”に終始していては競争力を失ってしまうでしょう。
■日本企業は内向きで“タコツボ化=サイロ化”している
かつて成功した企業こそ、こうした内向きで、唯我独尊、内部管理ばかり強化していく傾向が強くあります。チャレンジは嫌悪され、失敗は許容されず、内部管理ばかり強化されてお互いに責め合いです。人も育ちませんし、いい人材はとっととやめてしまいます。
たしかに、自部門にこもってあいつが悪い、こいつが悪い、リスクがある、だから言っただろう、といっているのはとても楽です。責任を他者に押し付け続けることで、責任を取らなくてよいのですから。
■潮目は変わり、パラダイムも変わった企業の競争条件
右肩上がりに経済が成長していた時代なら、外部の現実を見ないで内部でつぶしあい、足の引っ張り合いをしていてもなんとかなったでしょう。しかし、時代が変わり、作れば売れる時代はとうの昔に終わってしまいました。
生活を変えるほどの革新的な製品・サービスが一部の企業で生み出される一方、変化が早くなり、その変化に追随し、あわよくば先を越さなければ売上・利益が取れない時代になりました。そのうえ、新興国に追い上げられ厳しいコスト競争にもなっています。
厳しい競争が始まっているのです。変化を読み、外部で起きていることに敏感になり、対応しなければならないのです。内部で足の引っ張り合いをしている場合ではありません。
過去にあった、外国のイノベーションをまねて量産効果でコスト低減して勝つパラダイムは終わっています。
■“タコツボ=サイロ”から出て、仕事を再生しよう
会社の過去の成功の方程式はもう通じません。私たちは、会社や自部門という狭い“サイロ=タコツボ”から出て、過去の延長や自分の都合のいい想像で世界を見ずに、実際に起こっている現実を見なければなりません。
どうすれば、自社が生き残れるのか、さらに言えば、自分自身も生き残れるのか、仕事の仕方をどう変えていけばいいのか、偏見(バイアス)を捨てて、素直に考えなければならないのです。
仕事を再生しなおなければいけない時代になりました。そのためには、繰り返しですが、安全な過去や自部門という“タコツボ=サイロ”から出て、自社の弱みも強みも、もう一度曇りのない目で、謙虚に見なければならないのです。