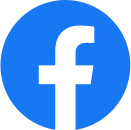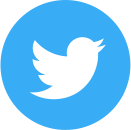(6/30修正 法案が成立し、2017年6月2日に公布されましたので、6月20日時点での内容に本文の内容を更新しました)
(12/15追記 改正民法の施行日が、2020年4月1日となりました。 参考:法務省Webサイト PDF )
■民法改正法案は2017年成立、施行は2020年4月1日
債権関係の民法は、主に、契約に関する私法の基本ルールです。この民法の改正法案は、政府案(閣法)の「民法の一部を改正する法律案」として、2015年3月31日に、第189回国会に提出されました。しかし、国会の法務委員会において、刑事訴訟法一部改正など多数の法案があったため、この改正法案の審議開始は、第192回国会の2016年11月18日にずれ込みました。
法務委員会での審議入りは、日本経済新聞でも報道され(2016年11月16日付)、民法改正へどう対応すべきか話題となりました。その後、衆議院法務委員会で9回ほど丁寧な審議がなされましたが、採決には至らず、2016年12月14日に閉会中審査(次回の193回国会への継続審議)となりました。
2017年1月に招集された第193回国会で、4月14日に衆議院本会議で可決、5月26日に参議院本会議で可決、6月2日に公布となりました。
2020年4月1日に施行されます(2017年12月15日閣議決定)。
法務省は、施行までの間に、十分な周知活動を行うとしています。
■誰のために民法が改正されるのか
契約に関する民法の規定の大半は、「当事者の合意内容が不明な場合に、契約内容を補充する標準的(デフォルト)ルール」です(※1)。
例えば、サービスの提供を受け、または商品を購入した場合、代金を支払います。この代金の支払いのための口座振込の手数料や、通販での代金引換手数料などの費用(弁済費用)は、提供者(代金の債権者)と購入者(代金の債務者)のどちらで負担すべきでしょう。
契約で合意していれば、その合意内容によります。契約での合意がなく、何らかの合意が想定できる事情のない場合、民法の標準的(デフォルト)ルールが適用されて、その結果、代金を支払うための費用は、購入者(債務者,代金の支払いをする人)の負担となります(民法第485条)。なお、契約に要する費用は折半とされています(民法第558条)。
このように、民法は、当事者に公平で、合理的とされるルールを定めています。しかし、民法制定から120年経過し、重要な裁判例や、国際的調和へのニーズなどもあり、適用されるルールが、民法の条文を見ただけでは分からない状態となっています。このため、多くの裁判で採用され、多数の法学者が賛成しているルールについて、考え方を整理し、民法典の条文として明確化する機運が高まりました。
今回の民法(債権関係)改正の大きな目標は、日本民法の適用を受けるすべての人々にとって、民法というルールへのアクセスを良くすることです(※2)。何らかの契約をする際に、「民法にはこう書いてありますね」といった対話がしやすくなり、法律の基本ルールが市民社会に根付いていくことが期待されています。
その結果、契約書の文章を書いたり、契約の内容を読み取ったりする作業(解釈)の多くが、専門家から、一人ひとりのビジネス・パーソンや市民の手にゆだねられていくでしょう。
逆に、今回の改正は、条約に加盟するとか、経済界の強い要望による改正ではないため、国会審議の順番に関する優先度は低く、成立時期が見通しにくい状況となっています。
■民法の一部を改正する法律案(第189回国会第63号)改正の経緯
民法(債権関係,債権法)の改正がいつごろになりそうか、予測の見通しを良くするために、今までの経過と、今後の工程とを、簡単な一覧とします。
・2006年10月 学者グループが「民法(債権法)改正検討委員会」立ち上げ。
・2009年3月末 民法(債権法)改正検討委員会が『債権法改正の基本方針』(別冊NBL 126号)」を取りまとめ。
・2009年10月 法務大臣が、「民法のうち債権関係の規定について国民一般にわかりやすいものとする等の観点から、見直しをする要綱を示されたい」旨を諮問。
・2009年11月から2015年2月 法制審議会 民法(債権関係)部会が99回、分科会が18回開催される。
・2011年4月 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」を開催。パブリックコメントを実施。
・2013年2月 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」を決定。2回目のパブリックコメントを実施。
・2014年8月 「民法(債権関係)改正に関する要綱仮案」を決定。
・2015年2月 「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」を決定。
・2015年3月 政府 民法の一部を改正する法律案を閣議決定。
・2015年3月 第189回国会第63号民法の一部を改正する法律案が内閣提案(閣法)として国会に提出される。
・2016年11月 第192回国会 衆議院 法務委員会で審議入り。8回審議され12月会期末に継続審議となる。
・2017年4月 衆議院 法務委員会で採決・付帯決議
・2017年4月 衆議院 本会議で採決
・2017年5月 参議院 法務委員会で採決・付帯決議
・2017年5月 参議院本会議で採決
・2017年6月 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の公布(官報号外第116号)
・2017年12月 施行日の決定
・2020年 4月 改正された民法の施行
■民法(債権関係)改正のポイントを把握する3つの切り口
それでは、今回の改正法のポイントはどこにあるでしょうか。条文については、国会で審議中の法案を「改正後の民法」と略称します(※3)。
専門用語や、業務委託契約の実務への影響は、今後の記事で、できるだけわかりやすく紹介していきますので、この記事では、専門的な用語は読み飛ばしてもらって大丈夫です。今回の記事では、まず、民法(債権関係)の改正についての全体的なイメージをざっくりとお伝えします。
民法(債権関係)の改正は、(1)考え方の一本化、(2)原則や通説の明文化、(3)規律(ルール)の現代化の3つの切り口で理解できます。また、全体を通して、諸外国で行われている民法改正に対して、日本からの情報発信となっています。
(1)第1の切り口「考え方の一本化」
改正後の民法では、細かく分かれていた規律(ルール)を整理して、考え方の統一を図っています。一元化・一本化といわれています。
・改正法は、瑕疵担保責任(の法定責任説)を廃し、契約不適合による債務不履行に一本化しました(改正後の民法562条・564条・565条の前提)。
・改正法は、履行不能時の危険負担による契約の解除(の債権者説)を廃し、契約の解除は催告又は無催告の解除に一本化しました(改正後の民法541条・542条)。
・改正法は、消滅時効について、短期消滅時効の規定を廃するなどの整理をして、権利行使できることを知ってから5年間、権利を行使できる時から10年間、行使しないときに消滅する制度に一本化しました(改正後の民法166条)。
・改正法は、破産法の否認権にあわせて、詐害行為取消権の規律を整理しました(改正後の民法424条)。
(2)第2の切り口「原則や通説の明文化」
今回の改正法では、私法上の重要概念である契約自由の原則(改正後の民法521条)や、債務者が債権者に弁済した際に債権が消滅するという原則(改正後の民法473条)を、民法の条文として、明文化しました。さらに、判例・通説による法理が、下記のように明文化されます。
・意思能力を有しない人の法律行為は無効であること(改正後の民法3条の2)。
・瑕疵担保責任に関する法定責任説(特定物ドグマ)は採用されず、契約責任説が採用されていること(改正後の民法562条・565条)。
・売主は、買主に対して、登記、登録その他の権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うこと(改正後の民法560条)。
・登記のある不動産賃借権に基づいて不法占拠者を排除できること(改正後の民法605条の4)。
(3)第3の切り口「ルール(規律)の現代化」
その他、民法の規定として、諸外国の民法改正動向も調査し、判決や学説で指摘されてきたことを踏まえて、ルール(規律)の現代化が図られています。
・消滅時効の内容が整理された他、条文上の表現がわかりやすく修正されました(改正後の民法147条等)。
・法定利率を3%としたうえ、変動制を基礎としました(改正後の民法第404条)。中間利息の控除も明文規定が新設されました(改正後の民法417条の2)
・定型約款の規定が新設されました(改正後の民法548条の2から548条の4)。
・保証人を保護するための規定が新設されました。例えば、事業に係る債務についての保証は、公正証書での意思表示を必須とする(改正後の民法465条の6等)などです。保証人への情報提供(改正後の民法458条の2等)についても新しいルールができました。
■民法(債権関係)改正のまとめ
今回の民法改正の趣旨について、東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授の中田裕康先生が、短くわかりやすくまとめています。
「今回の法案は、穏やかな改正ではありますが、民法の規律を明らかにし、現代化するものです。国際的な潮流に沿うものでもあります。」
(中田裕康・衆議院法務委員会,2016年12月7日)。
民法のルールは、あなたの権利や財産を守ると同時に、あなたの行動を制限します。そのルールの内容を、より分かりやすい日本語で条文にしていこう、というのが、今回の改正の大きな目標なのです。
改正後の民法521条は、次のように規定しています。
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる(1項)。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる(2項)。
契約の締結及び内容の自由が、このように比較的読みやすい文章で明文化されました。例えば、契約内容は自由なので、振込手数料を債権者負担としても、折半としても有効です。合意がない場合に、デフォルトルールである民法485条が補充的に登場し、債務者が負担すべきとなります。
この契約の締結及び内容の自由が制限される局面は、さまざまあります。例えば、他者を奴隷として扱う契約や、麻薬など違法物質の取引をする契約などは無効となります。一定の上限を超える金利は、有効性がなく、当事者間で合意したとしても、裁判で強制的に支払を求めることができません。住居を借りる人や、労働者や、消費者を保護するための強制的なルールもあります。
この契約自由の原則の限界となる「法令の制限」は、民法だけでなく、多数の法律(特別法)で定められています。労働法、消費者保護法、借地借家法などです。今回の民法(債権関係)の改正では、これら特別法による強制的なルールに大きな変更はありません。
今回の民法改正に対するスタンスや注目点は、それぞれの業界によって異なっておりますが、最も影響を受ける典型契約は「請負」であり、業務委託契約のひな形を維持するか否か、新たな契約での留意事項がどう変化するか、などの判断が必要となります。
これから、民法(債権関係)改正を紹介する数回の連載で、ビジネスの実務への影響を紹介していきます。民法は一部専門家のためにあるのではなく、経営者・営業担当などのビジネス・パーソンや、市民社会を構成する一人ひとりのためにあります。それぞれが、法により守られる点と、法により制限される点とを知ることで、将来の紛争を予防するために、契約締結までにできることや、契約した通りにならなかった際の対策を整理していきます。
次回は、経営者・営業担当に知っておいてもらいたい改正のポイントをご紹介します。なお、個別の契約書のリーガル・チェックなどは、お取引のある弁護士へご依頼をお願いいたします。
※1 下記参考文献(3)道垣内p120、下記文献(6)大村・債権編p26
※2 下記参考文献(1)内田p238
※3 国会に提出された法律案についての説明となりますので、審議の進展に応じて、条文の番号や文章表記は、修正の可能性があります。
参考文献
民法と、改正に至る方針・試案や法案との関係がわかる書籍を紹介します。
(1)債権法改正の基本方針 内田貴『債権法の新時代』(2009.9,商事法務)
基本方針の概要、諸外国の民法改正の動向に対する危機感などがわかりやすく説明されています。
(2)債権法改正の基本方針 潮見佳男『基本講義 債権各論〈1〉契約法・事務管理・不当利得』(2009.12,第2版,新世社)。
通説の代表的教科書で、本文中で適宜「債権法改正の基本方針」(民法(債権法)改正検討委員会の試案)の方向性について言及されています。
(3)中間試案 道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門』(2014.1,初版,日本経済新聞社)
民法の入門書ですが、改正前民法の論点や通説を紹介したうえで、中間試案の方向性がコラム的に紹介されています。
(4)中間試案 中田裕康『債権総論』(2013.8,第3版,岩波書店)
債権総論の教科書で、中間試案の内容が紹介されています。
(5)民法(債権関係)改正法案 潮見佳男『民法(債権関係)改正法案の概要』
逐条的に改正法案の条文と解説が紹介されています。立法担当者よりも一段深い法解釈が示され、条文の書きぶりについて、立証責任との関係での意味なども紹介されています。
(6)民法(債権関係)改正法案 大村敦志『新基本民法 債権編・契約編』(2016.7,初版,有斐閣)
4債権編と、5契約編は別の書籍です。文献紹介も詳しい民法の入門書で、通説と論点が紹介されたあと、改正法案が紹介されています。改正法の条文番号は案○条なっています。
(7)改正法への批判 加藤雅信『民法(債権法)改正―民法典はどこにいくのか』(2011.5,日本評論社)
法学部教授で政府の審議会委員も歴任し、弁護士でもある加藤教授による批判書です。加藤教授は、衆議院法務委員会の参考人として招かれ、改正法の問題点を指摘しています。